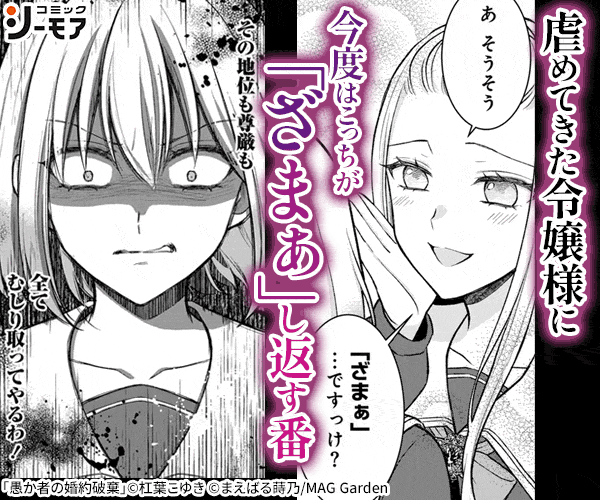6・ぱぱのたいせつな、ままのもの
「えっ」
――その瞬間。
キッチンにあったものが浮かび、私に向かって飛んでくる!
『魔力暴走』だ!
「っ……!!」
反射的にユーグカがしまった! という顔をする。
わかる。こうなったら彼女にも止められない。
「――大丈夫ですよ」
飛んでくるフライパンにりんごに、包丁に網。
私は落ち着いて、それらに向かって手をかざす。
ぴた。
瞬間、時を止めたように物たちは動きを止める。
「はい、これで元通りです」
私がさっと手を払うと、元の場所に静かに戻っていく。
「え……あ……」
がたがた。しゃがんだまま震えているユーグカに近づく。
彼女は小さな声で、ごめんなさい、ごめんなさいと呟いていた。
「ごめんなさい、ゆーぐか、わるいこなの。ごめんなさい、また……わーってなって……」
「……ユーグカお嬢様……」
その姿で、私は全てを理解した。
彼女は『大自在の魔女』の力を制御できない。
生まれた環境も、その後の環境も、決して彼女にとって穏やかで落ち着いたものではない。
突然生まれて、父に愛され。その父は具合が悪く、傍で見ていることしかできない。
使用人は次々と辞めていく。『幽霊古城』の噂からして、きっと酷い言葉もかけられたのだろう。
シュヴァルツも言っていた。後妻を狙う女性達がやってきてはユーグカを傷つけていたと。
彼女はずっと傷つきながらも、父親を守ろうとしてきたのだ。
『大自在の魔女』の力がどんどん不安定になるのは当然だった。
――ごめんね、傍にいなくて。私がずっと傍にいるから。
「ユーグカお嬢様」
「っ……!」
ぎゅっと、私は抱きしめた。
「大丈夫ですよ、大丈夫。まずは息を吸って、吐いてしましょう」
「……っふえ…………」
「すー……はぁ……すー…………はああ……」
「ね? どきどき、とまってきますよ。大丈夫」
小さな背中を撫でる。とくんとくんと、早鐘を打っていた鼓動が穏やかになっていく。
少し体を離して顔を見ると、ユーグカの顔は落ち着いていた。
「もうこれからは、『魔力暴走』させてもいいですよ」
「えっ」
「ああでも、包丁や、危ないものがある部屋ではやらないお約束です。廊下とか、他のお部屋ならいいですよ」
大きな青い瞳が、私をじっと見つめる。
「いーの?」
「はい、失敗を繰り返して覚えていくんです。おこられる、おこられる……と頑張っても、『魔力暴走』させてしまうのはとめられませんでしたよね」
「うん……ゆーぐかが、わるいこだから」
「違います。がんばってもうまくできないなら、仕組みを変えるんです」
私はきっぱりと言う。
「うっかり暴走させても怒ったりしません。どんなときに暴走させちゃったのか、どうすれば我慢できたのか、ひとつひとつ一緒に確かめていきましょう」
「でも、おしろのなか、ぐちゃぐちゃで……めいどさんたち、ちっとかいってたし……」
「私がお片付けします。お掃除するためにメイドがいるんですから」
「……おこらない?」
「はい」
「ほんと……?」
「もちろんです」
彼女の顔が驚きに満ちている。
これまで、使用人達に怖がられてきた。心ない言葉もいわれたことがあるのかもしれない。
シュヴァルツはあの体調だから、頼ろうと思っても遠慮するのだろう。
そもそも、魔力暴走の制御方法なんて私しかしらない。だって私とユーグカは、現時点で世界でたった二人だけの『大自在の魔女』の能力者なのだから。
「私が傍にいるからには、ユーグカお嬢様もシュヴァルツお父様も、たっぷり幸せにしますよ」
「……ありがとお」
ユーグカは極上のふにゃっとした笑顔を見せた。
ハリネズミのように武装していたちくちくを、ようやく脱いでくれた笑顔だった。
「あのね、りーべるねーには、みせてあげゆ」
すくっと、ユーグカは立ち上がる。
そして床に落ちたノートを手に取る。
茶色く黄ばんだ古いノート。それは私がさっき出そうとした棚から飛び出した、古いレイラのノートだった。
「これ、ぱぱのだいじなもの。あけちゃいけないばしょ」
「もしかして、私が大切なものを出そうとしたから、びっくりして暴走させちゃったんですか?」
こくん。ユーグカはノートを抱きしめたまま頷く。
「お母様の大切なノートがそこにあると、ご存じだったんですね」
「ゆーぐかにままのこと、のこったものでしかみせられないからって。ぱぱは、ままのもの、とてもだいじにしてるの」
「もしかして、他の使用人が捨てようとしたりしたこともあったんですか?」
「……うん」
ああ、だから不安だったのか。
「私は捨てませんよ。だってユーグカ様と旦那様の大切な思い出ですもんね」
「ほんと?」
「ほんとです」
ユーグカの肩からほっと力が抜ける。
私は嬉しくなる。
「ところでお夕飯ですが」
そして話を戻した。お腹がぺこぺこだと、気も立つだろう。
「ノートを出そうとしたのは、ユーグカお嬢様の夕食のヒントを探したくてなんです。お母様のノート、少し開いてもよろしいですか?」
「いいよ」
「しつれいします」
彼女がそっと私に手渡してくれる。ページを傷めないようにそっと開く。
ユーグカも中を覗いてくる。
「ゆーぐかもね、よむのははじめてなの」
「そうなんですね」
レイラは公爵令嬢だったが料理もできた。宮廷魔術師として生活能力は必須だったからだ。
「まま……」
ユーグカがママ(レイラ)に思いを寄せている。
私はいつの間にか、前世彼女を生んだような気分になっていた。
もしかしたら――シュヴァルツに家族を作りたいと思う願いが、最期に奇跡を残してくれたのかもしれない。
「りーべるねー、よんでー」
「はい。これはリゾット。これはハンバーグ。これはお野菜のスープに……」
ユーグカが、すみっこに描かれたオムライスに指を向ける。
丸いオムライスにハートを描いた、レイラの得意料理だった。
「これかわいいね」
「食べたいですか?」
「りーべるねー、つくれるの?」
「メイドですから!」
「わーい!」
私はノートを彼女に返し、手を叩く。
一斉に食材や調理道具がふわっと浮かび上がる。
「……ひゃあ!」
目を丸くするユーグカ。私はにっと笑った。
「お見せいたします。これが『大自在の魔女』の能力の使い方ですよ」
縦横無尽に宙をかけめぐる、たまねぎににんじん、たまごに、フライパン。
コンロは自然と炎を灯し、ハート型の炎がバターを溶かす。
料理人が保存したままのご飯が炒められる。野菜が次々と包丁で刻まれる。
とろとろの卵が宙でハート型を描いてチャーハンにのる頃には、ユーグカは先ほどの涙も嘘のように、興奮した顔で手を叩いていた。
「すごいねー! すごいねー!」
興奮しても、『魔力暴走』は起こさなかった。