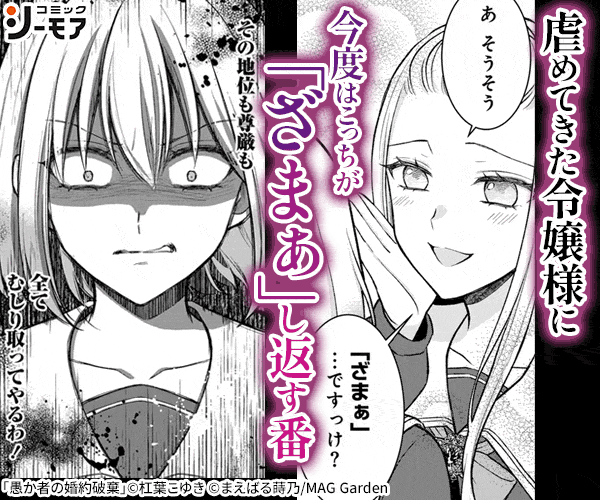43・子供を守る大人でありたい
「お前の父親はおそらく『才なし』だ、リリーベル」
ギルバートが単刀直入に言った。
「シブレット男爵は『才なし』を隠し通すべく魔術師家系の娘と結婚しようとしていたのだろう。娘側の血で強い魔力の子供が生まれれば誤魔化せるからな。だがお前は不幸にも『才なし』で生まれ、あの男のプライドを傷つけた。悪いのはもちろん傷ついた父親の側だ。お前は被害者だ」
うっすらと感じていた違和感の理由はそこだったのか。
父は異常に『才なし』の私を嫌悪し、『大自在の魔女』の力も『悪霊憑き』と疑った。
悪霊信仰はどちらかというと民間宗教で、父のような人は非魔術的だ、迷信だと言いそうな発想だった。
(彼は自分が『才なし』だから、娘の判定に過敏に怒った。同時に『才なし』が遺伝したと思い込んでいるから、私の能力を『大自在の魔女』の力かもしれないと考えが及ばなかった)
私を生んだ母デルフィや母方のフロレゾン男爵家に対する酷い態度も、後ろめたい秘密があるからだ。
母は酷い扱いを受けて死んだと言うし、父は遺骨も返さないとまでいう。
そして継母と異母妹に対しても、魔術についてかなり強い教育を求めていた。
あのヒステリックさは己の能力不足を隠すためなのだと思ったら理屈が通る。
そこまで考えて、疑問が浮上した。
「でもよく……『才なし』で仕事できていますね? 職務からして、それは難しそうですが」
「問題はそこだ」
ギルバートとシュヴァルツ、二人が険しい顔になった。
「俺たちは不法なことをして魔力を増やしていたのではと疑っている。思い当たる節はないか?」
「うーん、不法なこと……」
「どんな小さな事でもいい。妙なことがあったら教えて欲しい」
身を乗り出すシュヴァルツ。私は視線をあげて考えた。
「確かに……怪しい魔道具商人は屋敷に来ていましたね。私は詰めたり入れたり磨いたりする内職をさせられていました。魔道具自体は普通の魔道具だったんですが……魔道具職人がわざわざ遠くから、個別に男爵家にわざわざ内職を頼むっておかしいですよね?」
今思えばおかしい。
私は『大自在の魔女』の能力の練習に使っていたので気にしなかったし、地方の男爵家の常識なんてよく知らなかったから「そんなものかな」と思っていたけれど、あんな田舎に大量の魔道具の内職なんて、妙と言えば妙だ。
「私を養うお金を出したくなくて、私に自分の食い扶持ぶん働かせていたのかもしれませんけど……」
「念のため調査をしよう。また何か思い出したことがあれば言ってくれ」
「わかりました。……あ」
「あ?」
二人の視線が私に向く。
今思いついたことを話していいか悩む。レイラとしての知識込みでの想像だからだ。
でも口にしちゃったからには仕方ない。私は言葉を選びながら続けた。
「えっと……本で読んだんですけど、禁術の一つに……魔物の力を飲んで……一時的に魔力を強くする方法って、ありませんでしたっけ」
「お前、どこでその本を読んだ?!」
ギルバートの剣幕にたじろぎつつ、私は答える。
「れ、レイラ奥様の遺品です。確か『禁術大全』の五巻……だったと思います。ええと、ミントローズ・パルスレー辺境伯令嬢に整理をおまかせしていたので、彼女に聞くともっと具体的な話が分かると思います」
「そうか」
ギルバートはそれだけ言い残し、杖をカツカツと鳴らして足早にさっていった。
部屋には私とシュヴァルツが残る。
(すごい剣幕にもなるわよね。魔物を飲んで魔力を強くする方法って、確か最終的に人間が魔物になっちゃって自我を失って暴れる、だいぶん危険な薬だもの)
「部屋に送るよ」
「ありがとうございます」
私たちは二人で歩いた。
先ほどの緊迫した名残が残っているので、空気が固い。
ふと、シュヴァルツが独り言のように呟いた。
「でも……よかった」
「旦那様?」
「これでシブレット男爵がなんと言おうと、君と縁を切らせることができる」
穏やかな声音だけど、その眼差しは穏やかならざるものだった。
深い嫌悪感と怒りが、瞳の青を暗い色に染めている。
きっと己の過去を重ねて、リリーベルという子供に同情してくれているのだろう。
(心配かけてごめんなさい。リリーベルの過去を、怒ってくれてありがとう)
シュヴァルツの瞳が柔らかくなる。いたわるように、私の頭をそっと撫でた。
「すまない。君はまだ幼いのに……色々と、大人の都合に巻き込ませてしまって」
「いえ、大丈夫ですよ。と言いますか、そもそも自分の経歴に関する話なので」
「……大丈夫にさせてはいけないんだ。本来は」
私が強がっているようにみえたのだろう、彼は自分が傷つくような顔をした。
「話を進めているが、君は無理をしていないだろうか。我々大人ばかりが急いて状況を変えようとしているが、君の心の安寧が一番大切だ。義兄上も私も一刻も早く解決したいと思っているが、辛いときはいつでも言って欲しい」
「旦那様……」
シュヴァルツは自嘲的な笑みを浮かべ、肩をすくめた。
「僕は……レイラに守ってもらっていたのにな。ユーグカにも長くさみしい思いをさせて、君に助けられて。まだちっとも、理想の大人になれていないよ」
(そんなことないわ。あなたは立派よ)
レイラとしてシュヴァルツを抱きしめて、慰めてあげられないのが、ちょっと歯痒い。
「大丈夫、君はちゃんと我々が守るよ」
私が不安そうに見えたのだろう、シュヴァルツは私の頭をそっと撫でた。
「君はまだ9歳だ。しっかりしているからこちらも甘えて大人扱いしてしまうが……つらいときは、いつでも相談しなさい。私も魔力で実家に利用されて生きてきた。だから君の辛さは少しはわかるつもりだ。もちろん今すぐじゃなくてもいい、いつでも君が大人に頼りたいと思った時、不安になったときは力になる。それだけは覚えていてくれ」
「ありがとうございます」
その時。
シュヴァルツの様子がおかしいと、私は気付く。
「……旦那様?」
うつろになっていく瞳。お酒でも飲んだのかしら、と思ったけれど違う。
――魔力枯渇だ。
「旦那様!」
ぐら、と倒れかける体を抱き留める。
『大自在の魔女』の力を使う余裕もなく、私はシュヴァルツを抱えたまま、思いっきり倒れ込んでしまう。
「あたた……だ、旦那様?」
「…………」
シュヴァルツの返事はない。熟睡していた。
倒れ込んだせいで寝顔は顔のすぐ傍にあった。せっかくなのでシュヴァルツの顔を眺める。
大人になってはいるけれど、その寝顔はかつてのシュヴァルツの面影がある。
昔もこうして頑張りすぎるきらいがあった。
(私を守るために訓練をし続けて、いつも最後は訓練場でばったり倒れていたっけ。
いや、あの頃から危なっかしいわね、この子。
――だから一緒にいて守ってあげなくちゃ、って思ってたんだっけ……。)
「もう。限界まで働いちゃだめじゃない。またユーグカを一人にするつもり?」
私は頭を撫でる。
熟睡しているからいいだろう。
「……限界まで、リリーベルのために頑張ってくれてありがとう」
大人になっても、頼もしい父親になっても。
愛する人の寝顔はあいかわらず可愛いと思った。
しばらくすると、音を聞きつけた使用人の皆さんが廊下の向こうから何人もやってきた。
私は手を振って助けを求めた。
「すみません! たすけてくださーい……旦那様が倒れちゃって……」
大自在の魔女の力で起き上がってもいいけれど、今はシュヴァルツを受け止めるのが心地よかった。
お読みいただきありがとうございました。
おかげさまで8000ポイント超えました!ありがとうございます……!!
楽しんで頂けましたら、ブクマ(2pt)や下の⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎(全部入れると10pt)で評価していただけると、ポイントが入って永くいろんな方に読んでいただけるようになるので励みになります。すごく嬉しいです。