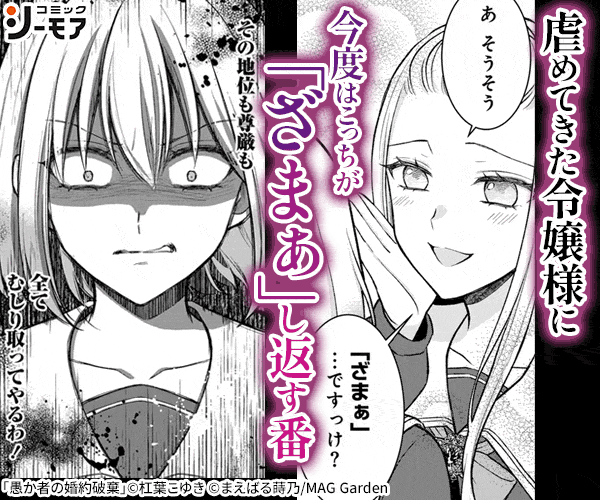40・ユーグカの不安、懐かしい実家
セージと研究所の皆さんに見送られ、私たちは王都へと向かった。
旅は鉄道と移動魔石を使ったもので、翌日夜には王都に到着しアンドヴァリ公爵家に入った。
行きすがら、シュヴァルツが説明してくれた。
「私の王都屋敷は複数あるが、どれも宮廷魔術局に貸し出していて、宮廷魔術師達の寮になっている」
「ええと……リヒトフェルト魔術伯としてご所有の屋敷と、ご実家のローゼンベルク侯爵位に紐付いた屋敷、ですっけ」
彼は頷く。
「ユーグカを連れて王都に長居することもなかったし、余らせておくくらいなら貸し出した方が屋敷も傷まない。魔物騒乱の影響で家財を失った魔術師は多い。王都に寮があれば、王都に身を寄せるあてがなくとも王都で働くことができる」
魔術師はこの国の要だ。育成のために余っている屋敷を貸し出すのは家持ちの宮廷魔術師として理に適っている。
「そもそも両方とも、私の『帰る家』という意識が薄いからな……」
――リヒトフェルト魔術伯としての屋敷は元々アンドヴァリ公爵家所有のものだ。
シュヴァルツが魔術伯の爵位を得た時、彼には領地も財産もなかった。魔術伯が世襲の爵位ではなく、功績により新たに授与されたものだからだ。そのためレイラが嫁いだ際、持参金が代わりに公爵家の所有地をシュヴァルツが譲り受けたのだ。
もう一つのローゼンベルク侯爵屋敷はシュヴァルツを利用し破滅した実父の家。
当然、帰る家と感じるわけがない。
(実際のシュヴァルツの生家は貧民街で壊されていて、もう残っていないものね……)
シュヴァルツは膝のユーグカに目を落とす。
長い移動で疲れたユーグカは、シュヴァルツに膝枕を借りてすよすよと眠っている。
「私にとっての家は湖上の古城と、レイラの実家アンドヴァリ公爵家だけだ」
◇◇◇
屋敷では先日会ったばかりのアンナアンナに出迎えられた。
久しぶりの実家は内装が改められ、アンナアンナ好みの明るい調度で整えられている。
到着したときは、すでに生まれたての赤ちゃんと双子は眠っていた。顔合わせは「つどい」からになりそうだ。
家主のギルバートは宮廷魔術局に泊まり込みらしい。相変わらずのワーカホリックだ。
アンナアンナがシュヴァルツに詫びる。
「ごめんなさいね、ギルバートは宮廷魔術局に泊まり込みなの」
「相変わらず仕事熱心ですね、義兄上は」
「シュヴァルツくんも今度言ってあげて? 魔術を使わずとも、過労でも人は倒れるのよって」
「はい、倒れていた私が言って説得力があるかは分かりませんが」
「あらやだ」
初めての場所にきらきらと目を輝かせていたユーグカだけど、やっぱり慣れないのだろう、夜は私に添い寝を求めてきた。
「りーねー、いっしょにねよ」
普段はメイドとお嬢様だけど、今回のつどいは私も男爵令嬢として参加するし、メイド服以外のドレスを着て過ごすことになる。
マナーとしても問題ないということで、堂々とベッドを共にした。
寝室としてあてがわれたのは、レイラの寝室だった。
家具もカーペットも、死後10年経過しているとは思えないほど綺麗に整えられている。
一瞬、自分がリリーベルではなくレイラだと錯覚してしまいそうだ。
「ここはママのベッドですよ、ユーグカ様」
「ままの? 」
キラキラの瞳であちこちを見て回るユーグカ。母の面影を追い求めているようだ。
私は懐かしい気持ちでベッドに触れる。ユーグカがベッドに潜り込むと、レイラとうり二つなのも相まって、昔の自分がそこにいるかのようにみえた。
「りーねーも、ここ」
隣をぽんぽんと叩かれて、私も一緒に入る。
見慣れた天井、見慣れたベッド。腕の中に入ってくる小さなぬくもりにじんわりと母性が満たされていく。
産んだ覚えもないのに、シュヴァルツと自分の子供だと本能的に感じる。
自然と互いの魔力が溶け合って、目を閉じると心地よい。いつもの添い寝より、ずっと近くに感じられた。
(どんな運命のいたずらか知らないけれど、私はユーグカの傍にずっといたいわ)
満たされた気持ちでいると、ユーグカがつんつんとつっついてくる。
「りーねー、おきてる?」
「はい、起きてますよ」
「あのね。……あしたね、ほかのことね、あっても、だいじょうぶかな」
私は思わず腕の中の顔を見た。
夜の闇と慣れない環境がそうさせているのか、ユーグカの不安そうな顔を久しぶりに見た。
手をもじもじさせて、こわごわと尋ねてくる。
「あのね、はじめてのこにね、びっくりさせたりとか、『だいじざのまじょ』のちからがね、わーってなって、こわしちゃったり、したら……こわくて……おともだち、できるかな」
「ユーグカ様、不安だったのですね」
「うん」
ユーグカの青い瞳に、じわっと涙が湧いてくる。たまらず私は抱き寄せた。
腕の中で、ユーグカはたどたどしく続ける。
「おしろのめーどさんもね、こっくさんもね、みんな、ゆーぐかのことこわがってたから……りーねーとか、みんとしゃんとか、ゆーぐかのこと、こわがらないひとたちがいっぱいだったからわすれてたの、どうしよう……こわい……」
「怖いお気持ち、いっぱい伝えてくれてありがとうございます。そうですね、怖いんですよね」
私は受け止めながら、腕の中の頭をゆっくりと撫でる。
「いつもと一緒ですよ、大丈夫です。私も旦那様も傍にいます。ミントローズさんも公爵夫人もいます。なにより、ここは……お母様のおうちですよ。おうちと同じくらい、絶対大丈夫な場所です」
「だいじょーぶ?」
「はい」
私は『大自在の魔女』の力を使い、二人が横たわるベッドを浮かせる。
ゆらゆら。ゆれてもびくともせず、布団もクッションも何故かぴったりと吸い寄せられるように落ちない。
「わあっ……!」
「レイラ奥様はよくこうして遊んでいたそうです。アンドヴァリ公爵家は『大自在の魔女』の力が暴走しても壊れないようにしっかり対策してあるんですよ。湖上の古城よりも実はしっかりしてるんですよ。まだ幼い頃のレイラ奥様がお住まいでしたので……それっ!」
私はベッドをそのまま、くるっと横に一回転させる。
腕の中でユーグカが楽しそうな声をあげた。
「すごい! すごいねー!」
ぱちぱち。ユーグカは手を叩き、すっかり不安が取れて、はしゃいだ声をあげる。
「使用人の皆さんも『大自在の魔女』の力に慣れています。今日も嫌な思い、しなかったですよね?」
「うん、みんなやさしかった」
「『つどい』でも皆さんが味方です。もちろん私も旦那様も一緒です。ユーグカ様は安心して、にっこりわらってご挨拶すればいいんですよ」
「おともだちできる?」
「はい!」
私はぎゅっと抱きしめる。
「レイラ奥様もお友達はたくさんいましたよ。娘なんだから大丈夫です」
「そっかー……」
ユーグカの体からは、すっかりこわばりは消えていた。
「りーねー、あした、いっしょだからね? おててにぎっててね? なにかぼうそうしそうになったら、たすけてね?」
「はい。暴走なんてさせませんよ」
私は強く頷いた。ユーグカの体からすっかり力が抜ける。
きゅーっとくっついてきて、彼女の体温が密着する。
「がんばるね、りーねー」
「はい!」
疲れていたのだろう、それからすぐ、ユーグカは眠りに落ちていった。
◇◇◇
――翌朝。
私たちは一緒にくっついて目を覚ました。