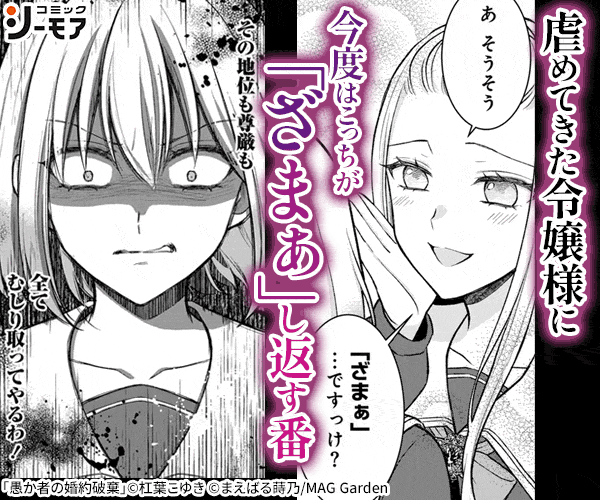38・その頃の実家/カトリネ視点◇◇◇
――フロレゾン男爵家の遣いが来て数日後。
カトリネは夫のいない間に、そっと倉庫の中に忍び込んだ。
カトリネは一度も夫に逆らったことがなかった。
家庭内暴力も恐ろしかったが、何より実家オストマヌ侯爵家への報復を考えるととても逆らえなかった。夫は没落したオストマヌ侯爵家に金を貸してくれた。だから夫には逆らえなかった。
けれど。
カトリネはフロレゾン男爵家の遣いから握らされた一通の手紙を握りしめる。
書いてあることが本当なら、夫に怯えている場合ではない。
意を決して倉庫の木箱を開き、カトリネは思わず口を押さえた。
そこには手紙の通り、暗がりでもぎらぎらと輝く、明らかに違法なポーションが隠されていた。
――夫シブレット男爵は己の『才なし』を隠すために、魔術師家系の娘を娶っている。
エリファに魔力がなければ、彼女はポーション漬けにされるかもしれない。
手紙に書いてあった内容の一部が、頭の中に浮かぶ。
「うそでしょ……嘘……」
「お母さま……?」
反射的に振り返る。
エリファが倉庫の中を不安そうに覗いていた。
母の姿が見えずに不安になったのだろう。
「エリファ……!」
反射的に、カトリネは娘を抱きしめた。
「っ……お母さま……?」
最近抱きしめられていなかったエリファは、予想外の抱擁に驚く。
「どうしたの? お母さま……なにかこわいの?」
娘はこちらを心配してくれている。
がたがたと、エリファは体の震えがとまらなかった。
娘は急にはっとして、表情を陰らせた。
「ごめんなさい。わたしが魔力じょうずにつかえなかったから、おこってるんだよね」
「……そんなことないのよ、……違うのよ」
カトリネは己の愚かさに気付いた。
エリファは常に、自分に喜んで貰うために魔力を頑張っていた。
うまくできないエリファを張り飛ばした。
才能があるレイラ・アンドヴァリのような子供だったらどんなによかったかと思った。
愚かだった。
自分も、影で恐ろしい事を考えている夫と同類なのだ。
――能力がなければ、意味が無い。リリーベルのように捨てても仕方ないのだと。
――こんなに優しい娘に、自分は。
「ごめんなさい……ごめんなさい」
泣き始めた母に対し、エリファは不安そうに見つめていた。
――夜。カトリネは帰宅した夫に、王都出張に同行したいことを申し出た。
「お前とエリファが? なぜ」
案の定怪訝な顔をされる。
カトリネはフロレゾン男爵家の遣いの入れ知恵をそのままに、必死に笑顔を作って言った。
「魔術検査前に王都を見せてあげたいんです。魔術検査本番前にどんなところか見せていると、魔力が出やすいと思うんです……」
ジョアンはこちらの顔をじっと睨んでくる。
しばらく考えた後、ジョアンは頷いた。
「確かに娘に良縁を掴ませるためには、早い内から顔を覚えられるのは大事だろう」
「じゃあ……!」
「同行を許す。だがこちらの邪魔はするなよ。あと旅費はお前の金からだせ。あと王都に行くつもりならエリファの魔力開花に励めよ。いいな」
「わかりました。もちろんです」
その後、カトリネはすぐにエリファに伝えた。
「エリファ。こんど王都に行くのよ。だからその日まで、お父様の機嫌を損ねないように言うことを聞くのよ」
「王都……? なにをするの?」
「たのしいことがいっぱいあるわ。きっと……あなたにとっても、いいことが」
カトリネの興奮した様子に、エリファも無邪気に喜んで、父親にありがとうと伝えに行った。
ジョアンは娘を見て微笑みながら頭を撫でている。
カトリネはぎゅっと胸を掴み、嫌悪感を飲み込んだ。
(娘に触らないで。娘をリリーベルのように、捨てさせはしない)
カトリネは知っている。
娘リリーベルがまだ生きていることを。
ジョアンに任され、リリーベルの死亡届を提出する手続きの最中に知ったのだ。
リリーベルはまだ生きて、とある貴族の屋敷に勤めているということを。勤め先は秘匿されていたが、職業斡旋所を通じて手紙を渡すことはできる。
(娘はまだ少しは魔力の素養があった。あんな気持ち悪い薬を飲ませるわけには行かない。けれどあの愚かな父親と同じ『才なし』の娘なら……薬を飲ませても、問題ないわ)
カトリネは手紙を書いた。
それは調べた職業斡旋所に、リリーベルに会いたいと伝えるものだった。