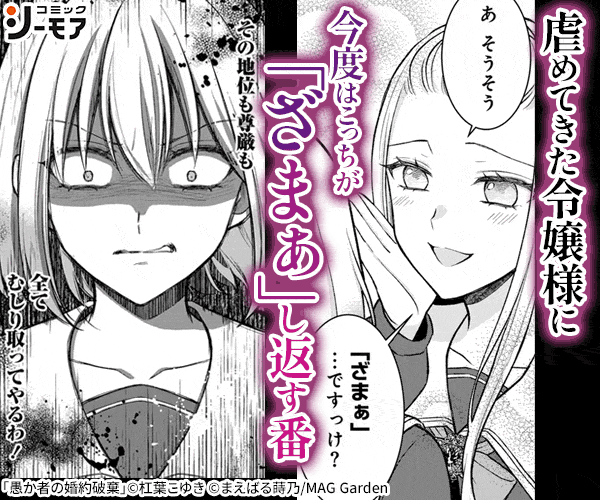36・ギルバートの回想 下
『兄さま! 素敵な人とであったの! ……大丈夫よシュバルツ、兄さまは怖い顔をしているけど、噛みついたりはしないもの』
手を繋いで、すっかりレイラは気に入っている様子だった。犬でも拾ってきたようなノリだ。
待て。俺もか、犬扱いされてるのは。
そんなふうに思っていると、その捨てられた犬のような小汚い少年はこちらに頭を下げた。
『シュヴァルツです。初めまして、アンドヴァリ公爵令息』
『お兄様って呼んでいいのよ』
『……』
レイラの言葉に何とも言えず、困った顔で口をつぐむ少年。
そりゃそうだろう、いきなり王族に匹敵する家柄の嫡男に会わせられたら困る。
一般常識は多少ありそうなこの少年に、シュヴァルツは多少の同情と共感をする。困るよな、レイラ。
連れてこられたシュヴァルツという少年は、ザヴェルト公爵に捨てられたメイドの生んだ子で、貧民街で長く暮らしてきたという経歴だった。
『ねえ兄さま、シュヴァルツはすごい才能があるの。どうかシュヴァルツが魔術師になれるように応援したいの。力をかして』
確かに話を聞く限り、放っておいては危険因子になりかねない才能を秘めていると感じた。
だがそれはそれ、これはこれだ。ギルバートは頭の中で愚妹に説教する。
(だしぬけに何を言うか愚妹。貴族の血を引いている上に魔力の才能があるのなら、まあ養子の宛てはあるとはいえ、いきなりそんな貧民街育ちの野犬のような年下の男と親しくするな。お前にとってはガキだろうが、そいつはあっという間に成長する。恩義を感じたそいつと愛着が湧いたお前、当然間違いが起こりかねんだろうが。というかすでに間違いの萌芽があるような気がするぞ。ならんならん、お前はアンドヴァリ公爵家の女だ、魔術の強い、家柄のある男しか許さない。面倒な家が絡む貴族もだめだ。アンドヴァリ公爵家の地盤を強固にし、なおかつ、お前という愚妹を理解し丁重に扱う男でなければ。ついでにお前の美しさを引き立てるように、ある程度以上に容姿も整った――)
はたと気づく。
こいつしかいないのでは、レイラの夫として都合の良い魔術師は。
実際、レイラに手を繋がれてアンドヴァリ公爵家に足を踏み入れて平然と立っているのだから、このガキの根性は割と据わっているらしい。
『……悪くないな。良いぞ』
『本当!? ありがとう!』
喜ぶレイラの横でシュヴァルツはまっすぐこちらを見ていた。
『良いのですか、公爵令息。僕は育ちも悪く、父親も貴族ではありますが破滅しています。アンドヴァリ公爵家の家名に傷が付きます』
『危険な実力者を手中に収めるのは公爵家の領分だ。せいぜいいい手駒に育て。手間をかけてやる代わりにな』
シュヴァルツは言葉の意味の重さを理解したらしく、まっすぐギルバートを見返した。
その瞳には覚悟が滲んでいる。
『よかったわねシュヴァルツ。兄サマは認めない人には話かけすらしないの。気に入られたのよ』
うるさい。翻訳するなこの愚妹。
そうしてギルバートは親に話を通し、シュヴァルツの保護を行った。
レイラに甘い両親もレイラが幸せになれそうな相手なら早く目をつけておくに限ると、あれこれと手筈を整えてくれた。
新しい家柄と居場所、そして学歴を得たシュヴァルツは、レイラと共に魔物討伐の最前線で戦える頼もしい魔術師になった。
義弟としても理想的だった。
職務にあたらせれば誠実で、功績から魔術伯の爵位を得ても、見目麗しく人気が出ても、一切浮つくこともなく、レイラとアンドヴァリ公爵家を大切にした。
ギルバートにとっても、面白い弟ができた気分だった。
己の体が不自由なぶん、勢いよく動き回り、外野を実力と拳で圧倒するシュヴァルツは小気味いい存在だった。
レイラの相手をできる家族ができて嬉しかったのもある。
大暴れ怪物のようなレイラも、自然とシュヴァルツと一緒に居ると可愛い顔を見せる時が増えた。妹気質だからか年下のシュヴァルツにも素直に甘え、時に年上ぶって楽しそうにし、とにかく仲が良さそうだった。魔術師としての相棒としても配偶者としても、理想的なように思えた。
妹が幸せそうにしているのが嬉しい自分を、認めたくなかったが。
――幸せの絶頂だったレイラ。
――魔物騒乱を終わらせて、幸福な花嫁になって、新しい人生が始まる直前で。
――それでも、レイラは死を選んだ。
自分の幸福より世界を選んだレイラの考えを、ギルバートはすんなり理解できた。
(あれは、最期までアンドヴァリ公爵家の魔術師であることを選んだ)
天衣無縫に見える愚妹は、『大自在の魔女』の能力者で、国を守る宮廷魔術師だった。
アンドヴァリ公爵家の人間として、自分の幸せよりも人々の幸せを優先する。
気持ちは理解できる。
おそらく、この世で一番レイラに共感できるのは自分だ。
だからこそ疑ったのだ。
あの規格外の愚妹は、何らかの方法で生まれ変わって、元気に愛するシュヴァルツに再会しにいきはしないか、と。アンドヴァリ公爵家の責任をすっきりさせた上で、一介のメイドとして。
◇◇◇
(まあ、違ったがな)
うるさいアンナアンナを引き取りながら魔術杖に乗り、帰路につく。
ギルバートは夕暮れの空を仰いだ。レイラの瞳を思わせる、燃えるような色をしていた。
10年経っても、あのうるさかった妹がこの世にいないのが信じがたい。文字通り消えるように去ったからか。
(……お前なら、戻ってきてもおかしくないと思っていたんだがな、レイラ)
レイラが居なくなってから、急に世界が無音になったように感じていた。
常に喋り続けているうるさいアンナアンナと結婚したのも、さっさと子供を三人ももうけたのも、あの愚妹の欠落を埋めるためかもしれない。認めたくないが、寂しかったのだ。
(お前がいない世界に一生慣れることはないだろうな。シュヴァルツも、俺も。……だが、想いながら生きていくことはできる)
今日は10年ぶりにシュヴァルツの笑い声を聞いた。
シュヴァルツはユーグカと幸せそうに過ごしていた。
(最初、シュヴァルツにユーグカを見せられた時は頭でもおかしくなったかと思ったさ。だがユーグカのおかげで、あいつは過労死寸前まで自分を虐める自傷行為をやめられた。そして……やっと、前に進めるようになった)
あのメイドが来てくれて、新しい風を運んでくれたお陰だ。
レイラの死で停滞した10年が、ユーグカと、リリーベルのお陰で進み始めている。
あれがただのメイドかどうかは、ゆっくり知っていけばいい。今は義弟と姪が幸せならそれでいいのだ。
「ねえギルバートったら、話聞いてるの?」
「聞いてるさ」
「あら? 少しご機嫌ね、あなた?」
(そう言われる謂れはない)
黙っていると、腰に回った腕に力が入る。
アンナアンナの豊かな胸がぎゅっと押し当てられて柔らかだった。
「きっとシュヴァルツくんが笑っていたからご機嫌なのね、あなた。だってシュヴァルツくんが悲しそうにしていたら、レイラさんもきっと悲しいと思うから。……レイラさんの代わりに、あなたってば、シュヴァルツくんのことを気にかけてあげなくちゃって、いつも想っているものね」
(そんなことはない)
思ったが、わざわざ言葉に出して否定するつもりもなかった。
「あなたが上機嫌なら、私とっても嬉しいわ。思い切って飛び出していってよかった」
「それは反省しろ」
「うふふ、そうね」
アンナアンナの熱を背中に感じながら、ギルバートは杖の速度をあげ、夕陽に染まる王都へと帰っていった。