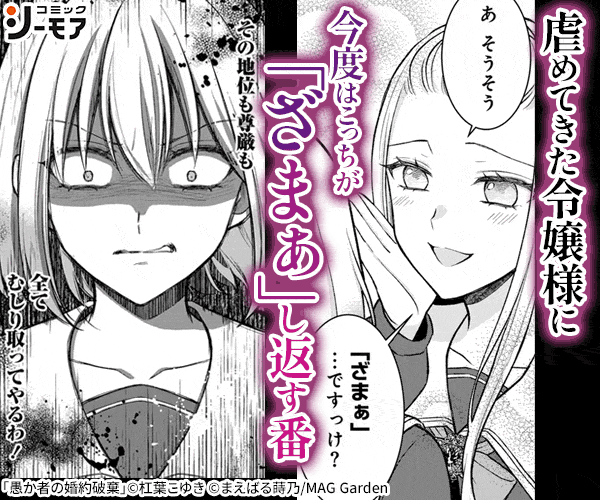33・レイラじゃないです、リリーベルです
「……え?」
シュヴァルツの間の抜けた声が響く。
杖はあさっての方向に飛んで行った。
「……」
真顔で杖を見送るギルバート。
杖は生き物のように空間を自由にひらひらくねくね動き回っている。
当然『大自在の魔女』の力は人の持ち物にも有効だ。対策を取られると厳しいけれど。
今日のギルバートはそこまで対策していないと読んだのだ。
私はにっこりと笑った。
「えへへ。危ないので飛ばしちゃいました、公爵の杖。どうでしょう!」
「私が杖なしに魔術が使えないとでも思ったのか?」
手をこちらに向けてくるギルバート。
私は大げさに驚いて見せた。
「ええええ……!! つ、杖が無くても魔術が出せるんですか!? えっどうしよう、どうしましょう旦那様……!」
再びぽかんとするシュヴァルツ。真顔のギルバート。
「申し訳ありません、武器を持った人とはこうやって戦えばいいんだって思ってましたけど、投げるものもないし、どうやって戦えば……ええーと……そうだ!」
私はエプロンを脱ぎ、エプロンを空に広げる。ぶんぶんとエプロンが飛ぶ。
「エプロンで捕まえちゃいます! ……ああでも燃やさないでくださいね! 燃えたら悲しいので!」
「…………もういい、杖を返せ」
気が抜けた様子でギルバートは溜息をつき、モノクルをぐっと押し上げた。
「リリーベル・シブレット」
「はい」
「ここは魔力が満ちている。念じれば物を具現化できるし、お前が戦う為の道具は何でも出せるぞ」
「えっ!? そうなんですか?」
「……念じてみろ」
「はい!」
(知ってたけどね)
呆れた様子のギルバートに促され、私はポンとぬいぐるみを出す。
「すごい! えっ、食べ物は出せますか?」
無言を了解と判断し(知ってるけど)、私は次々に食べ物を出す。
まずはテーブルセット。
レモンケーキ、ビスケット、ババロア、ティーセット、プチケーキの盛り合わせ。
紅茶のガラスポットにティーセット、ワゴンに載せたのはお冷やとアイスクリーム。
「……待て」
泉のようなチョコフォンデュタワーを出したところで、さすがのギルバートも止めに入った。
「ふざけているのか? 私と戦う気はないのか」
「え、ええと……戦い方、実は知らないんです。『大自在の魔女』の力は独学なので、レイラ様の遺品の書物を読みながらアレンジを加えてますが……なので、メイドとしての能力をお見せするのが私の戦い方かなって!」
「…………」
ギルバートが無言で固まっている。
そしてモノクルを直し、目をこらしてじーっと私を見た。
「お前は本当にレイラではないな?」
私はちょっと困惑した顔を作って、改めてお辞儀をした。
「はい。リリーベル・シブレットと申します」
沈黙をやぶって、シュヴァルツが魔術障壁のなかで笑い始めた。
「……ふふ、そうだな……確かに、君はレイラではない」
「もしかして私、アンドヴァリ公爵にレイラ様だと思われていたんでしょうか……?」
沈黙が肯定だった。
「ははははは」
「笑いすぎだぞシュヴァルツ」
笑うシュヴァルツをひとにらみして、ギルバートは腕組みして私を見下ろす。
「出したティーセットや菓子の選定は、何か意味があるのか」
「はい。連続で魔術を使われていたのでお疲れかなと思ったので、レイラ様の遺品のレシピ集に書いてあったものを再現してました」
レイラの遺品レシピ集に書いた覚えはあるので、後で調べられても嘘にはならない。
――『兄さまを怒らせた時用レシピ! 兄さまはハニーベル産の紅茶と蜂蜜が大好きだから、まずは匂いでご機嫌を取ろう!』など書いていたことは内緒だけど、絶対。
「せっかくだ、いただきながら話をしよう」
しかめっ面だが匂いに誘惑されてくれたらしい。
そうして私たちは魔術空間でお茶をすることになった。
ギルバートは元々シュヴァルツにあらかたの話を聞いていたらしい。
甘ったるいティータイムをしながら、私は改めて事実確認をされた。
「お前がレイラならば、アンナアンナが再婚だ再婚だと迫ることで動じるかと思ったが」
「公爵夫人を好きになさっていたのは、わざとでしたか」
「当然だ」
(だと思ったわ~!)
と私は心の中で苦笑いする。
兄が人に出し抜かれるなんてありえない。ギルバートは常に支配者だ。
でも同時に、兄はだだをこねる奥さんを好きにさせてあげたかったのもあるんだと思う。
(さっき微妙に表情緩んでたものね~)
わがままを言われると弱い。意外と兄はそういう人なのだ。
おてんばなレイラにもなんだかんだ甘かったし。
「ともあれ、『大自在の魔女』をこのままにはしておけない。シブレット男爵家はリリーベル・シブレットの死亡届を出していたしな」
「っ……なんですっって!」
シュヴァルツが驚きで言葉を失う。
ギルバートは淡々と続ける。
「どうやら追放後すぐに出したようだな」
「父ならやりそうですね……」
「魔術師家系ならば『才なし』が生まれるのを恥とする家も多い。死亡届を出していてもおかしくない。幼い頃のシュヴァルツと逆だ。才能があれば捨てた女の生んだ子供を浚い、才能が無ければ捨てる」
「……」
辛い顔をするシュヴァルツに、私はレイラとして手を撫でてあげたかった。
けれどリリーベルなので、私はぎゅっとスカートを握るだけにする。
ギルバートは言った。
「ともあれ幸か不幸か、現時点でお前とシブレット男爵家の縁は切れている。よって養子縁組手続きをするならば、アンドヴァリ公爵家は力を貸そう」
「ありがとうございます」
「……問題は、貴様がどこと養子縁組をしたいかだ、リリーベル」
ギルバートは私から目を逸らさぬまま、指を2本立てて示した。
「二つの案がある。一つ――完全に実家との縁を切り、シブレット男爵家には何も知らせず孤児として任意の家との養子縁組手続きに入る案。縁組先はアンドヴァリ公爵家の縁戚になる。シュヴァルツの養女になるのでも構わないが、養女になってメイドとして働くのもやりにくいだろうから選択肢から外す」
妻から娘になるのは落ち着かない。私もシュヴァルツの養女になるのは遠慮したいところだ。