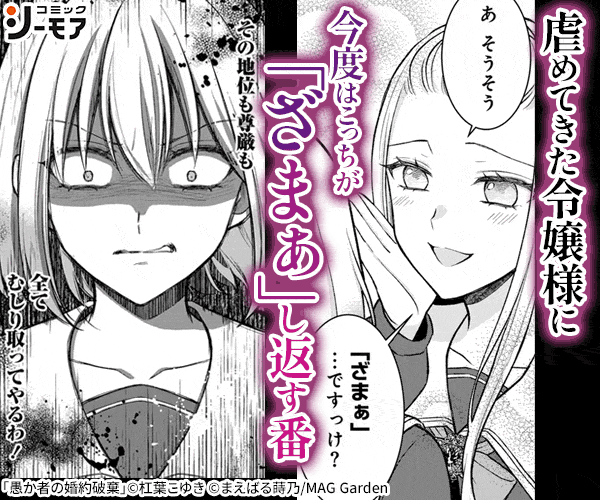26・シュヴァルツの再婚事情と、父娘にとっての必要な時間
チーズケーキと一緒に研究所に向かうと休憩室に案内され、しばらくしてシュヴァルツが出てきた。
「ぱぱ! けーき! たべて!」
「ありがとう。眠くなり始めていたから、差し入れは助かるよ」
父にチーズケーキを差し入れできて満足したのだろう、おさんぽ疲れでユーグカはチーズケーキを食べるシュヴァルツにくっついてすやすやと寝てしまった。
セージが頬をつつく。
「寝顔は全然レイラ様と似てねえよなあ。眉毛と目の感じがすっごいシュヴァルツだ」
「ちょっと! 部隊長とユーグカ様に失礼ですわよ、お兄様!」
ぷんすかとするミントローズだったが、他の研究者に呼ばれて慌てて休憩室を後にした。
イスカリエさんがテーブルに釣書の山を載せると、セージが露骨に顔をしかめた。
「あの、ここ職場だから一応プライベートのやつは」
「そしてこちらが言付かっております、セージ様宛ての釣書です」
どすん。
二つの塔のように積み上げられた釣書に、セージは黙り込んだ。
ケーキと膝のユーグカから魔力補給して、少し眠気が取れたシュヴァルツが溜息をつく。
「義姉様は、諦めていらっしゃらないのだな……」
「あの」
私は片手を上げる。
「私、アンドヴァリ公爵夫人について存じ上げないのですが……どのような方なのですか? 公爵については(前世の実兄なので)存じ上げているのですが……」
兄、ギルバート・アンドヴァリは数年前に公爵の位を引き継いでいた。
宮廷魔術局の局長も務める、身分も実力も肩書きも王家に匹敵する力を持つ男だ。
一言で言えば、厳格が服を着て歩いたような兄だった。
その兄の結婚相手の情報は、実はまだ掴めていなかった。
私の質問に、シュヴァルツとセージは顔を見合わせる。
そして同時に言った。
「仲人が人生の生きがいな女性だ」
「いわゆるお見合いお世話大好きおねーさまだよ」
「な、なるほど……」
「悪い人ではないのだ。むしろ公爵夫人としてはこれ以上無い有能な方で、貴婦人達の社交界をとりまとめる手腕は王家すら凌駕する。私がレイラの死後もアンドヴァリ公爵家の親族として扱われるのも、彼女の力なしにはなしえない」
「ギルバート・アンドヴァリ公爵がとにかく堅物眼鏡で氷山のような男だとすると、公爵夫人は太陽のようなお方だよ。なんつーか、明るく温かく、どこに居ても目立って華やかで、そして熱で全部を溶かして、一つにまとめたがる」
「貴族子女の噂を網羅し、彼女に聞いて分からないことはないと言われる。ユーグカの友人としておすすめの令嬢たちのリストも毎月送られてくる」
「わ、わお……」
「とにかく『社交』がドレスを纏っておしかけてくるような、そんな人だよ」
話は分かった。
立場も能力も押しの強さも、とにかく凄い人なのだ。
二人が釣書を見てもいいと言うので、私もいくつか見てみる。
「それ、写真の裏に詳細情報が挟まってる。見るとぞっとするぞ」
「わ、わあ……」
びっしりと細かな達筆で、その令嬢の詳細情報が描かれている。交友関係から、妻に迎えた場合のメリット、デメリット、社会的影響といったものから、普段の服装やプレゼントの趣味まで。褒め言葉ばかりで嫌な言葉は書いていないが、とにかく文字数が圧巻だ。
石をひっくり返したら虫がうじゃっとでてきたような、そんな寒気を覚えた。
「お城にいらっしゃることもあるでしょうし、私も気を引き締めてお迎えしますね」
「まあ、少なくともしばらくは大丈夫だよ、まだ来るとは書いてないし」
「そうそう。まだ末娘のレヴェッカが赤ん坊だから、しばらくは動かないだろうしな。あの人は乳母に丸投げせず、自分でも見たがるような人だから」
そうか、と安心しつつ私は不安になっていた。
――兄ギルバート・アンドヴァリはとてもくせ者だった。
あの人の妻なのだから、当然、一筋縄ではいかないだろう。
◇◇◇
翌朝。
キッチンで朝食の準備をしていると、シュヴァルツはいつもより早く目を覚ましてきた。
シャツにトラウザーズの、簡単に身支度をすませただけの姿だ。
「おはようございます、すぐにご用意しますね」
「いや、いつも通りの時間でいい。コーヒーを淹れてもいいか?」
「私が淹れますよ」
「いや、自分で淹れたいんだ」
シュヴァルツはそう言うと窓辺の作業台で、手際よくコーヒーを淹れはじめた。
緑色の生豆を手のひらで包んで上下にシェイクしながら炎魔法をかけ、均等に熱を通して焙煎する。浅煎りにした豆を確認したのち、ドリッパーにフィルターをかけ、手のひらで包んで風魔法。豆を挽いてとんとんと均し、最後に水魔法と炎魔法をアレンジして、手のひらをかざして熱湯を注ぐ。香り立つコーヒーは、何工程にも渡ってシュヴァルツの魔術をかけられ、コーヒーポットの中で琥珀色にキラキラと淡く輝いている。
朝日に照らされた、一連の作業をするシュヴァルツ。
その姿はかつてのシュヴァルツと重なった。あの頃も、コーヒーを淹れるのが得意だった。
あの頃は少年の気配が強かったシュヴァルツがすっかり大人の男性だ。
その隣で、レイラが生きていたらどんな風に立っていただろうと考える。
「……綺麗ですね……」
「朝からこの作業をすると目が覚めるんだ。君も飲めるなら、飲むかい?」
「では少し。お言葉に甘えて」
私たちはキッチンの片隅、スツールを並べてコーヒーを口にした。
9歳の体にはちょっと刺激が強い味だけど、少しだけ、思い出に浸りながらゆっくり味わう。
「旦那様は再婚する気はないんです……よね?」
「君も私に見合いを勧めたいのか?」
「い、いえ違います! ただ、その、10年って長いなあ、と思ったので……旦那様はまだ20代ですし、かっこいいですし、何でもできますし、お見合いを勧める人がいらっしゃるのもわかるなって」
気を悪くさせたかと慌てたが、シュヴァルツは小さく肩をすくめただけだった。
「これまで心配をかけてきたせいで、まだ私は、ユーグカとしっかり父娘として関係を作れていない。あの子が遠慮無く私に甘えてくれて、わがままも言えるようになることが、今の一番の目標かな」
「……そうなんですね」