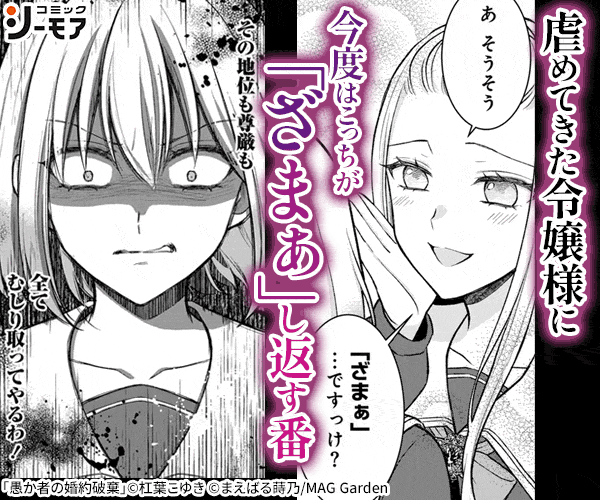24・ その頃の実家/カトリネ・シブレット男爵夫人視点
パン!
乾いた音が部屋に響く。カトリネ・シブレットの娘エリファは頬を抑え、涙を堪えている。
「最近どうしてしまったの、集中力が足りないわよ」
「ごめんなさい……」
エリファがしょんぼりする姿を見て、カトリネは罪悪感を覚える。
抵抗もできない娘を叩いてどうなるというのだろう。
けれど娘の魔力が突然弱くなったのは、本人が原因としか考えられなかった。
「もう一度。……いいわね?」
「はい……」
エリファは力なく、机の上の水晶玉に手をかざす。
正式な魔力検査で使われる正規品と同じものだ。魔術師を輩出する貴族家は大抵私物として持っている。
エリファはぎゅっと目を閉じ、一生懸命水晶玉に念じる。
けれど全く何の変化も出ない。
「どうして……」
カトリネは泣き喚きたくなった。エリファも一生懸命やっている。
かわいそうだ。
確か数ヶ月前までは、微かながらも魔力の気配が感じられたのに。
泣き出したエリファをハグしながら、カトリネも泣きたい気分になった。
「……あれの呪いなのかしら」
カトリネは窓の外、庭を見つめた。
庭の木々の向こう、こちらからは見えない場所に、誰も手入れをせずみすぼらしい墓がある。
そこには前妻の墓がある。あの『悪霊憑き』を生んで死んでしまった、不幸な女の墓だ。
夫ジョアン・シブレットは遺骨や遺品を実家に戻してやっていない。『悪霊憑き』で『才なし』のリリーベルだけを産んで死んだ彼女は婚姻契約の違反だと言いがかりをつけ、前妻の実家に慰謝料を請求しているらしい。
呆れた男だ。
不幸な人間と愚かな男しかいない、この家はやはり呪われていると思う。
カトリネは何度も聖職者にお祓いをさせたけれど、まだ効果がない。
効果的なパワーストーンやお焚き上げ、胡散臭い辻占いにも頼んだけれど、エリファは相変わらず魔力の調子が悪い。
「おかあさま……っわたしも……あのひとみたいに、おいだされるの……?」
「追い出されたくないなら頑張りなさい。あなたはあの子とは違う。できていたのだから。父親も私も、しっかり魔術が使えるのだから、あなたも使えるはずよ」
言いながらカトリネはあの子ーー前妻の娘、リリーベルを思い出す。
思えば不気味な子どもだった。
幼いころは泣き喚いたり、悲しそうにしたり、ただの哀れな子どもでしかなかった。
夫が暴力を奮って罵倒している姿は見ていて気分がいいものではなかったが、前妻の子どもが寵愛されるよりはましだと、虐待からは目を逸らしていた。
あまりにひどい時は夫に孤児院に捨てるように提案だってしていたので、自分は悪くないとカトリネは思う。
しかしあの娘は、5歳の時はっきりと雰囲気が変わった。
あの娘は急に、恐ろしいほどにおとなしくなったのだ。
夫は「悪霊も賞味期限が過ぎたのだろう」と笑っていたけれど、カトリネは不気味だと思っていた。
リリーベルは自由だった。
腫れ物扱いなのをいいことに、彼女は他の使用人と親しくしたり、商人と話したりすることも多かった。
こっそり家を抜け出して、何かしているのも実は知っていた。けれど『悪霊憑き』がこちらに感染しても嫌なので、やはり無視していたのだ。
だから不気味な子どもが家から消えて、ほっとした。
夫がリリーベル・シブレットの死亡報告を提出していたのもよかった。二度と戻ってきてほしくなかった。
けれど。
あの子が消えてからエリファの魔力に変化が起きてしまったのだ。
それだけではない。カトリネもなんだか、魔法がかかりにくくなったように思う。
内職でやっている魔道具作りも、なぜか以前より疲れやすくなった。やはり、呪いだ。
「奥様、魔道具商人が来ましたが……」
カトリネはため息まじりに立ち上がった。夫が内職で命じている仕事だ。
非合法の魔道具商人なのだろう、どこか気味が悪い男で、カトリネは話をするのが億劫だった。早く用事を済ませよう。
「私は商人に会ってくるわ。あなたは練習を続けなさい」
「はい……おかあさま……」
しゃっくりをあげて泣くエリファを残して部屋を出る。ふと、テーブルに置かれた広告が目にとまった。貴婦人向けの絵本通販の広告手紙を開いたままにしていたのだ。
そこには鮮やかな新刊、レイラ・アンドヴァリ公爵令嬢の子ども向け自伝が紹介されていた。
銀髪を靡かせ、明るい笑顔で人々に平和をもたらした『大自在の魔女』。
「この人みたいな能力がうちの子にもあったら、どれだけ良かったか」
はあ、と深いため息をつく。
カトリネ・オストマヌ・シブレットは、人生のやるせなさを噛み締めていた。