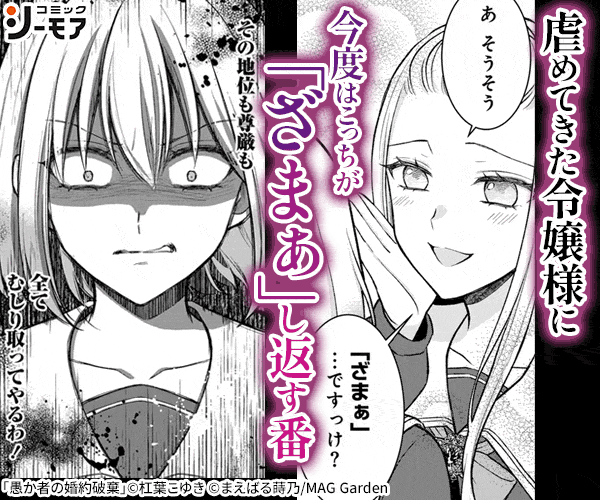23・セージとシュヴァルツ、出会いと人生 下
「え?」
「え? じゃねえよ、こりゃ最低限の治癒は必要だな、俺がやってやっから、お前はけが人を並べろ!」
「いいんじゃないのか? これくらい」
「取り返しがつく程度に回復してやらねえと、証文取ってても覆されるぞ、馬鹿」
いくら証文があるとはいえ、子供が想像以上にぼこぼこにされては手のひらを返しかねない。
「レイラ様の実家にもみ消して貰うのは嫌だろ?」
「そうか、そうだね。ありがとう」
ようやく理解したという様子で、シュヴァルツは決まり悪そうな苦笑いを浮かべた。
(あ、こいつ人間だ)
不気味なのではない。――視野が狭くて、直情で、能力がものすごく高いだけの、普通のガキだ。
セージは初めてこのとき、この不気味な同級生が理解できた気がしたのだ。
その後は二人で治癒魔術を遣い、令息たちを適度に直してやった。
治癒魔術の腕前さえも卓越している、その事実が余計怖かったのだろう、彼らはおとなしく去って行った。
結果的に。シュヴァルツに嫌がらせをしていた連中は、親の許可の下シュヴァルツにぼこぼこにされ、そのみっともない状態で華やかな社交シーズンに赴くことになってしまった。
その上、シュヴァルツは学外活動と称して、レイラと共にあちこちの社交の場に遠出をしては、地元の有力魔物を狩りまくった。
『魔力検査で実際に魔物と戦った』なんて、みんな信じてなかったが、本当だったらしい。
こうして子から親の世代まで、シュヴァルツを見下すことはできなくなった。
セージはなぜかシュヴァルツと仲良くなった。
彼に叱ったりつっこんだりできるのはセージだけになったからだ。
シュヴァルツの友人という縁で、セージもレイラと親しくなった。
レイラは白百合の精霊のような美しさで、抜き身の剣のように強い女性だった。
「彼はセージ・パルスレー。治癒魔術の天才で、僕の友達だ」
「っ……と、友達って」
「違うのか?」
そういう恥ずかしい言葉をはっきり口にするタイプだとは思わなかった。
セージが気まずく思っていると、レイラはセージに笑顔で挨拶する。
「パルスレー辺境伯領は良質な薬草の産地で有名ね」
「えっ、ご存じなのですか?」
「当然じゃない。宮廷魔術局に届けられているもの。魔術師の根幹を支えるポーションの原料を、いつもありがとう。何か困ったことはない? あなたのお話も色々聞きたいわ」
お高くとまった令嬢かと思いきや、彼女はセージのような貧乏辺境伯領の役割まで当然のように把握していたのだ。そんな彼女を、シュヴァルツはうっとりと見つめている。
ああ、こういう人だから好きになったのだなとセージは理解した。
三人で過ごす時間は楽しかった。
レイラはいつもシュヴァルツに、花の盛りのような華やかな笑顔を向けていた。
その眼差しは、愛情が全身から溢れるような、見ていて気持ちいいほどの溺愛だった。
そしてレイラを前にしたシュヴァルツは、とても満たされた優しい目をしていた。
学園で見せる、あのどこか不気味で浮世離れしたシュヴァルツとは別人のようだった。
それがなんだか妬けるようで、彼女がいるのがうらやましいようで。
この二人は絶対に幸せになるのだと、セージは信じ切っていた。
――信じていたのに。
◇◇◇
「お前、笑うようになったよな」
こんなに顔色がよく、穏やかに笑む姿は、レイラ没後初めてだった。
長い年月、シュヴァルツの心は凍てついていたのだ。
治癒魔術師からシュヴァルツの部下に転属してまで湖の研究所に住み込んでいるのは、シュヴァルツが後追いしないか見張るつもりでもあったのだ。
シュヴァルツは少し考えた末、薄く微笑んで返事をする。
「そうだな。……心配かけたな」
「別に。長い付き合いだから心配くらいさせろ」
「良い友人を持ったな、私は。そうだな……友人、か……」
シュヴァルツがぽつりと呟く。
「ユーグカも能力の制御ができるようになってきた。友達くらいそろそろ作らせてやりたいが……」
「だな。令嬢は早めに女社会になれた方がいい」
「あてがないわけでは……ないのだがな」
「ああ……俺も言いたいことは分かる。アンドヴァリ公爵夫人か」
シュヴァルツは頷く。
「また手紙が届き始めた。姿絵付きの分厚いのがちらほらと」
「……ああ……」
「お前の分も届いてるぞ」
「やめろ、やめろやめろ、あああ、あのお見合い大好き夫人はほんと……」
そこで、沈黙していたイスカリエが何か言いたそうな顔をする。
察したシュヴァルツが発言を許可すると、イスカリエは一礼して言った。
「手筈通り、リリーベルさんのご実家の調査は進めております。ただ遠方の男爵家の情報なので、かなり限られておりまして」
「……何をいいたいのか分かったぞ」
「それでは言葉にいたします。アンドヴァリ公爵夫人のネットワークを借りれば、シブレット男爵家のかなり詳細な情報を調べることはできるのではないでしょうか」
「たしかに……」
「あの人なら、貴族夫人、令嬢のコミュニティは全て網羅しているとも言えるが……」
沈黙が降りる。
「話したくないな……」
「ああ……」
子供のようにシンプルに抵抗感を口にするシュヴァルツとセージ両名。
「絶対、いち情報ごとに一見合いを入れられる」
「成婚に応じて詳細情報を伝えると言いかねないな、あの人は」
「心中お察しいたします」
イスカリエが頷く。
「実は私も、あの方に会うたびに後妻を迎えないかと言われまして」
「「イスカリエでさえ!?」」
男やもめ二名、独身一名。
お見合い大好き夫人に対して、どうするべきか悩ましい溜息を同時に吐いた。