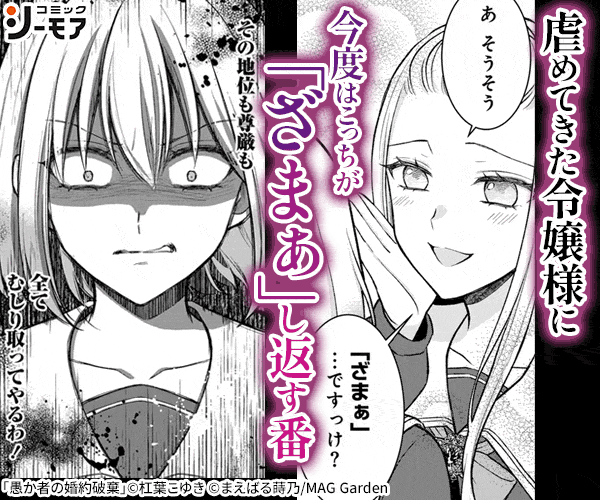22・セージとシュヴァルツ、出会いと人生 上
静かな喫茶室で大人二人、ガラスポットで薬草茶が抽出されていくのを見つめる。
研究所にシュヴァルツが来るのは久しぶりだった。魔力以外は、ほとんど全快に近いようだ。
「妹の件、うまくまとめてくれてありがとな」
「私は何もしていないさ。あれはリリーベルの働きだし、ミントローズの自覚あってのことだ」
「あいつ、視野が狭くなってたからな……」
ふわふわと踊る茶葉を眺めながら妹を思う。
妹は視野が狭くなっていた。早く大人になりたいと焦りすぎていた。
自分が幼かったせいで両親を守れなかったと、今も心の傷になっている部分がある。
だからこそ強さで全てを薙ぎ払ったレイラ・アンドヴァリに恋焦がれ、彼女を盲信するのだ。
「ぶっちゃけ同級生をバカにしてたからな、あいつ。焦れば焦るだけ早く大人になれると思い込んでいた。
今回のことで、妹も少し落ち着けたから嬉しい」
「いい友達になれるといいな、リリーベルと」
「俺たちみたいに?」
セージの言葉に、シュヴァルツは言葉を返さない。
けれど穏やかな気配が、彼の返事そのものだった。
家令のイスカリエが茶を注ぐ。
――かつて、シュヴァルツは妾の子として学園で孤立していた。
10年以上前は、まだ学園に貴族以外がほとんどいなかった時代だ。
学園に招き入れたのはレイラだが、公爵令嬢のスカートの陰に隠れてると揶揄する連中に虐められていた。
最初にセージが接したのは、ただの興味本位だった。
「最初は大変だったよな。ほら、あいつとあいつに成績が不正だとか枕だとか因縁つけられたり」
「懐かしいな。終わった話だ」
「相手にとっちゃ終わった話じゃないけどな? なにせ、きっちり仕返しされるとは思ってなかったようだからな」
シュヴァルツは薄く微笑む。
◇◇◇
――学園入学当初、シュヴァルツは孤立していた。
レイラや出自にまつわる嫌がらせを一切気にしないのが、ヒエラルキーに敏感な貴族令息どもの余計鼻についたのだ。
セージ・パルスレーは辺境伯領家の嫡男として同期だった。
魔物があちこちで暴れ回る時代において、魔物危険区域の辺境伯は貧乏で、ヒエラルキーは下層。
だから当初はガキ共の関心を矢面に立って受け止めてくれる、シュヴァルツの存在に感謝すらしていた。しかし流石に一ヶ月以上になり、嫌がらせが「いじめ」に発展しそうになると、知らず存ぜずでいるのが怖くなってきた。
ある日その件について彼に話しかけると、彼はセージを見て軽く目を見開き、そして薄く微笑んだのだ。
「ありがとう。でも僕に構っていたら、君も面倒に巻き込まれるよ」
物腰こそ柔らかいものの、青い瞳は何を考えているかわからない。
不気味な奴。それが、セージ・パルスレーにとってのシュヴァルツの第一印象だった。
四月入学から数ヶ月後、貴族令息令嬢たちの入学後、最初の社交連休期間が訪れた。
その連休直前の放課後、事件は起きた。
シュヴァルツはクラスのボス的存在の貴族令息の机に片足を乗せ、軽い調子で言ったのだ。
「なあ君。ちまちまと僕に絡むのもつまらないだろう、せっかくなら練習場で一発で終わらせないか」
教室の真ん中でいきなり言ったものだから、そいつも当然喧嘩を買う。
令息だけでなく令嬢まで、生意気な最下層が処刑されるのを眺めに、みんなぞろぞろと練習場に集まる。明らかにリンチの気配がして、恐ろしくてセージも彼らとともに練習場まで向かった。
令息は当然見下した調子で、シュヴァルツを煽る。
「悪いけれど君は俺の相手にはならんからな。学業に支障が出て辞める羽目になっても、当然お前の責任だからな」
「怖がらなくてもいいよ。ちゃんと許可は取ってきた」
シュヴァルツの言葉に観衆は笑った。
これまでの実技でもシュヴァルツはよくも悪くも普通の成績だった。
能力は高くとも「学園で求められる魔術行使」になれていない様子だったのだ。
令息は笑いを堪えながら言う。
「こんな時まで、女のご機嫌伺いを気にするのか、まるで妾だな?」
「別にレイラのご機嫌伺いはしていないよ。レイラは僕を信じてるから」
皆が知る絶世の美女レイラ・アンドヴァリを呼び捨てにするのも、思えば煽りの一つだった。
「……妾野郎が、」
うっとりと微笑むその笑顔に、令息は舌打ちする。
そしてシュヴァルツに襲いかかった。
数秒――あっという間の勝負だった。
シュヴァルツは軽やかに彼の拳を何度もいなすと、「許可は得たからね」と令息の顔面をしたたかに殴りつけた。回し蹴りが綺麗に脇腹に決まり、土に転がる令息は汚い叫びを上げた。
誰かが叫ぶ。
「わ、分かってるんだろうな!? その方は大臣の息子で」
「分かっているよ。ここにいる令息連中、全員を素手でやるならどこまでもやっていい許可を得てきた。さあ、次はだれ?」
「っ……!」
彼が空中に浮かび上がらせたのは、数々の魔術証文。各貴族家の紋章に署名が浮かび上がった本物だ。
シュヴァルツの落ち着きに、その場に居る全員が震え上がった。
「てめえ、調子に乗りやがって!」
「父上も知っているのなら、お前から逃げる訳にはいかない!」
ぞくりとした本能的な恐れにあらがうように、令息たちは一気にシュヴァルツを囲んだ。
学園入学レベルの剣と魔術を、シュヴァルツは素手で返り討ちにした。
拳で殴って骨を折り、剣を躱して叩き折り、魔術は同士討ちをさせて。
最終的に令嬢たちは身を寄せ合って震え上がり、婚約者が倒れていても心配する者すらいなかった。
「次は?」
「ばか!やり過ぎだ!」
たまらず、セージは声をあげた。