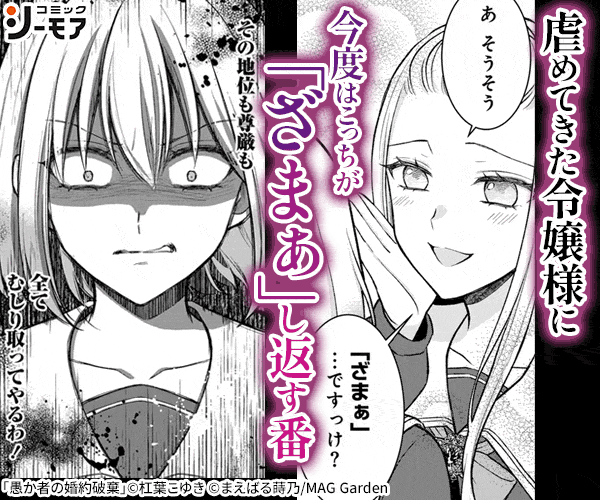2・幽霊古城は様子がおかしい
「本当に15歳? 8歳くらいじゃないの?」
「15歳です(嘘)! 成長が遅くて、身長が伸びなくて~、えへへ」
「……そう? まあ、いいけれど……」
なんだかんだ受理してくれた。貴族の証明付きの書類を作っていて良かったと安堵する。
早速、私は新聞の切り抜きを出した。
「こちらの求人が気になって来たんです」
「……ああ、『幽霊古城』ね」
彼女は私を見た。あまりいい反応ではない。
「幽霊って……あっ、昔レイラ・アンドヴァリ公爵令嬢が亡くなったからですか?」
「やあねえ、10年前までは魔物があちこちで暴れていた国よ? 一人や二人死んだって誰も気にしないわよ。でも待遇はいいけれど皆辞めていくのよ。まあ、こちらも紹介しないわけにもいかないから、あなたが行ってくれるなら助かるけど」
「は、はあ……」
気を取り直して、私は求人票に書かれた文字を指差す。
「お嬢様がいらっしゃるんですよね? もっと情報はありませんか? その、奥様がどんな方だとか」
「さあ? 元の奥様――レイラ様の娘でしょ」
「年齢が合いません。レイラ様は10年前に亡くなっていて、お嬢様はほら」
「4歳ね。……うーん、書類が間違ってるんじゃないの? 奥様がいらっしゃるなら流石に分かるわよ」
私は少なくとも産んでいない。初夜だって手を握っただけなのだから。
謎が謎を呼ぶばかりだ。
「妙に奥さんを気にするわね……あっ、玉の輿を狙うつもりは無いわよね?」
「はわわ! は、はい! もちろんです!」
「そう。ならいいわ。手続きをしてあげる」
「ありがとうございます」
親切な受付女性のおかげで、私は無事に手続き完了。
翌日には早速城に向かうことになった。
◇◇◇
私は馬車と船を乗り継いで、昼過ぎには摩口湖上の古城へと到達した。
古城は湖の中程にあるこんもりとした小島に建てられていて、下層部分をうっそうとした木々が覆っている。
今日は霧が濃く、まるで湖に城が浮かんでいるように見えた。
「懐かしいわね……」
築300年以上の石造りの古城。
シュヴァルツと前世の私が、新婚後の生活拠点として国から与えられた場所だった。
結婚式も初夜も、この城で迎えた。――そして、レイラとしての死も、この城で。
物思いにふけりそうになって、私は我に返る。
「おっといけないわ、早くご挨拶にいかないと」
行きと同じように重たいバッグに足を生やして動かしていると、向こうからどたどたと女性が走ってきた。
すぐに足を消して、手で持ってる振りをする。
きっとお出迎えだ。まずは深呼吸。元気な笑顔の挨拶で、好印象を持って貰おう――
「「新しいメイドね!」」
「はい、初めまして! 私はリリ」
「ああそう! わかったわ!」
「じゃあ、頑張ってね!」」
「……えっ!?」
二人は私とすれ違うと、乗ってきた舟に飛び乗る。
そしてオールをこぎ、大慌てで去って行った。
「え、ええ……」
「先ほどの二人が、この城の最後のメイドでした、残念ながら」
霧の向こう、年老いた男性の声がする。
見れば、50代ほどの白髪の男性が綺麗な足取りで近づいてきた。
「イスカリエさん……」
「おや、名前を知っているのですか?」
「あっ……は、はい! 先に教えていただきましたので!」
私は慌ててごまかす。
彼の事は知っている。昔から家令として勤めてくれていた人だ。
私はぺこっと、使用人らしいお辞儀をした。
「初めまして、リリーベルと申します! よろしくお願いします!」
「随分若いのですね?」
「15歳です!」
「……そうですか。ではこちらへ」
「はい!」
彼は訝しげにしていたが疑うのは業務外だと判断したのだろう、冷淡に告げるとくるりと城に向かう。
早速城に案内される。
玄関ホールから見上げた吹き抜けの天井も真っ暗。空気もかび臭く湿っている。
「足元にお気をつけください」
イスカリエさんが指す先に、倒れた燭台があった。
その横には散らばった手紙、崩れた箱。
あちこちに雑然と荷物が積まれていたり、ぐちゃぐちゃになっていたりする。
――ん? ぐちゃぐちゃ?
主が忙しくて、荷物の仕分け指示が遅れるのはまあ、理解の範疇だ。
でもメイドがいるのなら少なくともぐちゃぐちゃになんてなるのはおかしい。
そもそも寒い。かび臭い。
吹き抜けを見上げれば、ガラス窓は埃で曇り、光すら通さない。
背を向けたままイスカリエさんが言う。
「驚いたでしょう、これがこの城の惨状です」
「はい。メイドさんはもう、どこにもいないんですよね? 他の使用人の方々は?」
その時。
ドカーン!
「うわああああ!!」
向こうの方で音がする。確かキッチンのほうだ。
「また、始まりました」
イスカリエさんはは淡々と言う。
「これが『幽霊古城』、と言われるゆえんですよ」
音がした方角から、粉まみれの料理人が全力疾走で走ってきた。
「家令! 誠に申し訳ありませんが、もうお化け屋敷は無理です!」
「泳いででもここからおいとまさせていただきます!」
「「ではっ!」」
料理人が駆け抜けた廊下が、べったりと粉まみれになっている。
汚い城の中が、ますます汚れた。ああ、掃除したい。
こほん。イスカリエさんが咳払いする。
「実は私も年ですので、最近はここに来るのは週に一度です。家令としての執務のほとんどは港側の別邸にて務めております」
「あら……」
「つまり幼いあなたには酷でしょうが、もし働くならば、本日からオールワークスメイドです」
「そ、それはいいのですが……」
「何か気になることがあるようですね?」
「今のって『魔力暴走』ですよね?」
「……ほう」
イスカリエさんは感心したように眼鏡をつるを上げた。
「紹介状には『才なし』と書かれているようですが、『魔力暴走』に関する知識がある、と……」
「調べたんです。魔術伯のお屋敷で働きたいと思っていたので。それに」
「それに?」
聞き返され、私は生唾を飲み込む。
実は私は『才なし』じゃなくて――私も同じ能力を持っているんです。『大自在の魔女』と。
今明かすべきだろうか、どうしよう?
まだちょっと早いかな。レイラが死んだ城にレイラと同じ能力者が来るって、ちょっとできすぎだよね……。
そう逡巡しているうちに、廊下の向こうから革靴の音が近づいてきた。
「待たせたな」
少し掠れた低い声が聞こえて、イスカリエさんがお辞儀をする。
やってきたのは、黒装束で黒髪の、陰鬱な面差しの男性だった。
背が高くてまるで、影がゆらゆらと動いてきているよう。
長い前髪の間から覗く、真っ青な瞳。
瞳と同じ色のリボンでくくった長髪が、尻尾のようにゆら、ゆらと揺れている。
見間違えるわけはない。――シュヴァルツ・リヒトフェルト魔術伯だ。
さっと頭を下げると、イスカリエさんが紹介してくれる。
「幼いな。まだ子どもではないのか?」
「15歳と。斡旋所の確認も済んでおります」
「……そうか」
私は呆然と立ち尽くしていた。
ずっと待ち望んでいた、シュヴァルツとの再会なのに感動できない。
だって。