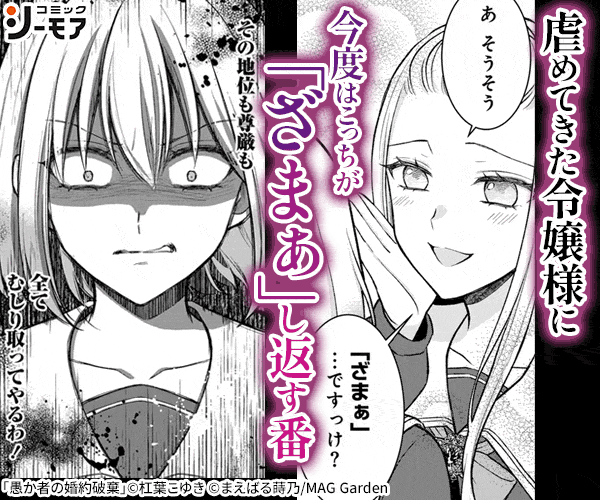11・その頃の実家/シブレット男爵視点
「また使用人が辞めたのか」
妻カトリネ・シブレットの報告に、シブレット男爵は苦虫を噛み潰したような顔をした。
「屋敷の管理はお前の仕事だろう。ここ最近たるんでいるんじゃないのか?」
「申し訳ございません。以前と同じようにやっているつもりなのですが……」
「変えてないからいけないんだろう、知恵を絞れ、知恵を」
頭をトントンと叩いてやると、彼女はもごもごと何か言いたそうにする。
しかし知恵の無い女は言い訳を思いつかなかったのだろう。しおらしくうなだれる。
「で、魔力判定の結果はどうだ? せめてそっちでは成果を出しただろうな?」
「あ、いえ……それが……」
ドンッ!
机を強く叩くと、妻はびくっと身をこわばらせる。
「いいか。魔力判定で結果が出なければ、あれと同じように追い出すぞ」
「そ、それだけは……!」
「そう思うなら知恵を絞れ! すがりついても、自分の役目すら全うできん女は知らん!」
彼女は消沈した様子で部屋を出て行った。
「ったく、あれがオストマヌ侯爵家の血を引くとは思えんな。知恵が足りんよ、知恵が。まったく髪は長いがなんとやらとはよく言ったものだ」
死んだ前妻と同じように、カトリネも宮廷魔術師を輩出する名家、オストマヌ侯爵家から娶った。
兄の学生時代に起こした虐め問題に始まり、そこから政治的失脚が続いて没落した家柄だ。
身分では釣り合わないシブレット男爵家に転がり込んできた、優良な母体だというのに。
遠くで、今部屋を出て行った妻の金切り声と、ぱあんとはじける音がする。
子供を叩いたのだろう。それでいい。甘やかしても魔力は伸びない。
「……金を積んで手に入れたせっかくの母体だ。せめて魔力検査の10歳までに能力を開花するくらいの才能が欲しい」
シブレット男爵家は爵位は低いものの、長年優秀な魔術師を輩出してきた過去がある。
だがここ数世代はぱっとしない。
そろそろ優秀な才能を輩出しなければいけない。それはジョアン・シブレットその人でなければならないのだ。
使用人が減った庭は少し荒れている。
長女を追い出した途端、なぜか使用人達が次々に仕事を辞した。
再雇用先なんざないと吐き捨てて追い出したが、なぜか彼らは事前に準備していたのか、順調に再就職をしているようで歯がゆい。
「リリーベル……あれが全ての元凶だ」
へらへらとした脳天気な才なし馬鹿娘を思う。
あれも、本来は魔力を期待して前妻に生ませた子だった。
前妻本人の才は平凡だったものの、家柄としては十分だった。
その上病弱で、もし都合のいい子どもを産めなかったとしても試しの結婚としてちょうど良かった。
だが実際は病弱なハズレで、気味の悪い娘一人を産み落として死んだ。
娘は魔力が強いどころか、『悪霊憑き』だった。
悪魔憑きをよく生ませたなと、シブレット男爵は実家に強い抗議を出し、絶縁した。
怒って遣いをよこしてきても、問答無用で追い返した。
知り合いのゴロツキや弁護士を使えば、たやすかった。
「……終わった話だ、胸くそ悪い」
シブレット男爵は庭に出て泣いている、幼い娘を見て思う。
次の子どもこそ才能がなければ困る。
「……困るのだよ、才能がなければ」
特に、娘の方が魔力が強ければいい。
男の出世は男爵家に生まれているので程度は知れている。
が、魔力の才能のある娘なら、優秀な子孫を残せる母体として高位貴族に嫁ぐことだって夢ではない。
くくく、とシブレット男爵は笑う。
「レイラ・アンドヴァリの夫、リヒトフェルト魔術伯――あれのような成り上がりを、わしはまだ諦めていないぞ」
彼はまだ気付いていない。
とんでもない才能を、実は逃していたことに。