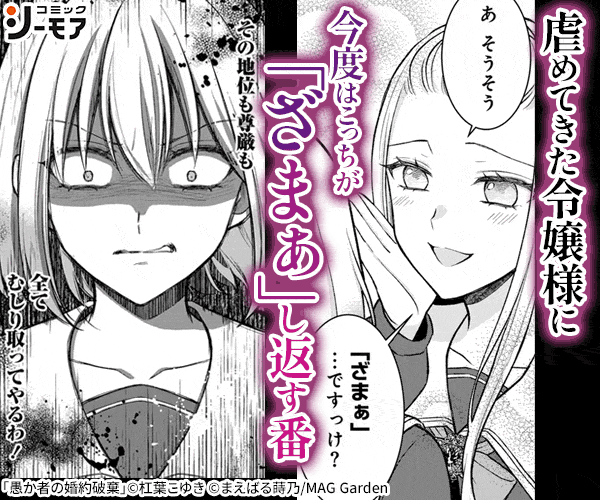10・メイドとして、今度こそ愛する家族を幸せにします
「リリーベル。君が隠していることを、当ててみようか」
突然の言葉に、私はヒッと声を飲み込んだ。
――私がレイラなのが、バレた?
「君は本当は、良家のお嬢様で、魔術にまつわる家柄の子ではないのか」
「良家、といいますと……」
「履歴書に押された貴族家の印章はシブレット男爵家のものだ。君が平民のメイドだと思い込んだ上で読むと、奉公していたシブレット男爵家に身元を証明する印章を押してもらったように見えてしまう。だがこれは――シブレット男爵家が実家ならば話は別だ」
ほっとして肩の力が抜け、エプロンの肩紐がずれる。
よかった。アンドヴァリ公爵家の令嬢と言われなくて良かった。
「筆記体が読めたのは、おそらくシブレット男爵家で魔術関係の手習いを受けていたのだろうね。貴族令嬢ならば『才なし』扱いだったとしても学があっておかしくない。どうだい?」
「過去を隠したいと思っていたのは……おっしゃる通りです」
私は観念した。
ユーグカが私とシュヴァルツの顔を交互に見ている。
不安そうな顔に、シュヴァルツは薄く微笑んだ。
「大丈夫だよ。リリーベル嬢を問い詰めたり怒ったりする気はない。事情があったのなら、雇用主としてきちんとはっきりしておきたいからだ」
真面目な調子で、シュヴァルツは私に向き直る。
「雇用するからには、君の保護監督責任を負う。まだ幼い君だから尚更、守るべき時にきちんと守れるように、嘘偽りない君の事情を知っておきたいんだ。いいかい?」
「はい」
シュヴァルツと、ユーグカとイスカリエさん。
三人の目の前で、私はリリーベル・シブレットとしての来歴を説明した。
前妻の娘だったので、父から酷く冷遇されていたこと。
『大自在の魔女』の力を『悪霊憑き』と恐れられていたこと。
この環境ではまともな人生を送れないと思い、独り立ちするために努力してきたこと。
「努力とは言っても、どうやって?『大自在の魔女』の力の使い方を教えてくれる人はいなかっただろう」
「レイラ・アンドヴァリ公爵令嬢の伝記を読んで、見よう見まねや想像で……。父に魔道具の内職を任されていたので、そこで魔力の使い方や仕組みを学びました。行商人とも縁を作って、こっそり逃亡資金も貯めたんです」
「……苦労していたんだな」
私の説明を聞きながら、シュヴァルツの顔が酷く険しいものになる。
妾の子だったシュヴァルツと、前妻の子だったリリーベル。立場こそはまったく同じではないものの、親から酷く冷遇されて、利用されて生きてきた所は同じだ。共感してくれているのだろう。
「『大自在の魔女』の力を持ってるとばれれば、実家から逃げられません。私は自分の幸せのために、自分が幸せにしたいひとたちのために、『大自在の魔女』の力を使いたいと思ったんです」
口にした瞬間、目の前が輝いた気がした。
そうだ。そうだったんだ。
前世は世界のため、国のため、自分のたった一つの幸福な未来を諦めて命を捨てた。
リリーベルとして生まれ変わっても、実家のために搾取され続けていた。
能力は、今度こそ自分の為に使いたい。
「旦那様。私はこの力を使ってメイドとして、今度こそ愛する家族を幸せにします、全力で!」
シュヴァルツが目を見開いている。眩しいものに驚いた顔のようだ。
私ははっとして、慌てて言葉を言い換える。
「あっ、愛する家族って、その……! 出過ぎた言い方になってしまいました! 愛し合ってるご家族の旦那様とユーグカ様の幸せを、守りたいという意味です! はい!」
私は慌ててごまかした。
シュヴァルツはくすっと笑う。初めて見た、27歳のシュヴァルツの屈託のない笑顔だった。
「イスカリエも君も、大切な使用人で城の一員だ。家族のように仲良くしていこう」
「よろしくお願いします!」
ユーグカがはにかむ。私も笑顔を向けた。
◇◇◇
私はイスカリエさんに本格的にお城の業務について教えて貰った。
メモ帳を肩からぶら下げて、イスカリエさんの後をついていく。
「そういえば、この屋敷ってどうやって買い物をしているんですか? そろそろ生鮮食品の備蓄が減ってきたのですが……」
「船で対岸の街に買いつけにいきます。行商人もまれにきますが、旦那様が呼んだときだけです」
「そうなんですね」
「他にも手に入れる方法はあるのですが、こちらはちょっとイレギュラーな時の対応で」
「イレギュラー、ですか」
そんな話をしているころ。
私はまだ気付いていなかった。
城の玄関に、一人の若い女の子がやってきていることを。
豊かなツインテールを靡かせ、腰に手を当て、白装束の裾を靡かせる不遜なポージングの少女。
「新しいメイドが入ったそうだけど、私はまだ見ていないんですからね」