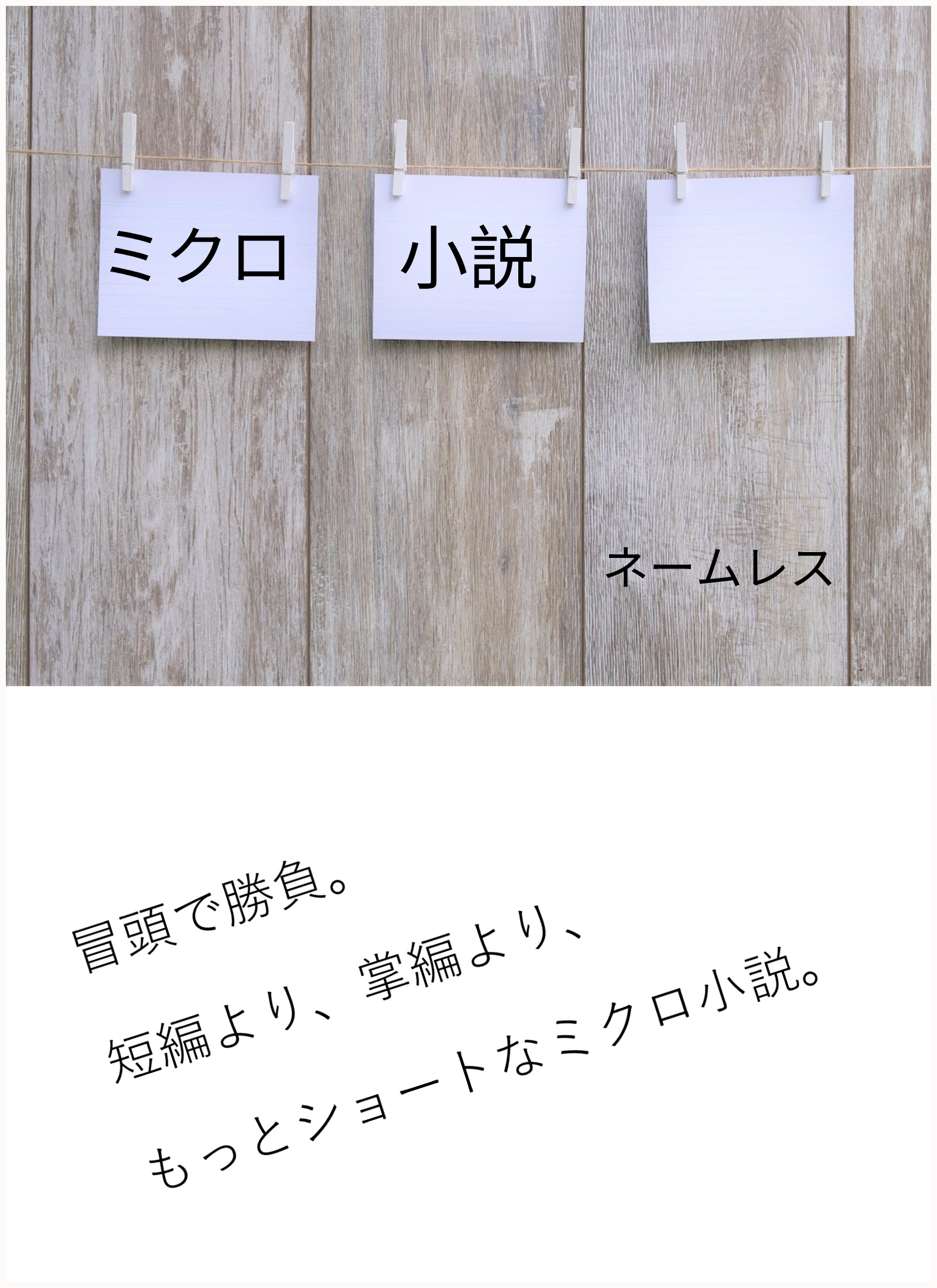第9話 竹取の翁(たけとりのおきな)
僕はふたたび裏山の竹藪を眼前にして竹藪を左から右へと見渡した。
そこで竹藪の全体像をさいど把握する。
そうかやっぱり違和感の正体はこれだったんだ。
僕は竹藪の中央に生えている風でしなった竹に手を当てた。
そしてその竹の中心に生えている七本の竹をながめる。
それらをひとつの塊として見てからほかの竹グループと見比べる。
この竹たちが同じ時期に生えて同じように成長したならば陽の当たりかたによっては多少のバラつきはあるだろうけど、この竹一本一本の繋目は均等な高さになるはずだ。
間引きされた竹たちの成長速度が、このわずかな期間でここまでずれるわけがない。
小屋の中にあった竹細工にもこのように繋目がずれている物があった。
この八本の竹だけがほかの竹とは成長速度が違っている。
つまりこの八本の竹はなんらかの理由でこうなった……これはどういうことなのだろう?
僕がずっと気になっていた違和感は、この竹たちの関節がほかの竹よりも半分ほど下にずれていることだった。
これは意図的に誰かがこの細工をしたということなのだろうか?
つまりは人為的な加工。
僕はその竹たちを左右に、それにうしろに前にと様々な角度で揺すったりしてみたけれどなにも起こらなかった。
これは専門家に話を訊いたほうが早いだろう。
※
僕は小屋に戻って明日事情を訊きたいという旨を、さっそく専門家に一報した。
急な物事の伝達は防人専用の伝書鳩に依頼する。
伝書鳩は空へとはばたいていく。
見上げた空から鴎が帰ってくるということはなかった。
今日は、もう、戻ってこなさそうだ……。
――――――――――――
――――――
―――
翌日僕が竹取の翁さんのもとを訪ねると、ちょうど仕事に向かうところだったようだ。
ここからすこし離れたところに竹取の翁さんを見送る年頃の娘さんがいた。
豪華な着物を羽織った彼女は鴎より二、三歳ほどは年上に見える。
この夫婦にあの竹の中から生まれた子ども以外にほかに子どもがいたなんて初耳だ。
……あるいは子どもではなく親類かもしれない可能性もある、か。
女性のうしろには多くの竹細工が置かれていた。
その中でも特に目を引くのは棚だ。
竹細工の中でも売れ筋なのだろうか。
棚は互い違いにしていくつも重なっていた。
ほかにも竹取の翁さんが作ったであろう様々な竹細工が店先のように並んでいる。
なかには民が掃除のときに使っている竹箒や日常で使う竹の桶なんかもある。
あれらは全国の購入者のもとへと運ばれていくのだろう。
「こんにちは」
さっそく竹取の翁さんに挨拶をする。
「こんにちは。おや? あんたかいあの伝書鳩……?」
「はい、そうです。昨日伝書鳩でご連絡さしあげた防人の青鬼と申します」
「ほう、それでなにやらわしに話があるとか?」
竹取の翁さんはすこしだけ腰を曲げてその手で腰をトントンと叩いている。
同時にしゃがれた唸り声がもれた。
”く”の字の姿勢にもいままでの苦労が滲み出ている。
ここまでくるのはな並大抵のことではなかっただろう。
「はい、すこしだけお時間を拝借できればと思います」
「ほう、それで」
「あの、あちらのかたは?」
僕はその前に気になったことがあったので僕に対して軽く会釈してくれたうら若き娘さんのほうに手のひらを向けた。
「ああ、あの娘?」
竹取の翁さんも確認のためにその着物の女性を指さした。
その指先、いや手全体がまさに職人という手だ。
年季の入った両手にはいくつものタコや細かな傷跡があった。
長いあいだ竹を切ったり削ったりしてできたものだろう。
「はい、そうです」
「あれはうちのひとり娘じゃよ」
えっ!? やはり娘さん? これで親類の線は消えた。
「ひとり娘? お子さんはおひとりなのですか?」
僕の声は自然と強まっていた。
竹藪の竹の中から見つかった赤子はいったいどこに消えたんだ?
「ああ、そうじゃがなにか?」
竹取の翁さんは腰に手を当てたままの険しい顔から一転して、目尻が下がって深いしわの走った柔和な笑顔になった。
竹取の翁さんは微笑みながら娘さんを見ている。
僕にはわからない感覚だけれど、我が子は目に入れても痛くないという言葉はまんざらじゃないのだろう。
「あの、大変失礼なのことをお訊きいたしますけれど……竹藪で発見された赤子は……」
僕ら防人は仕事柄プライベートなことに踏み込んでしまうことも多い。
人にはそれぞれ事情がある……いいたくないこともあるだろう。
それでも僕は防人、そこは譲れない。
「ああそれがあのかぐや姫じゃよ」
竹取の翁さんはその若い女性を指さした。
えっ……ど、どういうことだ?
その女性は自分が話題の中心にいることに気づいたのか、体の前で両手を重ねて
僕がここにきたときよりもさらに深く頭を下げた。
とても礼儀正しくしっかりとした教育がなされている。
「で、でもつい数ヶ月前までは赤子だったのではないんですか? それがこんな急成長を……」
「そうじゃよ。不思議なことにあれよあれよという間にあの姿じゃ」
「そ、そんなこともあるんですね?」
「まあ老い先短いわしら夫婦に神様がかぐや姫を贈ってくれたんじゃないのかのぅ」
「なるほど」
御伽の国ではそんな不可思議な話は日常茶飯事で古今東西そんな物語で溢れている。
特別おかしな話というわけでもない。
「いまじゃ他所の都からかぐや姫の機嫌を伺いにくるくらいじゃ。石作皇子殿。車持皇子殿。阿部御主人殿。大伴御行殿。石上麻呂殿という名だたる貴公子から引く手あまたでな」
「あの美貌ですからね。わかります」
「これもまた年老いたわしら夫婦に花嫁姿を見せるための神様の贈りものだと思っておるんじゃよ」
なんて前向きな人だ。
「あの、今日僕がここに伺った件なのですが」
「なんじゃな?」
「裏山の竹藪の中に一本というか、その竹を中心とした八本。その八本の竹にふつうとは違う竹があるんです……それについてなにかご存知ないかと」
「どんな竹じゃ」
「周りの竹とは明らかに成長の速度が違うんです。それに竹のなかの一本はやけに風にしなっていました」
「はて? あれじゃろか。わしがかぐや姫を見つけた竹」
「かぐや姫さんを?」
「そうじゃよ。裏山の竹藪の中央にある竹じゃよ」
「そ、そうです。その竹と回りの七本の竹です」
「おお~それならやっぱり! それはかぐや姫のいた竹じゃな」
「で、では。あの竹はどういう仕組みになっているのでしょうか?」
「あれはじゃな。かぐや姫を見つけたときにあの周囲の竹はぜんぶ刈ってしまったんじゃよ」
「ということは本当はあの場所に竹は存在していないということですか?」
「厳密にいえばかぐや姫が座していた一本の竹の根元だけが本物の竹なんじゃよ。根元より上は別の竹細工を被せてある。風にしなっていたというのは根本より上が接ぎ木の竹細工だからじゃろう。竹細工は軽量化されていて脆いからのぅ」
なるほど!?
接ぎ木の竹だからほかの竹と成長速度が違っていたのか。
それに竹のしなりかたは中身の薄さでもあったのか。
「ではその周囲の竹は?」
「おお。かぐや姫の竹が一本じゃ淋しいじゃろうと思うてなその周りにも竹細工を埋めてあるんじゃよ。まあ、かぐや姫が誕生した記念碑みたいなもんじゃな。ほかの七本は深く埋めてあるからそんなに揺れもしないじゃろうが」
かぐた姫さんのいた下のところだけ本物の竹だから、周りの七本とは繋ぎ目がずれていたんた。
ただし他の七本の繋ぎを合わせるのはある種竹細工職人のこだわり。
ようするに七本の竹も竹細工だけれど土の中に埋まっていて、かぐや姫さんのいたところまでは天然の竹で、その上からが竹細工。
そのかぐや姫さん誕生の記念碑はもう竹取の翁さんの作品と呼んでもいいかもしれない。
人間はよく自分の子どもが生まれたときに記念品を残したりする、今回は、あの竹の集まりが竹取の翁さんのそれだったんだ。
「わしはこれでもそこそこの竹細工職人じゃからな」
竹取の翁さんはそういって自分の腕をポンポンと叩いた。
この身振り手振りは腕に覚えのある職人がときどきする仕草だ。
職人としての誇りだろう。
「存じております。そういう理由から竹がしなって成長速度が違っているように見えたんですね。納得いたしました」
さすがは専門家……というより竹を切って接ぎ木をした張本人か。
「かぐや姫を見つけときはあんたの脛ほどの高さで竹を切っておるからな。それより上は竹細工じゃから上にポンと引けば簡単に抜けるはずじゃよ。それに中も削ってあるからそれなりに軽い作りになっておる」
へ~重要な情報をきけた。
そんなからくりだったとは。
「あの、かぐや姫さんを発見したときもあの竹藪の竹はあんな歯抜けだったのですか?」
「いいんや。立派な竹林だったよ」
竹取の翁さんはかぶりを振った。
「ではなぜ伐採されたのかご存知でしょうか? やはり間引きと竹細工の素材を探すためですか」
「ああ、それに近い理由じゃよ。いまは竹と竹細工の需要も多いしのぅ。それにほかの竹の成長を阻害しないように間引きする目的もあったんじゃ。だからいまはあんな状態になっておるんじゃよ」
竹取の翁さんは口元に手を置いてなんどか頬をさすった。
そのときのできごとを思い返しているようだった。
「七、八本の束くらいがちょうどいい間隔でな。ただあまりに竹を取りすぎてあのざまじゃ。たからここ数週間はあの竹藪には誰も入ってはおらんな。もうあそこから竹を刈る気もないからのぅ」
数週間立ち入っていないないということは、雨風、他所からの落ち葉や砂埃などが地面を覆いかぶすだろう。
いま、裏山の竹藪には昨日の僕が残した足跡しかない。
怪しい男があの場を逃げたのならその男の足跡が残っていなければならない。
それはつまり喜作くんの証言が真っ向から否定されたことになる。
「なるほど。竹取の翁さんも間引きをしていらしたんですよね?」
この質問をするとまた竹取の翁さんと目が合った。
「そうじゃよ。わしは間引きと同時に竹細工に使う竹の選定をしておったんじゃ。
もともとかぐや姫を発見したときも間引き作業の下準備じゃったし。そこに一本ぼんやりと光る竹があってそれを切ったら中にかぐや姫がおってじゃな……」
「……なるほど。けれどいまは歯抜けの竹藪になっていますけれど、あの量をひとりで間引きするのはそうとうな手間だったんじゃないですか?」
「あ~わしの間引き作業は合間仕事じゃよ」
「えっ!? というのは?」
「あの竹藪の間引きは主に複数人の出稼ぎの民がやっておったんじゃ」
「そうなんですか」
「ああ。わしはその管理監督が主な仕事で間引きはそんなにやっておらんのじゃよ。どちらかというと竹の品質の確認をおこなったようなもんじゃわい」
「とても重要な情報をありがとうございます」
「いやいや。防人に協力するのも民の仕事じゃしな」
「そういってもらえると大変ありがたいです」
※