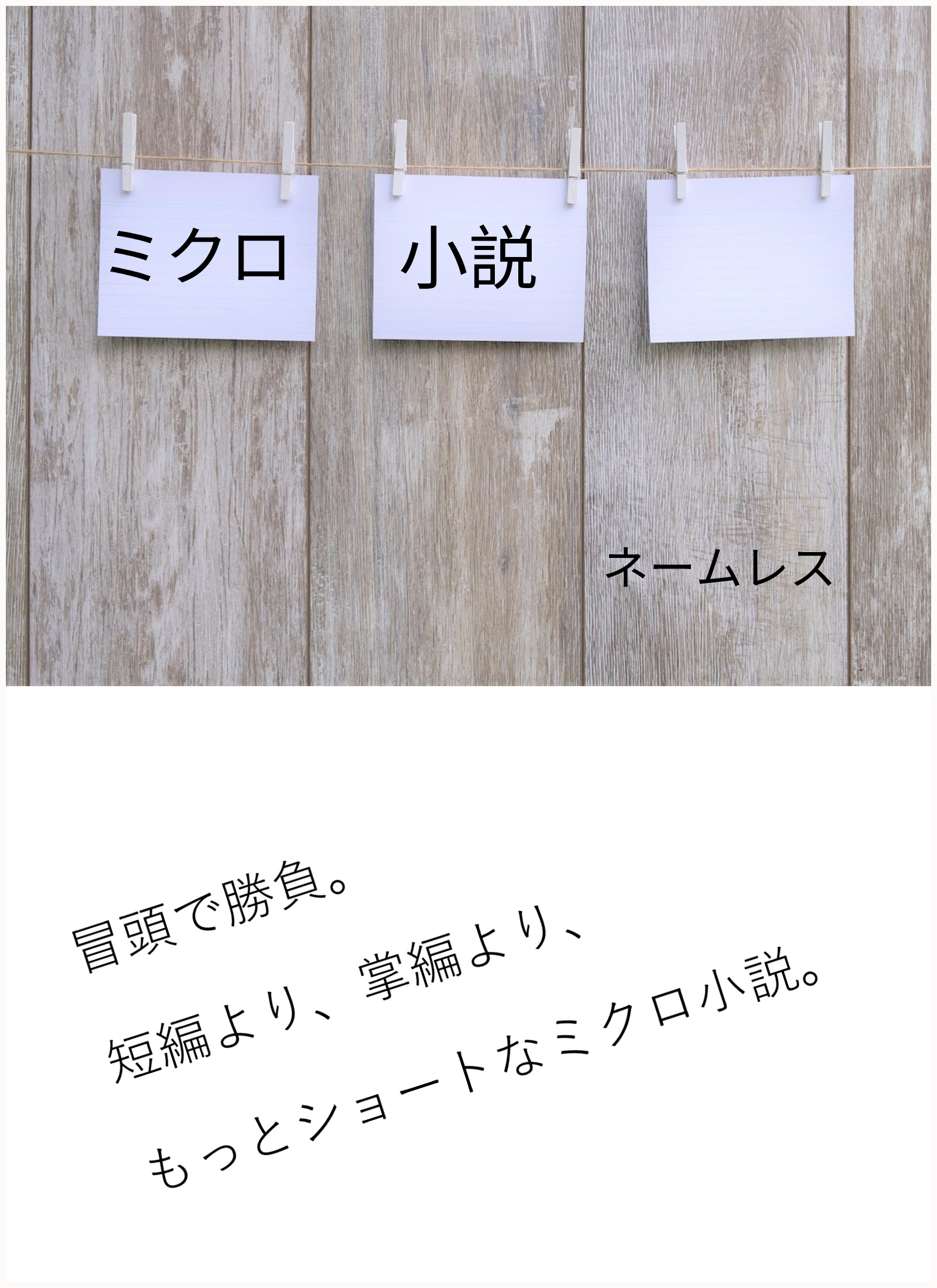第60話 「おじいさん」と「おばあさん」
見渡したさきにはいくつもの山並みが連なっている。
その中のひとつに裏山が見えた。
さらにそのさきは開かれた海も広がっている。
青い水面には反射した太陽がゆらゆらと揺らめいていた。
「ばあさんや。つぎはどこにいこうかのう?」
おじいさんは、まるで切り出したかのような石の椅子に腰をかけている。
――コトン。なにかが地面を擦った。
おじいさんは抱きかかえるようにして火縄銃を握っている。
「どこにしようかのぅ」
おばあさんは悩む素振りをみせた。
ふたりがいる場所は必然的に眼下の山々よりも高い場所ということになる。
ここから見る海はこじんまりしていてまるで洗面器に水を溜めたように些末だった。
太陽の光が射した場所に薄っすらとした小さな島がある。
「なんじゃ、まだ考えておらんのか?」
おじいさんは体から火薬のにおいを漂わせて訊いた。
「そうじゃのぅ、どこにしようかのぅ。果実はほぼ全滅じゃし。いまさらあの雪国からリンゴを取ってきたところでたいした収益にもならんしのぅ。そもそもあんな寒いところはごめんじゃ。あの童地蔵にも話が通じんし」
ふたたび考え込んだおばあさんの耳に変化が現れた。
ふだんは湾曲し弓状になっている耳の先が狼のようにみるみる尖っていった。
その弧は完全な角となった。
着物からでているしわしわな腕と足の皮膚がにゅいんと伸びパキパキと裂けはじめた。
皮膚の中からなにかの獣のような体毛が見える。
むあっと開く口の中には牙らしきものもある。
「ばあさん。顔。顔。やめておけ」
おじいさんに諭されたおばあさんはちらりとおじいさんを見る。
眼の中は蜘蛛の巣のように血管が血走っていて、瞳孔も縦長の爬虫類型に変わっていた。
「はいよ。ところでじいさんや。あのときの洪水わしまで巻き込まれるとこじゃったぞい?」
「ばあさんがあんなもんでくたばるかいな?」
「わからんじゃろ?」
おじいさんは火縄銃を右脇にはさみ地面に片膝を立て片目をつむった。
阿吽の呼吸でおばあさんは自分の親指と人指を擦り合わせる。
――バチっと指先に火花が散った。
おじいさんははるか彼方を飛んでいる、鴈に狙いを定めた。
おばあさんは火縄銃から垂れた縄に着火させる。
縄はわずかな白煙と火花を放ち、火は縄の上に向かってシュルシュルと走っていった。
――ドーン。
それから数秒も経たないうちに山頂に重く乾いた音が響いた。
――うひゃー。
おじいさんは狂気じみた声を上げニタニタと陰気な笑みを浮かべた
ふたりの目の前で鴈は螺旋を描きながらクルクルと山中に落ちていった。
「じいさんや、また弱い物いじめかえ?」
「いいんや、ただの狩りじゃよ。狩り! 狩り最高じゃ! それにばあさんが火を点けたんじゃろ?」
「ついつい、いつもの癖じゃ」
「ばあさんじゃって雀の舌を切っては棄て、切っては棄てして楽しんでおったじゃろ? 握りばさみでちょっきん、ちょっきん」
「ありゃ、狩りじゃのうてただの暇つぶしじゃ」
「狩りよりもタチが悪い。どっかの竹藪に棄てたのを埋めたのもわしじゃ。まったく世話のやける。後始末はちゃんとせい」
おじいさんの目は吊り上がり引金にかけた指先は鈍色の鋭い爪になっていた。
「おい、じいさんや。じいさんじゃって爪と目が変化しとるぞ?」
「おお。悪い。悪い」
「なにが悪いじゃ。意地悪爺さんになりかけておいて」
「いいやいいや。ばあさんこそ、さっきはどこからどう見ても意地悪婆さんじゃたわい」
おじいさんは――くくく。と笑った。
「いつか仕留め損ねた女子を殺りたいのう」
「ああ。あの物の怪の?」
「あのときは右の羽をかすめただけだからのう」
「どこがじゃ。かすめたじゃなく右の羽に命中じゃ。ありゃ死んどるかもしれんな」
――父上。母上。
そこに、おじいさんとおばあさんを呼ぶひとつの声があった。
「おや、桃太郎かい?」
そう言葉を返したおばあさんはもうすっかり人の姿へと戻っていた。
「僕の影武者が殺されたみたいだよ」
「だ、誰にじゃ?」
おじいさんのしゃがれ声が山中に木霊した。
遅れておばあさんの――なんじゃと。という声も混ざった。
「赤鬼ってやつ。だから鬼ヶ島のお宝は手に入らずってことだね。最近組織は金欠だね」
おばあさんの耳がまたメキメキと伸びて皮膚が割れた。
「んで。それを捜査したのが青鬼ってやつだって」
「また鬼か。津々浦々で展開していた葛籠箱の見世物も潰されてしまった。いまじゃ御上の御触れでお宝選びの見世物はぜんぶご法度じゃからな」
おばあさんは眉間にしわを寄せて阿修羅のような顔を見せた。
「おのれぇぇ鬼属!」
憤怒の声が海へと駆けていった。
その声はここからはるか遠くに浮かんでいる島にさえ届いたかもしれない。
おばあさんは山姥と呼べるような異質な容姿をさらしている。
山の上にはとても人間とは思えないおじいさんとおばあさんふたつの姿があった。
「母上、落ち着いてください。浦島太郎がいま竜宮城の財宝を持ってきますから」
慌てた桃太郎がおばあさんを慰めた。
「いつ間にそんなことを?」
「以前僕が立てた計画です。竜宮城の亀がときどき浜辺にいることを知っていましたので」
桃太郎がそういったあと自分のうしろに――おい。と声をかけ――忠之助。と繫げた。
「はっ」
ガサガサと草を分けて姿を見せたのは忠之助だった。
片膝をつき跪くその態勢は組織に忠誠を誓う姿勢だ。
「こいつは僕が操ってる『甘露屋』のひとり息子」
「ほ~桃太郎や。なにを考えおるんじゃ」
おじいさんがきょとんとしている。
「もちろん。『奇々怪々』の拡大です」
「立派な志じゃ。それで浦島太郎のやつはなにをしてるんじゃ?」
「母上、父上。まず話をきいてください」
――桃太郎の命を受けた弟の浦島太郎は町の果物屋の『甘露屋』に求職ということで内部に潜り込んだ。
それは『甘露屋』を意のままにするためにだ。
そしてひとり息子の忠之助を操ることで『甘露屋』の若旦那に様々な条件を飲ませることに成功した。
浦島太郎は竜宮城の財宝を狙うため策を弄す、まずは遣いの亀とお近づきになること。
そこで考えたのは地元の子ども三人、源太、喜作、茂吉を”おやつ”で手なづけたうえでいじめから亀を助けるというマッチポンプ。
たいした罪の意識もない三人はおやつと引き換えに指示通りに亀をいじめた、
もっとも三人は大人の頼まれごとを引き受けただけの感覚だった。
浦島太郎は子どもを褒めるという”おやつ”も与えた。
このおやつが効いたのは喜作だった、褒められることにこの上ない悦を覚えた喜作にとってそれは僥倖となった。
三人にはもはや人ではない忠之助の見張りをつけてある。
浦島太郎は偶然を装って亀を助けたあとは『甘露屋』で亀を接待し竜宮城へと案内してもらう。
浦島太郎はそれに成功し現在は竜宮城にいる。
ただ完璧主義の桃太郎には気に入らない点があった。
それは浦島太郎が『甘露屋』でなにげなく話した話だ。
……父と母の両親が健在だということ。
こともあろうに『甘露屋』で話しが世間話が広まってしまったこと。
流れ流れて瓦版に『奇々怪々』と浦島太郎の接点が取りざたされてしまったのだった。
その情報の発信元は猪だった。
これを良く思わない桃太郎は竹藪の間引きで出稼ぎにきていた男に大判を握らせて猪の殺害を依頼した。
桃太郎は情報が外に洩れれば洩れるだけ、組織に危険が及ぶと考えていた。
とくに家族構成がもれるのは致命傷だと思っている。
※
「桃太郎や。おまえはほんに賢い息子じゃ。この老いぼれにとっていちばんの宝じゃ」
「ほんに抜かりないのぅ~。反対に浦島太郎はどこか抜けておるからのぅ」
「父上。母上。お褒めいただきありがとうございます」
――――――――――――
――――――
―――