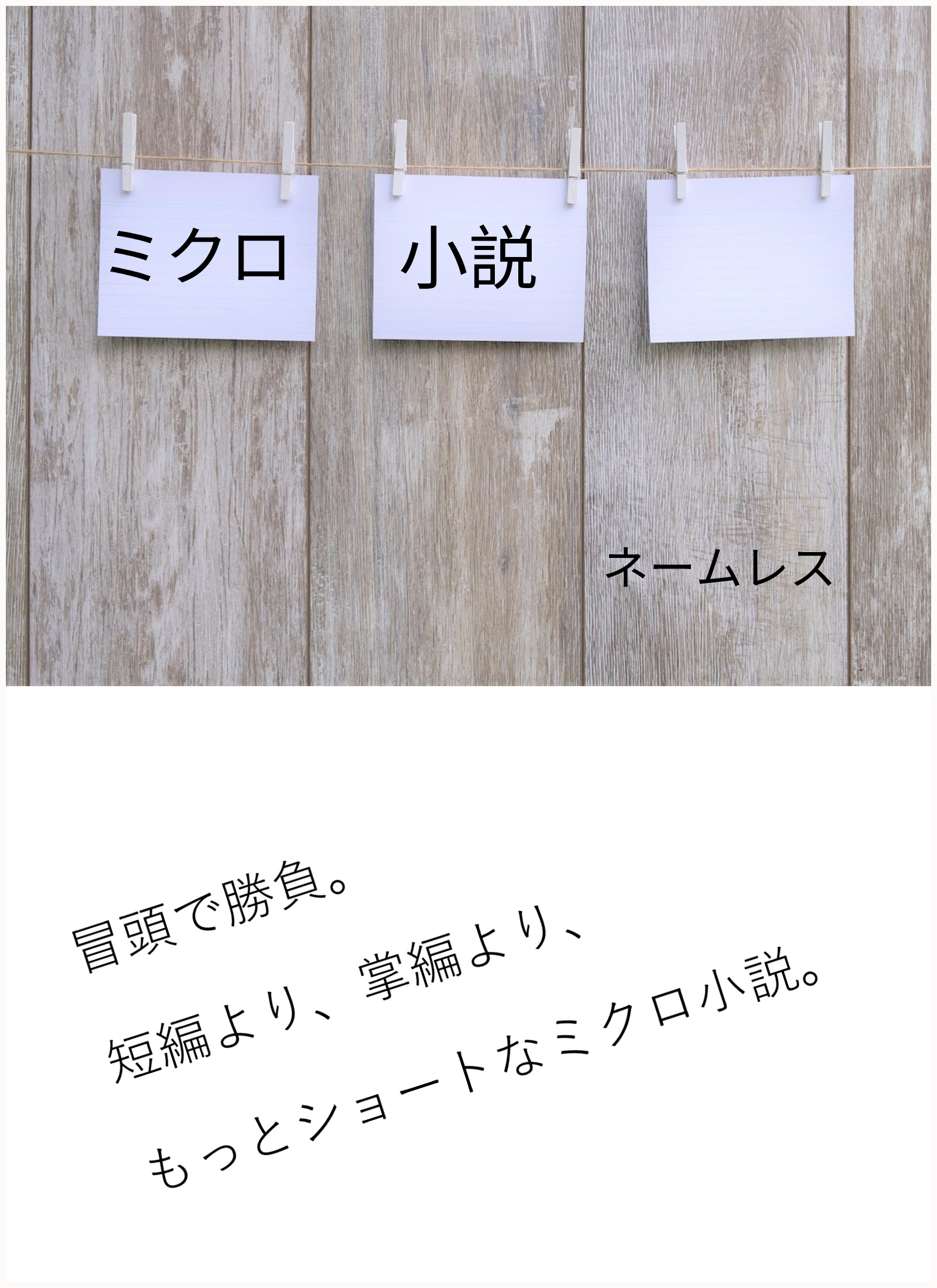第24話 遺書
職業柄こんな経験も多いのだけれど目を背けたくなるような凄惨な光景が広がっていた。
チュン太さんに教えられたその家の床で、仰向けになって死んでいたのはチュン太さん本人だった。
僕はチュン太さんの体に触れた。
「もう、手遅れか……」
体はすでに冷たくなって口の周りも血で赤く汚れている。
鼻にかけても血でべったりだ。
それに昨日ついた墨の色も残っている、チュン太さんで間違いないだろう。
そのかたわらには血のついた錆びたはさみが転がっていた。
これで自分の喉を……おそらく昨日の時点で、すでに……。
チュン太さんの隣には真新しい文が四つに畳んで置いてあった。
その横には開封されたもうひとつの文もある。
これは昨日僕が伝書鳩で送ったものだ。
僕は置かれたままの四つ折りの文を開いた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これは発見するのは、きっと青鬼さんか鴎さんだと思います。
そしてこれを読んでいるということは僕はもう死んでいるというとですね。
すみませんはさみを失くしたというのは嘘です。
はさみはある人にあげました。
誰かの幸せのために。
竹藪にいる仲間たちを見つけてくれたんですね。
ありがとうございます。
ただ、見つけたところでなんだってことなんですけど。
だって僕らは半獣や物の怪ではなくただの獣です。
僕らの仲間がいくら殺されても防人の捜査対象にはなりません。
じつは僕は言葉がしゃべれません。
だから、文字で会話をさせてもらいました。
獣の中にも僕のように文字の読み書きができる個体も存在します。
あの竹藪の事件が世間に公表されることが僕の目的です。
そろそろ僕も仲間のところにいきます。
いつかは獣も住みやすい世の中になると信じて。
”誰かの不幸も幸福に交換できる”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
僕はそれを読み終えてふたたびチュン太さんの亡骸に寄り添った。
そうか、僕の文がチュン太さんを殺してしまったのか……。
チュン太さん失礼します。
僕は両手を合わせてからチュン太さんの嘴を上下に開いて口腔内を調べることにした。
クルクルと巻かれた舌の包帯を解いていく。
傷ひとつない舌。
噛んだというのは嘘だったんだ。
口の中に怪我らしい怪我はなかった。
半獣や物の怪を装うために怪我をしたように見せかけていた。
獣の訴えでは防人は捜査はできない、それがたとえ重大な傷害や殺害事件であっても。
まさか獣にも文字の読み書きができる種がいるなんて……。
これじゃあ鴎が町医者に話を訊いたって無駄だったわけだ。
なんせチュン太さんは怪我をしていなかった。
それに半獣や物の怪じゃなければ会話が成り立たないから、診察を受けることもできない。
ついに、僕が危惧していたことが起こってしまった。
法度の盲点。
チュン太さんの仲間も獣である以上、どんな残酷な目にあっても防人の捜査の対象にはならない。
チュン太さんが伝えたかったのはそれか。
くそっ……なんて無力なんだろう。
チュン太さんの本当の目的は【防人に雀さんたちの遺骨を見つけさせる】ことだ。
僕は文を送ることで【白骨の発見】を知らせてしまった。
それは同時にチュン太さんが、この世にいる理由がなくなった瞬間でもある。
※
――仏説。摩訶般若波羅蜜多心経。
観自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊。皆空。度一切苦厄。
舎利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。
僕はまたこのお経を聞いている。
――舎利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不浄。不増不減。是故空中。無色無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色声香味触法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明尽。乃至無老死。亦無老死尽。無苦集滅道。無智亦無得。
この仕事をしていて何度これを聞いただろう。
――以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離一切顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸仏。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。
これを聞くということは誰かの死が目の前にあるときだ。
――故知般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。真実不虚故。説般若波羅蜜多呪。即説呪曰。羯諦。羯諦。波羅羯諦。波羅僧羯諦。菩提薩婆訶。般若心経。
チュン太さん……僕は気づけなかった。
※
二日後、チュン太さんの弔いを終えて一区切りはついた。
結局あの雀さんたちを殺害した犯人は不明なままだった。
こんなとき自分の無力さを痛感する。
後味が悪いままこの事件の幕は降ろされた。
獣が被害者ではもうほかに動きようがない。
僕は民たちの集う見世物でも見て、すこし気持ちを切り替えようと町の入り口に足を向けていた。
この竹藪はいやでも事件を思いだしてしまう。
なにせ通り道なのだから。
今日も民が殺到していた。
そういえば見世物を見るのに見物料が必要になったって鴎がいっていたな。
それに参加料も。
――ハズれか~!
そんな残念そうで楽しそうな、はしゃぎ声が耳に飛び込んできた。
いまの僕にはわいわいとした賑やかさは堪える。
もう、帰ろう。
とてもじゃないけれどいまの気分には合わない。
「あの?」
僕がひっそりその場から立ち去ろうとしたときだった。
ひとりの民に声をかけられた。
ときどき『仲裁奉行所』の前で挨拶を交わす顔なじみの男性だった。
「なんでしょうか?」
「俺。あの奇術師がきてからずっと見世物を見てるんだけど。変なんだよ」
「変?」
「なにがですか?」
「あれ、一回もアタリがでたことないんだよ」
その民は奇術師が娯楽に使っているふたつの葛籠箱を指さした。
「あの大小の葛籠箱ですか?」
「そうさ。青鬼さん、調べてくれないか?」
こんな気分だったとしても民の依頼を無下にはできない。
それに応じるのが防人だ。
……となると奇術師がこの町にきてから一度もアタリがでていないことになるのか。
なるほどそれはおかしい。
あの奇術師は大小の葛籠の箱のどちらかを選ばせる見世物だ。
確率でいってもそれだけの回数の見世物をおこなっていてアタリがでていないのはおかしい。
そもそも箱の中のお宝は本物なのだろうか?
僕はいつの間にかチュン太さんのことを仕事で忘れようとしていた。
「わかりました。調べてみましょう」
僕は、しばらくのあいだ見世物をずっと見てみた。
けれど今日だけでは、わかりそうにもない。
これは日をまたいだ調査が必要だろう。
※