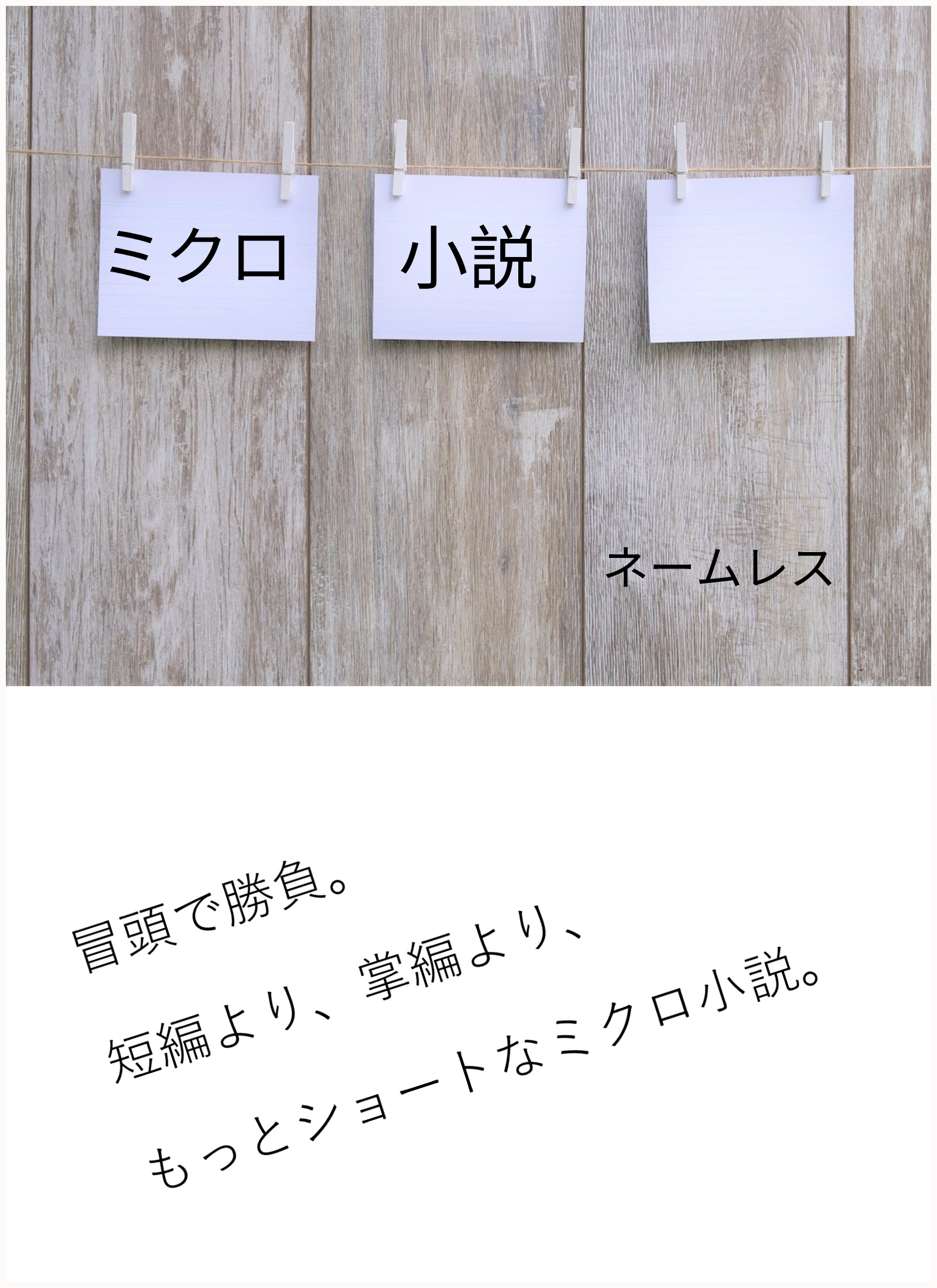第16話 そして青鬼は迷子の子どもを見つける。
「青鬼の兄ちゃんはなんでこの村にきたの?」
彼は息をきらせることもなく、ぐんぐんと僕の前を進んでいく。
雪道はお手の物ってことだ。
キミは疲れ知らずでいつもいつもそうやってこの雪原を駆けまわっているのだから当然か。
「村長さんにあることを解決してほしいと頼まれたんです」
「村長さんに? どんな事件?」
「それはですね……。父ひとり子ひとりのふたりで暮らしていた家族がいたんですよ……」
「オラの村にはそんな家族は大勢いるよ」
「そうですよね。キミのおうちはどうですか?」
「うちもおっとうとオラのふたりだ」
「そうですよね。キミとお父さん……」
僕はすこしだけ間を置いた、そのだいだも彼は僕を置き去りにするように雪道をドスドス跳ねる。
ありあまる元気、無尽蔵な体力。
「……村長さんにある依頼を受けて。頼まれたんですよ」
僕は同じ言葉を投げかける。
凍えそうなこの環境でもまったく冷たさを感じないであろう彼の背に。
きっと冷たいも熱いも感じない。
「さっきも聞いたよ」
「キミを助けてほしいと頼まれたんです」
「キミってオラのこと?」
「そうです」
「どうして?」
彼はそう質問したまま、僕のほうを振り返ることもなくまたズンズンと進んでいく。
そして呼吸ひとつ乱さずに――ねえ、どうして。そう訊き返してきた。
「キミがそうなってからゆく当てもなくこの雪原を彷徨っているからです」
「……? 青鬼の兄ちゃんなにいってんの? オラはなにも困ったことねーよー。もうちょっと村長さんのところに着くからねー」
彼は弾むように答えた。
それはこの状況でさえも楽しんでいるようだ。
まるで子どもが野を駆けるような無邪気な遊び。
「……」
「青鬼の兄ちゃん。どうして黙ってるの?」
「キミは……」
「ん?」
「キミはね」
「なに?」
「ほらキミが飛び跳ねるたびに雪原に残る足跡を見てください? キミのうしろです」
彼はそこでピタリと立ち止まると体を百八十度グルリと回転させた。
「おー。大きい穴がボンボンあるね」
無邪気な子どものはしゃぎかたと大げさな口振り。
どういう理由でそういう足跡が残るかまるでわかっていない。
「ええ、そうです。僕はその踏み固められたうしろを歩くので楽に歩くことができるんですよ」
「そう。よかったねー。オラのおかげかー」
「そうですね。石像が雪を圧迫するのですからそれはそれは歩きやすいです。キミはいま二本の足で歩いていますか? 二本の足で雪に着地していますか?」
「……ん……?」
「オラの足。両方がひとつにくっついてるみたい。オラの足一本一本で動かせない。前は別々に動いてたのに……。青鬼の兄ちゃん。これなんで?」
「それは」
「青鬼の兄ちゃん……オラ自分で足を見れない。オラの手も見れない。青鬼の兄ちゃんと白い雪だけしか見えない」
「僕はさっきキミに足跡を見てといいました。足元を見てとはいいませんでした。それはキミの視野では絶対に足元を見られないからです。足跡であればすこし離れた場所の足跡は視野に入りますから。いま足元を見られますか?」
「オ、オラ、首が動かない」
「ですよね。僕はキミと出逢ってから一定の距離をとってきました。いまのキミの首が固定された視界ではその角度からしか世界を見ることができません」
「どういうこと?」
「村長さんの待つ場所まであとどれくれいですか?」
「もうちょっとだよ」
「そこにいけばぜんぶわかります」
「わかったよ」
彼は重そうな体またを百八十度回転させた。
いま僕としていた会話のやりとりはとても深刻なやりとりだったはずなのに、それに囚われることなく僕の話を聞き入れた。
中身はやはり齢六歳……。
※