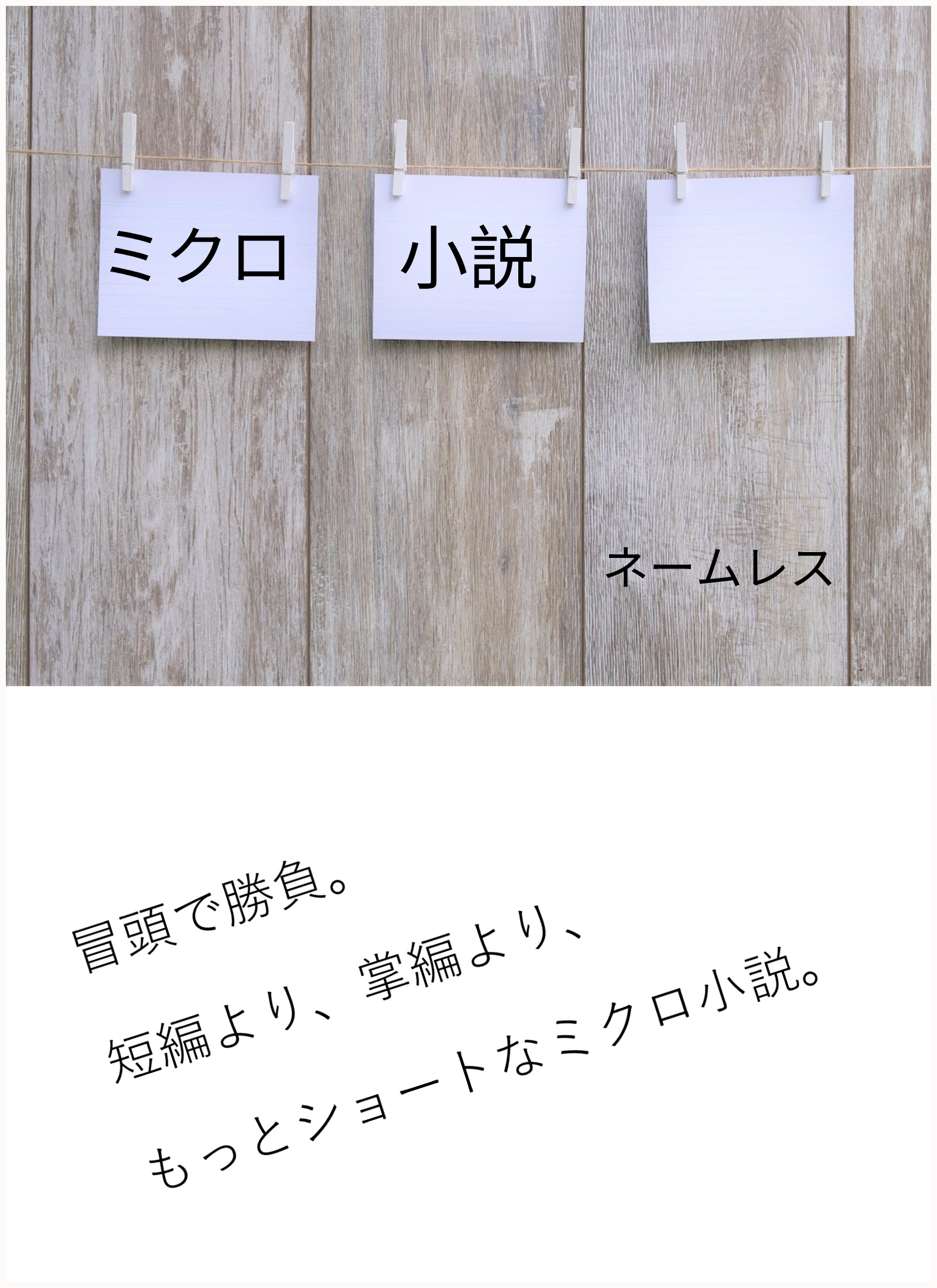第14話 雪原をいく、「おじいさん」と「おばあさん」
おじいさんの一歩うしろをおばあさんが付き添っている。
老夫婦は仲睦まじく重そうに笠と蓑を背負い、ドスドスと鈍い音を立てて懸命に雪の中を進む。
延々と伸びるふたつの足跡はわずかな時間ですぐに雪に覆われてしまった。
ヒューヒューと風の呼吸が強まっていく。
雪は天から地へと降るのではなく横殴りに地を叩きはじめた。
「じいさんやい?」
おばあさんはささやくように小さな声でおじいさんを呼び止めた。
強風の中で消え入りそうな声だった。
けれど悠久のときを過ごしてきたおじいさんはすぐにそれを聞きとる。
それができる関係性でもあった。
おじいさんは石臼でも回すように体を左に約四十五度ぐるりと回転させた。
「なんじゃ、ばあさんや?」
おじいさんはそう返事をすると阿吽の呼吸でおばあさんの視線に目を配る。
朽ちた大木がその身に吹雪を受けていた。
幹の根元には風雪に晒されたなにかが吹き出物のように大きくボコっと膨らんでいた。
突起物のさきはすこし欠けていて透明で濁ったなにかがはみでている。
「あんれまあ」
おじいさんはすこし驚くも表情をまったく変えなかった。
額も瞼も鼻も頬も口元も悴で凍っているのかもしれない。
いや表情を変えられるほどの緩みもなった。
あらかじめひとつの塊から削りだしたというほうが適切かもしれない。
おじいさんはザクザクと重石のような足跡を残しそのなにかに近づいていった。
おじいさんは重い頭を傾けて雪に埋もれたそれをじっくりとのぞきこんだ。
おじいさんはそれがなんなのかようやく理解した。
それは冷たく凍った人の鼻の先で、氷は透明ではなくすこし濁っている。
「まるで地蔵のように凍っておるのう……」
「じいさんやい。では笠と蓑を授けてあげましょう」
そういったおばあさんも、おじいさんのところまでザクザクと音を立てやってきた。
鋭い風が辺りを吹き抜け凍った人をかすめていった。
「そうじゃな」
おじいさんは手も足も使うこともなく体を動力にして起こした風で”地蔵と比喩した”人の顔、そして肩さらには全身の雪を吹き飛ばしていった。
おばあさんも職人芸のように蓑を放り投げてその凍った人に蓑を羽織らせた。
それを見届けると、つぎは笠を投げて頭に被せる。
おばあさんは百発百中で凍った人に笠と蓑を着せることに成功した。
ふたりのその行為には神仏への想いが込められているようだった。
命尽きた者はいま凍ったままで笠と蓑をまとっている。
「これでいいじゃろ?」
「そうですね」
おじいさんとおばあさんはしばらくのあいだその場で経を唱えた。
口籠る声は風の音と混ざり合ってモゴモゴとしている。
それでも御仏に対する供養としての効果は充分だろう。
ふたりは硬い表情を一度も崩すことなく、ふたたびザスザスっという音を立てその場をあとにした。
――――――――――――
――――――
―――