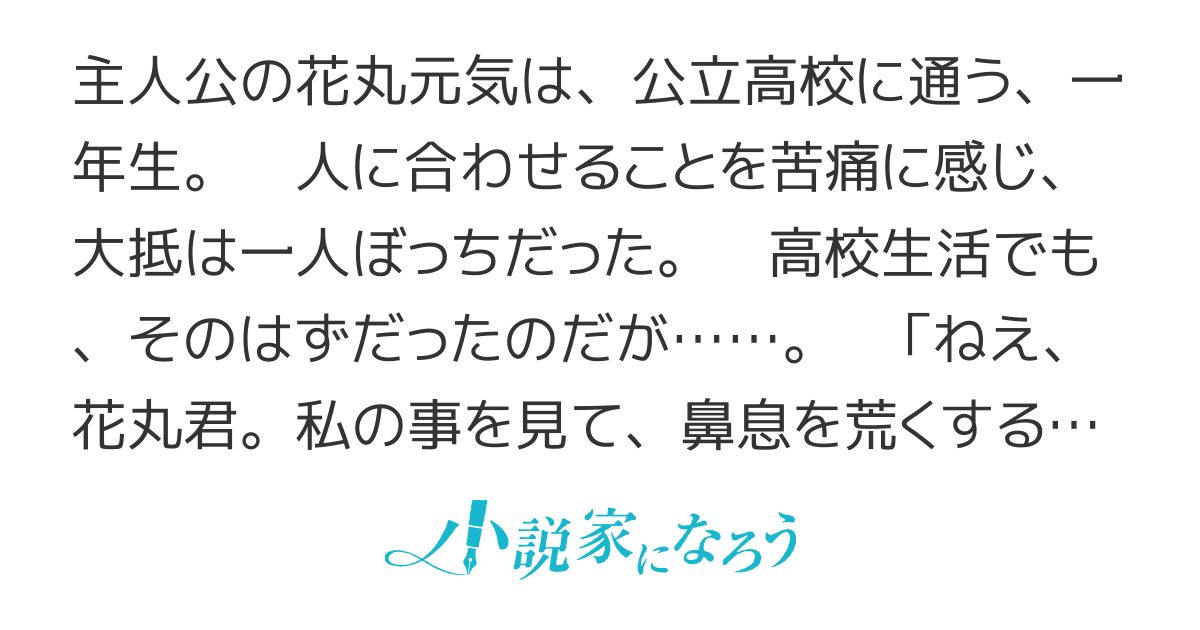映画
ペダルが踏み込まれるたび、紺色のプリーツスカートが持ち主に置いてかれまいと、ひらひらと彼女の脚を追う。そうして一舞するたび、たわわに実った果実の香りが風に乗るように、劣情を催す何かが、そこから放たれているようだ。
それに包まれているのは曲線美と言うにふさわしい曲線美。性成熟期に一歩踏み入れた女性の体だ。
長期間の使用に耐えうるよう丈夫に縫製されたセーラー服を以てしても、彼女の肢体から放たれる妖艶さを隠すことは難しいらしい。
あるいは幼さの象徴であるセーラー服と、それを身に纏う大人の体というギャップが、この上なく危険な香りを生み出しているのだろうか。
こう脚色すると俺がセーラー服の女子高生を舐め回すように眺めている変態かのように聞こえるだろうが、俺は至って真面目にその風景を描写している。それ以外にダイナミックな肢体と隷属する布の動きを表現する方法があるだろうか。
そう、ないのだ。
そして俺もあの脚に挟まれたい。生脚をさらさない上品さがこの上なく良いスパイスとなっている。俺の経験に照らせば、……40デニールくらいか?
……流石に今のは自分でもちょっとキモイと思ってしまった。
気を取り直して。
内海はじめ周りの人間に言っておきたいことが一つある。
それは俺は葵先輩に恋をしているわけではないということだ。
ドギマギしてしまうことを、恋とは呼ばない。俺は美しいものを美しいと言うためにふさわしい形容を施しているに過ぎない。そうして客体化されたものを愛する術を俺は知らない。この世の誰も知らないだろう。世間一般で愛と認識されるものは個人として独立する概念に対して向けられるものであり、自我を持たない「物質」に向けられるものではないからだ。
サン=テグジュペリ先生曰く、真の愛は、見返りを何も求めないところから始まる。
対象から何かを得ようとしている時点で、それは愛でないのだ。
だから釘を差すために言うべきことがあるとすればこう
「俺が彼女に抱くものがあるとすれば、それは劣情だ」
故にそれは愛ではない。
「そういう告白は人に聞こえないところでやりたまえよ」
刺すような視線とともに、非難めいた言葉が葵先輩の口から聞こえてきた。
俺は我に返った。
「や、やだなぁ。先輩盗み聞きですか?」
壮大なモノローグが意図しないうちに、口からポロリとこぼれ出ていたようで、焦りを取り繕うように、言葉を紡いだ。
それを聞いた先輩は呆れ顔をした。
「大きな独り言を言っておいてよく言う」
それでこの件は一件落着、となることは当然なく「で、劣情を抱く彼女とはいったい誰なんだい」
と問い詰めてくる。面白がるような顔をして。
「いや、それは」
あなたです。などといえただろうか。言えるわけがない。俺はこう見えて紳士なのだ。女性に面と向かって「あなたを見ているとムラムラします」などと言えるはずがないのだ。紳士ならそも劣情を抱かない、とか言わない。そこ。胸に秘めたる思いを口に出さないのが、紳士の第一歩なのだ。うむ、欲望が意図せぬうちに口からまろび出ているところを見る限り、それもできてないな。
「もし澪のことを言っているのだとしたら、さすがに看過できないな」
葵先輩は、探るような視線で、俺の目をじっと見てきた。
「いや、それはないです。あいつのこと異性として見てないので」
俺は即座に返した。あいつに劣情を抱くだと? 万に一つもないな。だってあの子怖いもん。もし彼女を見て俺が愉悦を感じるのだとしたら、俺は虐められて興奮するタイプの変態ということになってしまうではないか。それはない。今のところ。
「なんでぇ?! あんなに可愛いのに」
ところが先輩はさっきとは正反対に愕然とした表情を見せる。
「……あなた、従妹をエロい目で見て欲しいんですか、欲しくないんですか、一体どっちなんです?」
「生々しく、スケベな感じに見られるのはちょっと嫌だけど、全く女として魅力ないみたいないい方されると、ちょっとカチンときちゃうわけ。従姉のお姉さんとしてはね」
これが複雑な乙女心という奴だろうか。
多分違う。
*
制服のスカートをひらひらさせながら自転車を漕いでいった先輩について、到着したのは市内のショッピングモール。
駐輪場に自転車を停めながら
「なんか見たい映画とかあるんですか」
と葵先輩に尋ねた。
女子と二人きりで映画を見るというのは、無論、初めてのことである。だからと、言い訳をしたいわけではないのだか、ここでおすすめの映画をさっと提案できるような甲斐性は須くない。
むしろ潔く白旗をあげて彼女の希望を聞こうとしているところを褒めてほしい。
「スパイものかなあ」
先輩は、特に迷うでもなくそういった。
「好きなんですか」
ラブロマンス的な、もっとポワポワしたものを見たいのでは、と思っていたので、少し驚いた。
「まあ、それなりにね。気になってるのがあるんだよねぇ」
「そうですか。じゃあそれにしましょう」
「いいのかい? 私が決めちゃって」
「構いませんよ」
というか、アクション系にしたいと言ってくれてむしろ助かった。ラブロマンスに出てくるであろう、接吻シーンを女子の隣でどんな顔で見ればいいのか、俺は知らないからだ。どんな顔すればいいの? 仏頂面でもしとく? 誰か教えて?
チケットを買って、館内の売店で飲み物とポップコーンを手に入れた。
*
映画を見終えて、劇場をあとにしたところ、どちらが言うでもなく、感想を言い合いながら、そぞろにモール内を漫ろ歩きしていた。
「あの俳優がお気に入りなんですか?」
映画の主人公を演じていた、ヨーロッパ系の俳優を思い浮かべながら、彼女に訪ねた。
「まあね。今作でシリーズ完結だったし、見れて良かったよ」
「案外、続編やったりするかもですよ?」
「主人公死んでるのに?」
「直接的な描写はなかったじゃないですか。ひょっこり生きてるパターンかも」
俺がそういったところ、
「ま、それならそれでいいんじゃない。私的にはこれで終わりでいいと思うし、何れにせよ悔いはないかな」と満足した様子で呟き、俺の前腕をさするように軽くつかみ「映画、付き合ってくれてありがとね」
と熱っぽくウインクしてきた。
これが並の男だったならば、魔性の女に難なく篭絡されてしまっただろうが、俺は鋼の意思を持っているので、動揺しない。断じて動揺しない。
「先輩が良ければ、いつでも付き合いますよ」
だから社交辞令のように、そう言葉を返した。
そしたら、先輩は、少し何かを考えるような表情を見せる。
「どうしたんですか?」
俺が尋ねると、先輩は「うーん」とうなりながら
「君、彼女とかいないよね」
と聞いてきた。
「いたら、先輩と映画とか見に行かないですよね」
ていうかいるわけないですよね。分かって聞いてますよね。なんですか。おちょくってんですか。ええ、ええ。そうですとも。彼女いない歴イコール年齢の童貞です。どうもすみませんでした。
「君にまともな分別があったらね」
「ひどいな。分別くらいありますよ」
「そうか。じゃあ、ゴミ出しは君の役目にしよう」
「それ違う分別だし。読みも違うし。ていうか、なんで俺が先輩のごみの分別をしなきゃならんのです。駄目に決まってるでしょう」
「確かに。君にゴミ出しを頼んだら、細かく分別して、ジップロックに名前を付けて保存してくれそうだな。それはさすがの私も恥ずかしい」
「ちょっと!? 先輩、俺のことを何だと思ってるんですか?」
「え、レベルの高い変態?」
「違う!」
捨て置けぬ勘違いを、なんとかして訂正せねばと、対策を講じ始めた俺の横で
「あはは! 君は本当、面白い子だな。冗談だよ、冗談」
先輩は楽しそうに笑っておられる。俺はいたって、正常な反応しかしていないはずなのだが、彼女は何をそんなに面白がっているのだろうか。
「勘弁してくださいよ」
俺が泣き言を連ねるようにいったところ
「じゃあさ、好きな子はいるの?」
と聞いてきた。
「……いないですけど」
「じゃあ、さっき言ってた、劣情を抱く相手っていうのは?」
ぐぬぬ。覚えていやがったか。映画を見るうちに忘れたものと思っていたのに。
なんと言い逃れをしようかと、苦心した末に出てきた言葉は
「アイドルです」
正解だな、ある意味では。
葵日向、という人を、偶像として崇め奉る人間は、我が神宮高校には大勢いることだろう。まさに彼女こそ、神宮高校に顕現したアイドルではないか。
「やっぱり、男の子って、そういう目で見てるんだ」
先輩は、幻滅した顔、というよりもむしろ、面白そうなものを見る目で俺を見てきた。
「や、やだなぁ。全身舐め回したいだなんて、思ってないですよぉ」
「そういう気持ち悪い発言がでてくるあたり、嫌らしい妄想をしているのがバレバレだぞ」
「いや、ほんとに、先輩のこと舐めたいとか、思ってないですから!」
「え、私?」
あ、やべ。
ぶわっと、全身の毛穴から、冷や汗が噴き出してくるのを感じた。
俺が次の言葉を継ぐ前に
「変態」
たいそう、蔑みのこもった視線で、先輩は言い放った。
*
「あの、先輩」
「何? 会って、そう間もない、先輩のことを、いやらしい目で見ている銭丸君」
「……すみません、俺の名前の前に、随分と長い形容句があるんですけど、それを付けるのをやめていただけないでしょうか」
さきほどから、俺に声をかける度、そうやって俺をなじるように言うのを、辞めてもらおうと、恭しく提案をしたのだが
「え、何のこと? 会って、そう間もない、先輩のことを、いやらしい目で見ている銭丸君」
委員長殿下は、大変ご立腹の様子で、俺の提案を聞き入れるつもりは毛頭ないらしい。こちらに目もむけずに、冷たく言う。
「あの、ほんと、許してください」
俺が情けない声で、許しを請うたら
「大体さ、順番が逆だよね」
と、先輩はようやく俺のほうを向いて、不服そうに言った。
「と、言いますと」
「普通、好きになってからじゃないの? そういうの」
「……いや、おっしゃる通りです」
はい。本当のことを申し上げるのならば、全く見ず知らずの女性の、きれいな脚に欲情を抱いてしまうのは、日常茶飯事なのですが、さすがの俺も、ここで火に油を注ぐ様なことをしない分別はある。そう、俺には分別があるのだ。
いや待て。「あ、きれいな太ももだ。触りたい」という衝動は、それ自体、全く自然な感情で、決していやらしいものではないのではないだろうか。
空が青く、夕日が赤いのと同様、全くもって、自然な現象なのではないか。
ふわふわした子猫や子犬を触りたくなるようなものではないだろうか。
うん、そうだ。そうに違いない。俺はいやらしい感情を、見ず知らずの女性に抱いているわけではない。
生きとし生けるものを愛するものとして、俺はそこにあってしかるべき感情を抱いているにすぎないのだ。
ああよかった。納得した。俺はまともだ。変態とは程遠いところにいる。
「分かりました先輩。分かりましたとも。蒙が啓けました。俺は決して変態なんかではないのです」
「え、何だ急に。頭でも打ったか」
先輩は気味悪がるように俺を見てきたが、そんなことは気にかけずに、俺は続けた。
「俺が先輩に抱いている、感情の正体が分かったのです」
「……なにさ」
それは社会成立の根源にある、人間を人間たらしめる感情。
慈しみの精神だ。それをわかりやすく言い換えるならば─
「愛ですよ」
先輩はギョッとしたような顔をした。
無理もないか。俺が15年かけて出した結論に、先輩が即座にたどり着ける法はない。俺は先を行くものとして、蒙に包まれた世界で懸命にあがく後進を愛しく思い、そんな彼女に微笑みかけた。
彼女は慄然としながら言った。
「やっぱり変態じゃないか」
「なんでそうなりますか」
「いや、君。今の話を聞けば、誰だって同じ結論にたどり着くだろう」
「あれ、おかしいな」
この世の中の真理を、誰もが理解できるとは思わないが、並の理解力がある人間ならば、俺に同調してくれてもおかしくはないだろうに。
「まったく。君はとことん重症らしいな。澪が心配するのも分かる」
「え、内海に何を吹き込まれたんです」
「君がヤバい奴だってことをさ」
「ひどい風評被害だな。まったく遺憾の意である。そんなことを言ってはいかんぞう」
「だめだこいつ」
先輩は、深い深い溜息を吐いた。そんなに溜息を吐かれると、また俺の遺憾砲が炸裂してしまうぞ。大国の傘下で、長年犬をやっていたうちに極限まで練り上げられた遺憾砲の威力を知るがいい。ワンワン。
先輩は眉間にしわを寄せ、指でぐりぐりしていた。そんな顔をしたら、美しいご尊顔が台無しですよ。と心の中で忠告しておいた。
「ふーん」とまた溜息を吐いたかと思えば
「君、ゴールデンウィークは暇だろう。私に付き合い給えよ」
と、厄介な仕事を押し付けられた、休日出勤やむなしの中間管理職みたいな声音で言った。おじさんたちは、板挟みで大変なんですよね。管理職は労働基準法が適応されないから。やったね! 使い放題のサブスクみたいなものだね!
無論のこと、上長の命令を拒否する権限など、一介の忠犬にはない。
返事は、「はい」か「わん」。せいぜい「くぅーん」だけ。
ここは最大限の抗議を表明するためにも
「くぅーん」
と返事をしておいた。
誠に遺憾である。