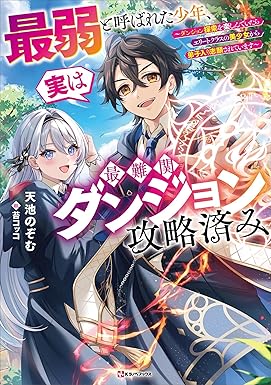第9話 ルクスの魔法
「っ……!」
ルクスに近寄った生徒の一人が吹き飛ばされた後。
Cクラスの生徒たちの表情には一様に焦燥の色が浮かぶ。
それはそうだろう。
リベルタ学園でも最底辺と呼ばれるFクラス。
そこに所属している生徒に、自分たちの仲間がわけも分からず吹き飛ばされたのだから。
ルクスが一歩踏み出すと、それまでは余裕ぶって椅子や机に腰掛けていた連中が臨戦態勢を取る。
「それで? コランの腕輪、返してほしいんだが」
「黙りやがれ! 誰がFクラスの奴の頼み事なんざ――」
「ああそう。じゃあ頼むのはもうやめるよ」
嘆息し、ルクスはCクラスの生徒たちを睨みつけた。
「返せ――」
ルクスは静かに、そしてはっきりと告げる。
途端、残っていた生徒の内、ルクスの前にいた3人が苦しそうにもがき出した。
「あ、が……」
「ぐはっ……」
「馬鹿、な……」
そして程なくして、3人はバタリと地面に倒れ込む。
意識を失ったわけではない。
しかし、3人は身動き一つ取れずにいた。
それは突如、金縛りに襲われたかのようだった。
「え? え……?」
後ろで見ていたコランにも分からなかった。
コランはただ困惑した表情で、倒れた生徒たちとルクスとを交互に見やっている。
「待ってろコラン。腕輪、取り返してやるからな」
あっさりと言われ、コランはただ呆然とするより他にない。
始めこそルクスのことを心配していた様子だったが、今はそれよりも一体何が起こっているのかという疑問の方が勝っていた。
「テメェ、何をしやがった? 一体、何の魔法を……」
唯一残っていたリーダー格の男が机から飛び降り、ルクスに問いかける。
「こっちの質問には答えてくれないのに、お前は教えてくれというのか? それって不公平じゃないか?」
「チッ……」
ルクスに言葉の意趣返しをされて、リーダー格の男は青筋を立てる。
どうやら問答は無用だと悟ったらしい。
と同時に、ルクスに何かをされては脅威だと感じたようだ。
リーダー格の男が手を掲げると、そこには火球が現れた。
「結界魔法が残っていて良かったぜ。《火球の礫》!」
「む」
ルクスはコランに当たらないことを確認し、飛んできた火球を回避する。
「それで逃げた気になってんじゃねえぞ! そらそらそらっ!」
リーダー格の男が放つ魔法は威力こそ抑えられているものの、連射性能に長けていた。
ルクスの移動に合わせ、次々に火球を打ち出してくる。
あえて魔法のランクを抑えて狭い教室内で有効な攻撃方法を選択するあたり、なるほどこの男がリーダー格なのも頷けると、ルクスは冷静に分析していた。
「ほっ――」
ルクスは回避しつつ、ある魔法を使用する。
その結果として、先程までCクラスの生徒たちが腰掛けていた机やら椅子やらが、ルクスの背後でふわふわと浮かんでいた。
「なっ!?」
次の瞬間、浮遊していた机や椅子がリーダー格の男に向かっていく。
それを男は間一髪で直撃を避けたが、驚愕の表情でルクスに視線をやっていた。
「テメェ、その魔法……。まさか《念操作魔法》か……?」
「お、知ってたか。ご名答だよ」
ルクスは口の端を上げ、その問いに肯定の意を示す。
「馬鹿、な……。Fクラスの奴が、どうして《念操作魔法》を……」
リーダー格の男が信じられないという表情を浮かべていたのにはわけがある。
《念操作魔法》――。
ルクスが扱う魔法の中でも特に使用されることの多い魔法である。
別名、念動力とも呼ばれるその魔法は、ルクスの視界に入る物体に様々な干渉を行うことが可能だ。
例えば先程のように机や椅子などを浮かせて射出することもできれば、校舎壁面の煉瓦を落下させて絡んできた相手の頭にぶつけるなどという芸当も可能。
更に言えば、干渉できる物体は無機物だけに留まらない。
――つまり、生物に対しても干渉が可能なのである。
「じゃあ、さっき他の連中が吹き飛ばされたり、動けなくなったのも……」
「そういうことだ。人間程度の大きさまでなら干渉できるからな」
ルクスがこともなげに言ったことで、男の焦燥はますます深くなる。
《念操作魔法》は、高難易度ダンジョンの中でも特に攻略が難しいとされる、《ダークエレメントの魔岩窟》の第10階層攻略時に習得可能と噂される魔法だったからだ。
「な、何故だ!? あのダンジョンは、オレが第1階層の攻略すらできなかった場所だ! それを、どうしてFクラスのテメェが――」
「隙だらけだぞ」
「う、あぁあああああっ!?」
ルクスが男に対して手を突き出すと、男は宙に浮く。
そしてそのまま、高速で床に叩きつけられた。
「ガ、ハァッ……!」
結界魔法が残っていて良かったと、男は先程言った。
確かに残っていて良かったのかもしれない。
そうでなければ、男は床などゆうに突き破り、地中深くまで埋められていただろうから。
白目をむいた男にルクスは歩み寄り、男の制服の内ポケットを物色した。
「コイツがリーダーっぽいし、たぶん……。あった!」
ルクスはお目当てのものを見つけ、声を上げる。
その手には様々な鉱石を埋め込んだ腕輪が握られていた。
「さて、連中への口止めは後にするとして――」
ルクスは腰を抜かしていたコランに歩み寄り、手にしていた腕輪を差し出す。
「ほら、約束通り取り返せた」
「あ、ありがとう……」
腕輪を両手で受け取り、呆然としたままで呟くコラン。
そして、コランは先程から気になっていたことを尋ねる。
「る、ルクス君……。君って一体……」
「俺? 俺はコランのクラスメイト、ルクス・ペンデュラムだよ」
コランの問いに答えると、ルクスは出会った時と同じように、ニカッと笑い返してみせた。