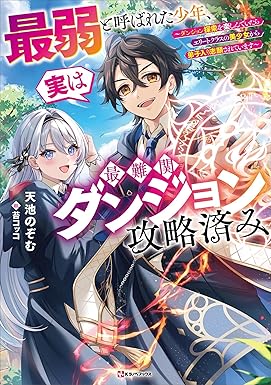第8話 愚者に対する宣告
「る、ルクス君、ほんとに行くの?」
放課後――。
ルクスはコランと一緒に旧校舎の空き教室に向けて歩いていた。
コランが祖父から贈られた腕輪を奪ったCクラスの生徒。
その連中がたむろしているという場所である。
「ああ。アイツらからコランの腕輪を取り返さないとな」
「でも、相手はCクラスの連中で、それに5人もいるんだよ?」
「大丈夫。コランは付いてきてくれるだけでいいから」
「僕の心配じゃないよ! あの人たちがルクス君にまで目をつけたらと思って……!」
己のことではなく、ルクスを案じて必死に声を張り上げるコラン。
その姿を見て、ルクスはきょとんとした顔になる。
「お前、やっぱり良いやつだな」
「え?」
「よっし。なら尚更アイツらから腕輪を取り戻さないとな!」
「えぇ!? 何でそうなるのさ!」
慌てて止めようとしてくるコランだったが、ルクスは構わずに廊下を進んでいく。
そして、目的の空き教室の前まで来ると、ためらうこと無く扉を開け放った。
「どうもー」
「あん?」
中にはコランから聞いていた通り5人の生徒。
その全員が紫紺の襟章を着けている。
リベルタ学園のCクラスというのは、6段階あるクラスの中でも上位に区分される等級である。
中にはAクラス、Bクラス相当の実力を持つにもかかわらず、素行不良などの点からCクラスに落とされた者もいる。
そしてまさに、今ルクスたちの目の前にいる生徒たちがそうだった。
まずルクスが教室の中へと入り、コランがおずおずといった様子で続く。
教室の中は机や椅子が一箇所に固めて積み重ねられており、連中たちのうち何人かはそこに腰掛けてルクスを見下ろしていた。
「テメェ、何の用だ? ってか、昼間の奴じゃねえか」
「コランの腕輪をアンタたちが持ってるんだってな。それ、返してくれないか」
「はぁ?」
ルクスはまず下手に出て尋ねてみる。
しかし、案の定というべきか、Cクラスの連中はルクスの言葉を一笑に付した。
「ハハハ! 馬鹿じゃねえのコイツ。いきなり現れて何を言い出すかと思えば。寝ぼけてんじゃねえのか?」
「寝ぼけてなんかいないさ。さっき授業でたっぷり寝てきたからな」
「……舐めやがって。お前のその襟章、コランと同じFクラスだろ。そんな奴がオレたちに頼み事なんざ百年早えんだよ!」
何が面白いのか、連中はゲラゲラと笑ってルクスを見下す。
最底辺のクラスに所属する無能が、陳腐な仲間意識でも持ったのか知らないがやって来たぞと。
そういう含みを持った嘲笑だった。
「ルクス君……」
「大丈夫。さっきも言っただろ。俺に任せてくれ」
心配そうな視線を向けるコランにルクスは微笑む。
そんなやり取りが癪に障ったらしい。
積み重なった机の一番上に陣取っていた男子生徒が命じる。
恐らく連中のリーダー的存在の生徒なのだろう。
「おい。あの正義のヒーロー気取りの馬鹿を教育してやれ」
「了解」
「念のため結界を張っておけよ。教師や生徒会の奴らにバレても面倒だからな」
リーダー格の生徒が指示を出すと、教室の内部が格子状の線に覆われる。
対象を封じ込めたりするのに用いる、上級魔法である。
その事象から察するに、やはり普通のCクラスとは異なる実力の持ち主たちのようだ。
「へぇ、結界魔法か。アンタら見かけによらず高度な魔法を使えるんだな」
「ハンッ。Fクラスのお前なんかにゃ一生かかっても習得できねえ魔法だろうぜ。これで、この中で何があっても外にはバレねえってわけだ」
小馬鹿にした笑みを浮かべながら、一人の生徒がルクスに歩み寄ってくる。
「そうか、それはありがたいな。手間が省けたよ」
「あ?」
直後――。
ルクスに近づいていた生徒が吹き飛んでいった。
その生徒は結界の壁に激突すると、そのまま床に崩れ落ちる。
「なっ――!?」
吹き飛ばされた生徒は口から泡を吐き沈黙していた。
その様子に、周りにいた連中も驚愕の表情を浮かべてルクスに問いかける。
「こ、これはまさかテメェが……」
「もう一度聞くぞ。腕輪、返してくれないか?」
ルクスは残った4人全員の顔を見渡し、静かに告げた。