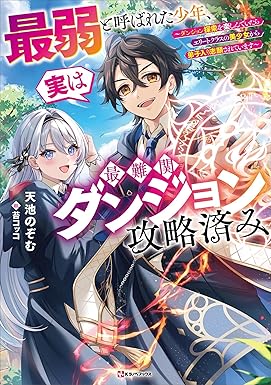第65話 救いたい者
「あれが、木の精霊ドライアド……」
《魔力の湧泉》にて一同が会した後のこと。
シーベルトの呼びかけに応じ、木の精霊ドライアドが皆の前に姿を現していた。
ウンディーネやルーナとはまた異なった少女の姿をしており、可憐だがどこか儚げな印象がある。
恐らくそれは、シーベルトの手の上で力なくうなだれているせいもあっただろう。
(何だか、元気がない感じだな……)
ドライアドの様子を見たルクスはそんな感想を抱いていた。
「ドライアド、すまないね」
「いえ……。先程からルクス様たちのお話を聞いていましたから。事情は理解しています」
ドライアドはか細い声で呟き、ルクスを虚ろな瞳で見つめている。
明らかにノームやウンディーネ、ルーナと違い「弱っている」という様子だった。
「ち、ちょっとドライアド。一体どうしちゃったのよ」
「ウンディーネ様ですか……。お久しぶりです。500年ぶりですね」
「そんな挨拶はいいから。それよりもアンタ、明らかに様子が変よ? 髪だってなんか黒っぽく染まってるし」
ウンディーネの言う通りだった。
木の精霊であるはずのドライアドは緑の髪がところどころが濁り、目は力なく僅かに開かれるばかりだ。
人間であれば大病を患い、床に臥せっているかのような状態である。
何故そんなことになっているのかとウンディーネが問い、それに答えたのはシーベルトだった。
「ドライアドはね、僕が見つけた時からこんな調子だったんだ」
「会長……?」
「ルクス君であれば当然知っているだろう? ダンジョンの階層は10よりもその先があるということ」
「……ええ」
「僕も一応生徒会長だからね。王都の魔法師団にいる人から個人的に依頼を受けていたんだよ。リベルタ学園に存在するダンジョンの中には10よりも深い階層が存在するかもしれない、だからその発見に努めよ、とね」
「……」
「だからダンジョン探索を続けていた。学園の生徒たちが偶然未知の階層を見つけて迷い込んだりすることのないように。まさかFクラスの生徒がそのダンジョンを攻略済みだなんて、思いもしなかったけれど」
「はは……。何だかすみません」
「いやすまない。所属しているクラスで先入観を持っているわけじゃないんだが……」
シーベルトが補足するが、ルクスは構わないという仕草で話の続きを促した。
「ダンジョンの新階層を見つけた時は僕も驚いた。然るべき準備の後に魔法師団や学園の先生たちとも共有して発表しようと思った。けれど……」
「そこでドライアドを見つけてしまった、と」
「ああ、そういうことだね。さすがに精霊も発見したというのはすぐに公表すべき事柄か迷ったし、それに何より、彼女は弱っている様子だった」
シーベルトは手の中でぐったりしているドライアドに視線を落とし、目を細める。
「会長は先程の、姿を消す魔導具を使ってダンジョン探索を?」
「お察しの通りだよ、ロゼッタ君。さすがに新階層の魔物は手強そうだったからね。だから攻略とは呼べないかな。そのせいなのか魔法習得のための魔法陣も反応しなかったし」
「なるほど」
「まあ、普通に攻略しちゃう天才もいるようだけれどね」
「ふふん。ここまで話しちゃっているのでもう隠せませんね、師匠」
「いや、何でそんな嬉しそうなんだ……。そんな褒められても何も出ないぞ」
得意げな笑みを浮かべたロゼッタに嘆息するルクス。
そしてシーベルトに話を元に戻すよう催促した。
「すまない、また脱線してしまったね。とにかく、ドライアドはその場を離れることもできないほどに弱っていた。初めて会った存在だったけれど何とかしてやりたくてね」
「シーベルト様は私に魔力を分け与えてくれたんです。今日も魔力の湧泉に連れてきてもらったりと、迷惑をかけてしまっているのですが……」
「ドライアド。前にも言っただろう? これは僕がしたくてやっていることなんだ。だから君が気に病む必要はないよ」
シーベルトが柔らかく微笑んで、ドライアドは潤んだ瞳を向けていた。
やっぱりいい人じゃないかとルクスが頷く中、今度はノームがシーベルトに問いかける。
「なるほどの。精霊にとって魔力の枯渇は死活問題じゃからのぅ。しかし何故そんなことになったんじゃ?」
「そうよね。普通に過ごしていればたかだか500年ほどで精霊の魔力が失われるなんてことはないはずでしょ? 一体何があったの?」
ウンディーネも続けて問い、ドライアドは弱々しい声で答え始めた。
「私自身、詳しい原因は分かっていないのですが……。少し前から体の一部や髪が黒く濁るようになって、体内の魔力が吸い取られていくような感覚に見舞われました」
「ふむ。病のようなものかのぅ。聞いたことはないが……」
「でも、今は原因究明より解決策がほしいよな。魔力の湧泉も応急処置的なものなんだろ? どうにかして治療してやらないと」
「そうですね、師匠。でも、どうしたら……」
ドライアドの身に生じている異変を何とかしてやりたいと、皆が思案する。
それに対し、声を上げたのはシーベルトだった。
「実は解決方法ならもう分かっているんだ。ただ、その実現が困難でね。だから僕も皆にこの話をした」
「もう分かっている? あ……。もしかして会長がこの前生徒会のみんなに聞いていたのって……」
シーベルトはロゼッタの言葉に頷く。
そして皆を見渡し、真剣な表情で口を開いた。
「そう。『アイリスフローム』という虹色に輝く花。それがあればドライアドを救ってやれる。だから僕はそれを探しているんだ――」