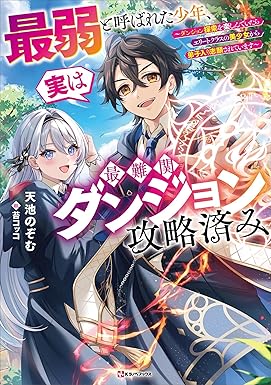第61話 発見と打開策
「ルーナ、どう?」
「こちらの方角で合っています。近いですよ」
《ジンの風穴洞》、第2階層にて。
第1階層にてブラッドガルムを撃退したルクスたちはそのまま下層に到達していた。
追跡対象であるシーベルトが姿を消していたとしても「匂い」が消えたわけではない。
ダンジョンの入り口でドライアドの匂いを察知したように、精霊の気配を探ることができるルーナであれば追跡が可能だ。
ダンジョン内の風が奥から入り口に向かって吹いていることも幸いしたといっていいだろう。
ルーナ曰くシーベルトが近くにいるということで、ルクスたちは慎重な足取りに切り替え、壁伝いに行先を窺いながら進むようになる。
そして――。
「あそこです」
ルーナが指差したそこは開けた空間で、洞窟内にできた泉があった。
不思議と風も止んでいて、どこか神聖な雰囲気を感じる場所だ。
ルクスたちは物陰から様子を窺い、声を潜めながら状況を整理する。
「何もないように見えるけど、いるってこと?」
「ええ。どうやらあそこから動いていないようです」
「泉か……。ダンジョン内にはたまにああいう場所があるよな。あれが目的地だったのかな?」
「でも師匠。普通の泉に見えますが何をしているんでしょうね?」
「さあ? 休憩でもしてるんじゃないか」
「ふむぅ。あれは……」
ルクスの隣でノームが声を上げた。
その視線はじっと泉の方を見据え、何事かを考えているようだ。
「ノームのじっちゃん、何か知ってんの?」
「あれはな、『魔力の湧泉』じゃ」
「魔力の湧泉?」
「うむ。見た目は普通の泉に見えるが、そうではない。儂ら精霊の住処となるダンジョンにはああいう場所が点在しておる」
「どういう場所なんだ?」
「微量の魔力を含む水が溢れている場所じゃ。儂ら精霊が休息する際には浸かることがある。簡単に言うとお主ら人間にとっての温泉のようなものじゃの」
ノームが解説すると、その横でウンディーネがうっとりとした表情を浮かべる。
「あれって浸かってると気持ちいいのよねぇ。疲れたときにはよく効くわ」
「そうでしょうか。私は月光浴の方が好きですね」
「まあ、ルーナにとってはそうかもしれないけどね。ちなみに私の住処にはたくさんあったわよ」
「何故そこで得意げな顔をするのです」
何だか精霊らしい会話だなと思いながらルクスは頭を掻く。
そして横道に逸れた話を戻すべく、ノームに再び問いかけた。
「要は精霊たちが療養するための場所ってことだよな? さっき入り口でルーナはドライアドが弱っているかもって話してたけど、もしかして……」
「うむ。ドライアドの身に何かしらのトラブルが生じているのかもしれん」
「じゃあシーベルト会長はその手助けをしているってことか?」
「そう決めつけるのは早計ですよ、ルクス」
「む……」
ルクスの推測に待ったをかけたのはルーナだ。
ルーナはルクスの目の前にずいっと顔を出して、無表情のまま語りかける。
「シーベルトという人間はどうやら魔導具の知識や扱いに長けているようです。姿を隠すという代物を所持しているくらいですからね。何かしらの方法でドライアドを捕縛し、使役している可能性も捨てきれません」
「まあ、確かに……」
「ドライアドは木の精霊ですからね。あらゆる植物を召喚する能力を持っています。たとえそれが魔界の植物だとしても、です」
「……」
《白水晶の遺跡》で起こった、黒の瘴気の発生。
それがイビルローズという魔界の植物が原因で起こったことは、ここにいる全員が知っている。
黒の瘴気発生事件の裏側にシーベルトが絡んでいた可能性もあると、ルーナが言っているのはつまりそういうことだ。
ルクスだけではなく、ロゼッタも目を伏せて考え込む。
シーベルトと生徒会の仕事で関わってきたロゼッタからすればそのようなことを行う人物だとも思えないのだが、確証がないもまた事実。
もしシーベルトが事件の黒幕という立ち位置なら、ルクスたちが追っていることはもちろん、精霊たちのことも明かすべきではないだろう。
「……」
どうすべきかが見つからないまま皆が沈黙する中、ルーナが泉の方へと視線を向けた。
「動きました。どうやら入り口の方へと戻るようです」
その声でルクスたちは岩陰の奥へと身を潜める。
「で、どうするの? このまま尾行を続けるしかないってこと?」
「そうですね……。今はそれしか……」
ロゼッタがウンディーネの問いに答える傍ら、ルクスは思考を巡らせていた。
そして何かを思いついたのか、顔を上げて皆を見渡す。
「よし、俺に任せてくれ。いい考えがある」
ルクスはそう言うと、ニカッと笑いながら親指を突き立ててみせた。