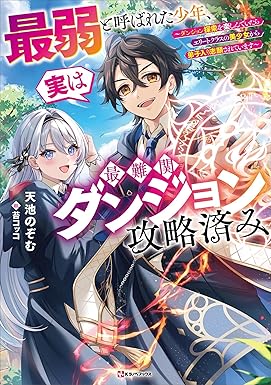第53話 鍵を握る人物
「あ、カップ3つしかないや。今度用意しとかないとな」
ノームとウンディーネが帰還し、ルーナと再会した後のこと。
ルクスはふわふわと浮いている精霊たちの前、テーブルの上に紅茶を注いだカップを置いた。
カップは体の小さな精霊たちにとっては大きく、それでも何とか持ち上げることはできるようだ。
まず初めにルーナが口を付け、ウンディーネもそれに続く。
ルクスはその様子を壁にもたれ掛かりながら眺めていた。
――土の精霊ノームに水の精霊ウンディーネ、そして月の精霊ルーナと。
一般的には存在するかどうかさえ確かではないとされる精霊が、三人もルクスの家にいるというのは現実味のない光景である。
「それにしても驚いたわ。ルクスの家に戻ったらルーナがいるんだもん。満月の夜でもないのに地上に出てきたの?」
「ええ。ちょっと色々とありまして」
ウンディーネの問いにルーナが端的に答える。
それに対してルクスが補足を入れ、昨日あった出来事――クラスメイトであるシエスタにルーナが同行しており、黒の瘴気発生事件についても共有したことについて話していった。
「ほっほっほ、そういうことじゃったか。しかし、儂ら精霊が地上でこうして会うことになろうとはのぅ」
「ほんとね。ドライアドも住処にいなかったし。もうみんな地上にいるんじゃないの?」
ウンディーネが呆れたように言って紅茶を啜る。
その言葉にルクスは疑問符を浮かべた。
「住処にいなかった? じゃあドライアドには会えなかったのか?」
「そうね。残念ながら」
ノームとウンディーネが調査していたのはドライアドの行方。
先日、《白水晶の遺跡》で発生した黒の瘴気についてイビルローズという植物が関わっていたことから、木の精霊であるドライアドに会えば何かが分かるかもしれないと思ってのことだった。
しかし、ノームとウンディーネの話によればドライアドの姿は見つけることができなかったという。
「となるとドライアドの一件は空振り、か……。ウンディーネ、すぐに見つかるから任せておけって言ってなかったっけ?」
「し、仕方ないじゃない。あの子、大人しい性格だし、住処から外には出てないと思ったんだもん……」
「まあ、確かにウンディーネがそう考えるのも自然なことですね。しかし、どこに行ったのか気になるところです。ノーム、何か見当はつきませんか?」
「うむ、それなんじゃがの」
ノームは懐からあるものを取り出し、卓の上に置いた。
それは小さなアクセサリーで、金色の輝きを放っている。
「え……? それ、リベルタ学園の襟章じゃん」
「そうじゃ。ルクスが付けているものの色違いじゃな」
「襟章の色は金……。つまり、Aクラスの生徒のってことか。ノームのじっちゃん、どこでこんなものを?」
「ドライアドの住処に落ちてたんじゃ」
ノームが答えたその言葉に、ルクスは目を見開く。
ルーナも表情こそ変わらなかったものの、僅かに口を開いて驚いている様子だった。
「えっと……。ってことは誰かが《ドライアドの地下樹林》の第200階層に行ったってこと?」
「そうなるのぅ。しかもルクス、お主と同じ学園の生徒がな」
「マジか……」
「そこでじゃ、ルクスよ。お主に確認したいんじゃが、襟章というのはいくつも持っているものなのか?」
ノームの質問の意図は明白だった。
ドライアドの不在とその住処に落ちていた襟章。
それらの事情から察するに、襟章を落とした人物がドライアドと接点を持ったことが濃厚であり、その人物が今回の一件について鍵を握っている可能性が高い。
であれば、襟章を失くしたAクラスの生徒という方向で追っていけば何かしらの手がかりが掴めるのではないかということだ。
「いや、襟章はクラス分けとか転入があった際に貰える一つだけだな。失くした場合は生徒会に再発行の手続きをすることになってるんだけど」
「それなら、ロゼッタって言ったっけ? あの銀髪の可愛い娘。あの娘に聞けば分かるんじゃない? 生徒会の人間なんでしょ?」
「そう、だな……。確かにロゼッタに確認すれば分かるかもしれない」
「なら、次にやるべきことは決まりね。その襟章を失くした人物を突き止めて問いただしましょ。そうすればドライアドの行方も分かるでしょうし、もしかしたら黒の瘴気発生についても何か関わっているかもしれないわ!」
「私もそれが良いと思います。ただ……」
ウンディーネの声にルーナが賛同する。
が、ルーナは神妙な面持ちで何かを考え込んでいるようだった。
「どしたの、ルーナ? そんな難しい顔しちゃって」
「いえ……。ちょっと気になったのですが、襟章は第200階層に落ちていたのですよね? その襟章の持ち主は、そこまで無事に辿り着ける実力の持ち主、ということになるのかな、と……」
「確かに、儂もそこが気になっておった。ルクス以外にそういう人物がおるのかとな」
ノームが言って一同は沈黙する。
ルクスもそれから考えてみるが、その答えは出そうになかった。