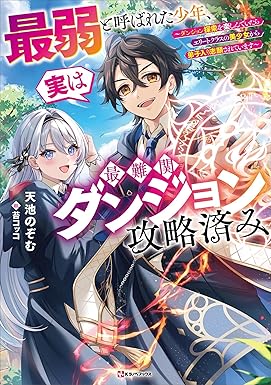第5話 【SIDE:ロゼッタ】弟子の想い
「《氷針の矢雨》――!」
指定中級ダンジョン、《サラマンドラの溶岩窟》。
その5階層にて。
炎を纏った蛇型の魔物、フレイムナーガに対し、ロゼッタの放った氷の刃が突き刺さる。
――フシュッ!?
大量の氷針に貫かれたフレイムナーガは短く悲鳴を上げ、バタバタとのたうち回った後に動かなくなった。
「「「おぉー!」」」
その様子を見ていたリベルタ学園の生徒たちが一様に感嘆の声を上げ、ロゼッタに尊敬の眼差しを向けている。
AクラスとBクラスの合同実戦授業にて、Bクラスの生徒にお手本を見せてほしいとせがまれたロゼッタが繰り広げた戦闘だった。
「ふむ。流石ですねロゼッタさん。あのフレイムナーガを一撃とは。いやはや見事です」
「ありがとうございます」
引率として同行していたBクラスの担任教師に称賛されたが、ロゼッタは微笑を浮かべるだけに留めた。
「さて、今の戦い方は見ましたか? 貴方たちもロゼッタさんの戦い方を参考にするように。それでは、グループを組んでこのフロアの魔物と戦闘してみましょう」
Bクラスの担任教師が自分のクラスの生徒に向けて言って、それを受けた生徒たちは散り散りになっていく。
その様子を見ながらロゼッタは一つ息をつく。
(……やっぱりまだまだですね。師匠ならあの程度の敵は近寄らせることもなく倒すでしょう。まあ、Bクラスの人たちのお役に立てたのであれば良かったですが)
ロゼッタは自分の手を見つめながら、ルクスのことに思いを馳せていた。
先日同行させてもらった《ノームの洞窟》での戦闘も凄まじいものだったと、ロゼッタはうっとりした表情で回想する。
197階層という、非常識な階層に出てくる強靭な魔物たちを、一撃どころかまとめて屠る広範囲魔法。
そして自身の十倍以上はあろうかという大型魔物をあっさりと倒してしまう大魔法。などなど。
魔法そのものも凄いが、ルクスの戦闘には本人も言っていたように「慣れ」がある。
ロゼッタからしてみればそれは余裕と言い換えても良いのだが。
かといってそれに慢心するでもなく、力に酔いしれるでもなく、ルクスは自然な振る舞いをしているのだ。
その飾らない姿を見て、ロゼッタは人間的にもルクスのことを尊敬していた。
(師匠はきっと、純粋なんでしょうね。この前もダンジョン探索を全力で楽しんでいる様子でしたし)
――見ろロゼッタ。珍しい鉱石があったぞ。綺麗だなぁ。持って帰って部屋に飾ろうかな。
――うお、何だあの魔物。岩がそのまま動いているみたいだ。
――今の戦闘、中々上手く立ち回れたな。良いタイミングで魔法が撃てたぞ。
そんなルクスの姿を思い出し、ロゼッタは笑みをこぼす。
(まあ、二人きりだったんですから、ちょっとくらい意識してほしかったですけど……)
そんな詮無いことに思考が及び、今度は少し膨れ面になるロゼッタ。
と、そこへ歩み寄ってくる女性がいた。
「ロゼッタ。お疲れ様」
リベルタ学園Aクラスの担任教師、そしてロゼッタの姉でもあるエレイン・シトラスだった。
「あ、お姉ちゃん」
「こら。学園ではエレイン先生、でしょう」
「いいじゃない。今は周りに誰もいないんだし。あ、ありがと」
ロゼッタはそう言って、エレインから差し出された革袋を受け取る。
中に入っていた水に口を付けて一息。
火属性の魔物が多く出現するダンジョンと言うだけあって暑かったため、ありがたいなとロゼッタはエレインを見やる。
「ころころと表情を変えて、何を考えていたの?」
「え……。み、見てたの?」
「ふふ。なかなか楽しかったわ」
「むぅ……」
姉にからかわれてロゼッタはぶすっとした表情を浮かべた。
「それで? もしかして前に言っていた師匠さんのこと?」
「……何で分かるかなぁ」
「お姉ちゃんですから。で? そろそろ誰なのか教えてくれても?」
「それはダメ」
「ヒントは?」
「それもダメ」
「ええー。いいじゃない。少しくらい教えてくれても」
「ダメなものはダメ。たとえお姉ちゃんでも」
ロゼッタはきっぱりと言って、エレインの問いかけに答えることを拒否する。
ロゼッタが師と仰ぐルクスは、どうやら人からの注目を浴びることを嫌う傾向にあるらしい。
嫌うというよりも、ガラじゃないと本人は言うのだろうが。
前に《ノームの洞窟》で話した感じでは、クラスが昇級したりすると面倒だし、今のFクラスで自由気ままにダンジョン攻略を楽しめた方が良いとのこと。
ロゼッタとしてはいつか師匠の凄さが知れ渡れば良いのにと思っていたが、こういう裏で伝えるのは違うだろうとも思っていた。
「ま、いいけどね」
エレインはそう言って、ロゼッタの傍を離れようとする。
「でも、たぶん男の人なんじゃないかなぁって思うのよね。ロゼッタが師匠って呼ぶ人」
「え……?」
「だって、さっきのロゼッタ。恋に悩む乙女みたいな顔になってたわよ」
言い残して、エレインは他の生徒たちの方へと歩いていく。
その言葉にロゼッタは自分の体温が上昇するのを感じていた。
それはきっと、ダンジョンの暑さのせいではないだろうと自覚しながら――。