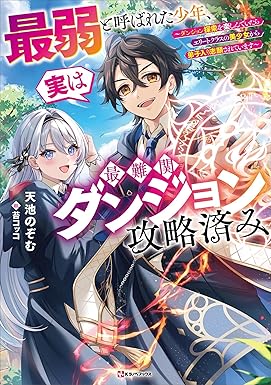第46話 【SIDE:ノーム&ウンディーネ】発見
「ふぅ……。ここが第200階層ね」
木の精霊ダンジョン《ドライアドの地下樹林》、その最下層にて。
精霊の住処とされるその場所で、ノームとウンディーネは最奥部を目指し進んでいた。
「この場所は相変わらず樹が多くて入り組んでるわね。さっきはでっかい樹のドラゴンなんていたし」
「ほっほ、ぼやくなウンディーネよ。姿を消していれば魔物との交戦は回避できるしの」
「まあ、そうなんだけどね」
ウンディーネが鬱蒼と茂ったダンジョン内の構造に悪態をついたところをノームが嗜める
そんなやり取りを続け、二人は奥へと進んでいた。
「それにしても、よくこんな場所を人間が踏破できたわね」
「ん? ああ、ルクスのことか」
「そ。正確にはこの場所じゃないでしょうけど、200階層ともなれば厄介な魔物がいるでしょう? それをルクスは攻略したのよね。大したものだわ」
「ふーむ」
「どうしたの?」
「いや、あんなにつっけんどんだったお主が素直に人のことを褒めるとは、500年という月日は長いもんじゃと思ってのぅ」
「しばくわよ」
ウンディーネがジトッとした目を向けるとノームはおどけた表情を浮かべて誤魔化す。
そのやり取りは二人の関係性を表しているようで、その場にルクスがいたらきっと感慨深く思っていたことだろう。
ウンディーネは短く嘆息し、そして語りだす。
「なんかね、あの子は普通の人間っぽくないのよ」
「ほう? 詳しく聞きたいのぅ」
「学園の生徒たちを見ていてね、特に思うわけよ。多くの人間は自分がどんな魔法を扱えるのか、どこのダンジョンをどれくらい深くまで攻略できるのかってところに重きをおいているってね」
「ふむ」
「それはある意味、物差しのようなものかもしれないわ。そして、ほとんどの人間はその物差しで他人も計ろうとする」
「ルクスはそうではないと?」
ノームの言葉にウンディーネはコクリと頷いた。
「自分が傑出した実力を持っているってのに、あの子はそれをひけらかしたりする素振りが微塵もない。私たち精霊に会ったときも、素直に喜んでいるようだった」
「そうじゃの……。ルクスにはそういうところがある。純粋、とも言えるかの」
「人間には珍しく、ね。あなたが興味を持ったのも分かる気がするわ、ノーム」
ウンディーネはそう言ってノームの方へと視線を送る。
それを受けたノームは、白い髭の奥で嬉しそうに口の端を上げた。
「この前は挨拶だけになっちゃったからね。色々と話をしてみたいものだわ」
「くっくっく。お主もぞっこんじゃの」
「べ、別にぞっこんじゃないわ! 単に私はあの子に興味があるだけよ!」
「……何というかウンディーネよ。お主もある意味素直な性格しとると思うぞ」
そんな賑やかな会話を交わしながら、ノームとウンディーネは奥へと進んでいった。
そしてまもなく最奥部に到達するだろうかという頃合いになって、ウンディーネがぽつりと漏らす。
「ま、何にしても今はドライアドを見つけることね」
「そうじゃの。首尾よく見つけられるといいが……」
ノームは呟き、白い髭を擦りながら呟く。
どこか難しい顔を浮かべていて、その心中をウンディーネは察していた。
「見つけるのもそうだけど、話がちゃんとできる状態だといいわね」
「……そうじゃの」
それ以上二人は言葉には表さなかったが考えは一緒だった。
魔界の植物、イビルローズの出現位置をノームが調査し、精霊の痕跡を感じ取ったことについては既にウンディーネとも共有済みである。
では、その精霊とは誰なのか――?
そこに痕跡があったからといって黒の瘴気発生を引き起こした者であるとは限らない。
しかし、それがドライアドだという可能性もあると、ノームとウンディーネは考えていた。
そしてその場合、ドライアドの真意を聞き出さなくてはならないのだ。
それは二人にとって、気が重くなることだった。
「さて、到着ね」
ウンディーネが声を発し、行く手には巨大な扉が現れる。
ノームがいた場所と同じ、精霊の住処とされるダンジョンの最奥部だ。
ウンディーネがそっと手をかざすと、その扉は自然と開かれた。
ノームとウンディーネは互いに頷き合い、そして中へと進んでいく。
そして――。
「誰もいない、か……」
結果は拍子抜けしたものだった。
ノームとウンディーネは気配を探ってみるが、精霊がいる様子はない。
ウンディーネの場合がそうだったように、ドライアドもまたダンジョンの外へと出ているのだろうかと、自然な考えが浮かぶ。
「はぁ……。ここまで来て空振りか。仕方ないわね、一旦戻るとしましょうか」
「そうじゃのぅ」
二人揃って嘆息し、扉奥の部屋を後にしようとする。
と、その時だった。
「ん……?」
ノームが地面に落ちている「あるもの」を見つけ、ふわりと着地する。
そこにあったのは、小さなアクセサリーのようだった。
「これは、どこかで見たことが……」
ノームは呟き、そして思い当たる。
確か、ルクスをはじめ、リベルタ学園の生徒がこのようなものを襟に付けていたと。
ノームはそこに落ちていたものを拾い上げ、まじまじと見つめる。
「金の、襟章……」
それは、リベルタ学園Aクラスに所属することを示す装飾品だった。