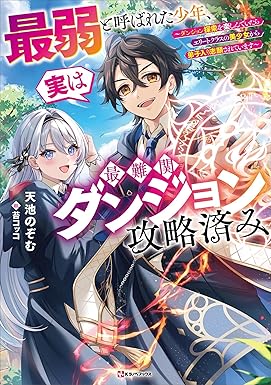第41話 露見
【砂の回廊:第1階層】
「や、やぁっ!」
シエスタが鋭い風の刃を放つと、目の前にいた蛇型の魔物が両断される。
ダンジョン攻略実践授業が始まってから少しして。
ルクスたちの班は順調に魔物を討伐していった。
魔物と交戦していたシエスタが額に浮かんだ汗を拭ってルクスたちの方を向く。
「ふぅ……。何とか倒せました」
「お疲れ様、シエスタ。戦う前は自信ないって言ってたけど、見事なもんじゃないか」
「うんうん。あの素早い蛇の魔物を一発目から捉えるなんて凄いと思うよ、シエスタさん」
「いえいえ、そんな……」
ルクスとコランに称賛を向けられ、照れるシエスタ。
が、すぐに視線を落とし、シエスタは曇った表情を浮かべた。
「ありがとうございます。でも、私の魔法なんて姉さんに比べればまだまだで……」
「お姉さん?」
「はい。実は、私の姉は王都の魔法師団に所属しているんです」
「へぇ、魔法師団か。それは凄いな」
ルクスは素直に感心しつつ納得する。
話した時の印象から自己肯定感が低い子だなと思っていたが、どうやらそれにはシエスタの姉とやらが関係しているらしい。
王都の魔法師団とは、謂わば魔法のエキスパートを集めた兵団である。
属する者は全てが一騎当千の強さを誇るとされる化け物揃いの集団。
リベルタ学園を卒業した後は魔法師団に属することを夢見るという生徒たちも多い。
そんな組織に、シエスタは姉がいるという。
恐らくシエスタは、その姉と学園の中でも最底辺のクラスに所属する自身とを比較して劣等感を抱いているのだろうとルクスは思い至る。
「姉さんは本当に凄くて。それに比べて私は……」
そう呟いたシエスタに対し、しかしルクスは真逆の言葉を口にする。
「でも、シエスタだって立派なもんだと思うぞ。さっきの魔法だって凄く正確な魔法だったし」
「え……? あ、ありがとうございます」
「肩書きでその人の価値が決まるわけじゃないしなぁ。それに、ダンジョンを攻略していけば魔法は新しく習得できるんだ。そしたら今より強くなれるさ。だったら、頑張ろうぜ」
「は、はい……」
それは慰めの意図や同情から発された言葉ではなく、ルクスにとっては素直な感想である。
だからこそ届いたのだろう。
シエスタは少し意外なことを言われたというように驚いた後、どこか安堵しているようだった。
「ルクスくん……。その、ありがとうございます」
「ん?」
「ああ、いえ……。私、姉さんと比べられることが多くて。だから、ずっと焦ってたっていうか」
「なんだ、そんなことか。まあ、そういうのは大変そうだよな。俺にはよく分からないけど」
そんなやり取りを見て、それまで黙っていたコランが笑みを浮かべる。
「ルクス君のそういうところ、僕は凄く良いところだと思うな」
「ん?」
「ううん。分からないようならいいや。とにかく、今はこのダンジョンを攻略しないとね」
コランがそう言って、ルクスは疑問が解消されないままにダンジョン攻略を続けることになった。
***
「それじゃあ今日はこれで終わりだ。これからは授業でも実戦が増えてくからなー。今日見つけた課題を各々復習しておくように」
特に目立った問題もなく、Fクラスの生徒たちはその日のダンジョン攻略実践授業を終える。
担任教師のオリオールはダンジョンの入り口に集まっていた生徒たちを見回すと、手を叩いて宣言した。
「それじゃ、解散」
その言葉で生徒たちは散り散りになっていく。
実践で魔法が使えたことに興奮している者や、魔物に驚いてしまって上手く対処ができなかったと嘆く者。
様々な反応を見せつつ歩く生徒たちを見送り、オリオールはその中で一人の生徒を注視する。
その視線の先にはルクスの背中があった。
(結局、何かずば抜けて凄いって感じはしなかったな。《白水晶の遺跡》の一件ではロゼッタ副会長と一緒にダンジョンに潜っていったって聞いたから、何か実力を隠してるんじゃないかと思ったが……。やっぱり俺の考えすぎかな)
そうしてどこか解せないものを感じつつも、オリオールは短く嘆息した。
***
「それじゃ、俺はこっちだから」
「うん。また明日学校でね、ルクス君」
「あの、今日はありがとうございました……」
学園の宿舎に向かうコランやシエスタと別れ、手を振るルクス。
そして、家に向かう道を独り歩く。
(さて、ノームのじっちゃんやウンディーネは戻ってきてるかな。もし戻ってなかったら一旦家に寄ってから日課のダンジョン探索といきますか)
そんなことを考えながら歩いていると、ルクスの背中に声がかけられる。
「あ、あのっ!」
「ん……?」
ルクスが振り返ると、そこに立っていたのは先程別れたはずのシエスタだった。
「どうした、シエスタ? 何かダンジョンに忘れものか? それならオリオール先生に言って付き添ってもらうか?」
「いえ、そうではなくて……。その……」
俯きがちになりながら、歯切れ悪く答えるシエスタ。
どうやら何かをためらっているようだが何だろうかと、ルクスは小首を傾げる。
「ええと、こんなこと聞くのは失礼かもしれないんですが……」
そう前置きして、シエスタは意を決したかのように自分のスカートを掴む。
そして――。
「あの、どうしてルクスくんは魔法使う時、手加減しているんですか?」
「え……?」
シエスタのエメラルドの瞳がルクスを見つめる。
表情は至って真剣だった。
「俺が、手加減してる?」
「はい。さっきの授業で、ルクスくんが魔法を撃つところを何度か見ました。そのどれもが加減して使っているように見えて。それで、その、何でなのかなって……」
言葉は小さくなっていったが、発言の内容には明確な自信があるようだった。
シエスタは視線を逸らさず、じっとルクスの言葉を待っている。
「お、俺が手加減してるって? はは……、そんなことはないよ。俺は初級魔法しか使えないFクラスの生徒で……」
ルクスが咄嗟にそう返した時だった。
ルクスとシエスタの間、その空中から鈴のなるような声が響く。
「とぼけても無駄ですよ、人間」
「は?」
突如聞こえたその声に、ルクスは素っ頓狂な声を上げる。
一方でシエスタは驚いた素振りすら見せない。
そして、声がした箇所に向けて集束するように風が湧き起こった。
(これは、まさか……)
覚えのあるその感覚にルクスは思わず身構える。
そこに姿を現したのはやはりというべきか、妖精のように可愛らしい小さな少女だった。
「初めまして。月の精霊、ルーナと申します。先程はシエスタがお世話になりました」