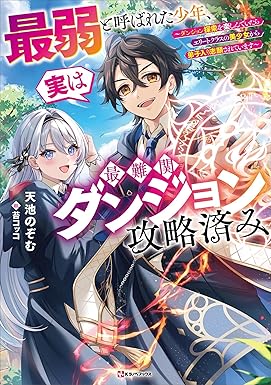第39話 その魔法、習得済み
初級ダンジョン《砂の回廊》入り口にて。
ルクスたちの班に合流したのは青髪の少女、シエスタだった。
「今日はよろしくな。俺はルクスだ」
「あ、うん。もちろん知って、ます……」
ルクスがニカッと笑って手を差し出すと、シエスタはおずおずとその手を握る。
シエスタ・ミクシャータ――。
自分と同じFクラスの生徒だが、いまいちどんな子か分かってないんだよなと、ルクスはコランと握手を交わすシエスタを見ながら考えていた。
今日の午前の授業でもあったように噛みながら教本を読んだり、普段の行動も慌ただしかったりと、影が薄いというわけではない。
しかし、それだけだ。
ルクス自身、シエスタというこの女子生徒と何か特別な接点があるわけではなく、もしかしたらちゃんと会話するのはこれが初めてかもなと、顎に手をやりながら記憶を辿っていた。
「えっと。私、お二人に迷惑かけちゃうかもしれなくて。その……ごめんなさいっ!」
ルクスは唐突に謝られた。
普段の授業で慌てていることからも何となく察しはついていたが、どうやらこのシエスタという少女はかなり自己肯定感が低めの性格らしい。
「いやいや、まだ何も始まってないぞ。せっかく授業でダンジョン攻略できるんだから、気楽に楽しもうぜ」
「は、はい……」
ルクスに声をかけられたが、シエスタはまだ緊張気味のようだ。
自分の髪をペタペタと落ち着きなく触りながら、上目遣いにルクスのことを見上げている。
「おーし、そろそろ班メンバーの確認も済んだかー? それじゃ、《砂の回廊》ダンジョン攻略実戦授業、始めんぞー」
担任教師であるオリオールの棒読み感ある声が響き、Fクラスの生徒たちはぞろぞろとダンジョンの内部へと入っていった。
***
「よっ」
ダンジョンに入ってすぐ。
現れた爬虫類系の魔物に対し、オリオールが見本として炎の槍を放つ。
その魔法は勢いよく突き刺さり、魔物の体を焼き尽くしていった。
その様子を見た数人の生徒が歓声を上げる。
「おおー。オリオール先生って強かったんですね」
「あのな、俺は仮にも学園の教師だっつの。ある程度魔法が使えなきゃお前らを引率することもできないんだぞ」
「でも、いつもの姿からは想像できないよなぁ?」
「だな。普段はやる気のない中年のおじさんって感じだし」
「お前ら……」
生徒たちに弄られるオリオールを遠巻きに見ながら、ルクスは素直に感心する。
(あの速度で魔物の急所に命中させるあたり、凄い正確性だ。やっぱり学園の先生ってのは強いんだな。普段の姿から想像できないのは俺も一緒だけど)
そうやって微妙に失礼な感慨を抱きながら、ルクスはオリオールの戦闘を分析していた。
「せんせぇー。今のは何て魔法なんですか?」
「ん? ああ。今のは火属性の《炎の烈槍》って魔法だな。《サラマンドラの溶岩窟》の第3階層を攻略すれば習得可能だ。けっこう便利な魔法だから使えると重宝するぞ」
「そんなこと言われてもなぁ。《サラマンドラの溶岩窟》って八大精霊ダンジョンでしょ? そんな所に行けるの、AとかBクラスの奴らじゃないんですか?」
「まあそう言うな。お前らだって腕を磨けばいつか習得できるはずさ。それに、火属性魔法にはまだまだ上があるからな」
「上って、どんなのがあるんですか?」
近くにいた生徒が手を挙げ、オリオールに対して質問する。
オリオールは「教本に書いてあるんだからちゃんと読めよ」と前置きしながらも、解説し始めた。
「より上級なものだと、植物系や氷雪系の魔物に有効な防御方法として《灼熱の炎壁》とかがあるな。触れたものを溶かしちゃうような魔法だ」
「何それ、すげー」
「カッコよさそー」
「あと、《業火の抱擁》っていう、全てを焼き尽くす火柱を召喚する魔法とかな。まあ、これは《サラマンドラの溶岩窟》を第10層まで攻略しないと習得できない魔法だし、俺の周りの先生でも使える人いないけど」
「最難関ダンジョンの最下層じゃん」
「そんなん習得したら英雄だろ」
「八大精霊ダンジョンなんて、第1階層でも無理だわ」
オリオールの解説に対し、生徒たちは口々に言葉を返す。
それはもっともな反応だったが、それを聞いたルクスは自分の頬をポリポリと掻いていた。
「ルクスくん、どうかしましたか?」
「いや……」
隣にいたシエスタが覗き込んできて怪訝な表情を浮かべている。
先程オリオールが語った全ての魔法をルクスは習得済みなのだが、それは言えるはずがなかった。