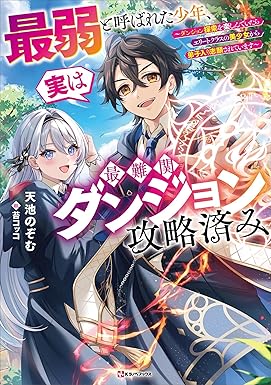第35話 人間と精霊たちの夜
「師匠、まだ起きてますか?」
「ロゼッタも起きてたのか」
ウンディーネとの会話が終わってからしばらく経ち。
そろそろ眠る時間ということでルクスとロゼッタは横になっていた。
もちろんベッドで二人一緒に、というわけではない。
ルクスはロゼッタに、ロゼッタはルクスに。
お互いが相手にベッドを使うよう押し問答が続いたのだが、結局ルクスの「女の子を床に寝かすわけにはいかない」という言葉に折れて、ロゼッタの方がベッドを頂戴することになっていた。
「何だ? やっぱり自分が床にって話なら聞かないぞ」
「ああいえ、そうではないんですが。ウンディーネさんとノームさん、あのあと外に出て行っちゃいましたけど何の話してるのかなって」
「会うのが500年振りらしいからなぁ。積もる話もたくさんあるんだろうな」
ロゼッタはふと窓の外へと視線を向ける。
そこには半分の月が浮かんでおり、どこからか虫の鳴く声が聞こえてくる。
ルクスの家は大樹の根本をくり抜いたような構造になっていることもあり、自然とも近いのだろう。
ロゼッタはそんなことを考えながら不思議な心地よさを感じていた。
「それにしても、この大地が精霊のつくったものだったなんてなぁ。あんまり実感湧かないや」
「そうですね。ノームさんのあのお話はびっくりでした」
「しかもダンジョンの更に深く、別の空間があるとはなぁ。どんだけ壮大な話だよって感じだな」
「はは……。そもそも精霊さんとああやって話ができること自体とんでもないことなんですけどね。本当、師匠の側にいると驚きの連続です」
ロゼッタはそう言って、ごろんと体を横に向ける。
視線の先には頭の後ろで腕を組んだルクスの姿が映り、別に一緒に寝ているわけでもないのに、それだけでロゼッタは妙な胸の高鳴りを覚えた。
(何だか師匠と一緒に横になっているの、変な感じがしますね……。もう少し起きていたら寝顔も見れちゃったりするんでしょうか)
「そういえばさ――」
「ふぇっ!?」
ルクスが自分の方を向いて、ロゼッタは素っ頓狂な声を漏らす。
思考を読み取られたわけではもちろんない。
ただ、突然目が合ったことでロゼッタの心臓は早鐘を打っていた。
「な、何だ?」
「い、いえ、何でもないです……」
怪訝な顔を向けてくるルクスに、ロゼッタは消え入りそうな声で返す。
そんなロゼッタの様子を訝しがりながらも、ルクスは先程の言葉の続きを発した。
「あの黒の瘴気、精霊の仕業だとしてもそうでないとしても、何であんなものを発生させてたんだろうな?」
「確かにそうですね。あの事件は偶発的なものではないとノームさんは仰っていましたが、仮に誰かが引き起こしたものだとして、どんな狙いがあるのか……」
「だよなぁ。ま、ノームのじっちゃんが色々と調べてきた感じでは、今のところ他のダンジョンに異変は見られないから心配いらないってことだったけど」
「まずは他の精霊さんたちに話を聞くことが先決ですね」
「他の精霊、となるとやっぱりウンディーネが言っていたように、木の精霊ドライアドか」
「ウンディーネさんの話では、気弱で大人しい精霊らしいからだから、いきなり人間が会いに行かない方が良いって言っていましたよね。まずは自分たちが探すからそれまで待っていろと」
「ああ。俺たちは普通に学園生活を送ってて良いってことだったけど、それも落ち着かないよなぁ。何かできることがあったら協力したいところだけど」
ルクスが溜息交じりにそう呟くと、ロゼッタは微かに笑う。
「ふふ。心配なんですね、精霊さんたちのこと」
「ん? ああ……。自分たちの仲間が事件に関わっているかもしれないって、あんまりいい気持ちはしないだろうからなぁ」
「前に話を聞いたコランさん、でしたっけ? その時もそうでしたけど、師匠ってほんとお人好しですよね」
「何でそうなる?」
「だって、見て見ぬふりをすることもできるはずなのに、師匠はそんなこと考えもしないじゃないですか。師匠のそういうところ、私は素敵だと思いますよ」
「……」
「それに、私の時も――」
ロゼッタはそこまで言って、続きを口にはしなかった。
この場の雰囲気で言ってしまうと何だかとても恥ずかしいことを口にしてしまいそうだったからだ。
「さ、さて、そろそろ寝ましょうか。明日も学校がありますからね」
「……? ああ、そうだな」
ルクスはまたロゼッタの様子を訝しがりながらも、その声に従って寝ることにした。
「それじゃ、おやすみロゼッタ」
「はい、おやすみなさい」
言葉を交わし、ルクスとロゼッタは互いに布団を被る。
そうして、しばし時間が経ち……。
(失敗しました……。よく考えたら、ベッドで一緒に寝ようと提案すれば良かったのでは?)
そんな邪な考えに思い当たったロゼッタがベッドの上で悶えていたが、全ては手遅れだった。
***
「まったく、珍しいこともあるものね。あなたが人間に付いているだなんて」
月明かりの下、ルクスの家の外でウンディーネがふわふわと浮いている。
その隣にはノームの姿があり、好好爺な笑みを浮かべていた。
「ほっほっほ。なかなかに面白そうな奴だと思ってのぅ」
「ルクスって言ったっけ、あの子。確かにあなたが好きそうな性格よね。サラマンドラやジンとも合いそうな気がするわ。ルーナあたりは……、うん。絶対に引かれるわね」
「それは儂もそう思う」
ノームはウンディーネの言葉に相槌を打ち、白髭を擦る。
自分の住処である洞窟の200階層までやって来たことも驚きだったが、ノームとしてはルクスの竹を割ったような性格と姿勢に興味を覚えていた。
「それにしても、黒の瘴気か……。何だか不穏なものを感じるわね」
「じゃのぅ。しかも、その出現位置から精霊の痕跡が見つかるとは……」
「ま、考えても仕方ないんじゃない? 今はそれよりもドライアドを探さないと。まったく、余計なことに首を突っ込んじゃったかもしれないわ」
「ほっほ。そう言っても何だかんだ協力してくれるんじゃから、面倒見の良さは相変わらずじゃの」
「うっさい」
ぷいっと顔を背けてふてくされるウンディーネの態度が面白くて、ノームはまた笑みを浮かべる。
しかし、すぐに真剣な表情になると、低い声で呟いた。
「とにかく、この地上にまで黒の瘴気を蔓延させるわけにはいかんしの。誰の仕業か分からんが、そんなことは絶対にさせん」
「……そうね」
ノームの声に応じ、ウンディーネもまた真剣な表情で頷く。
そして、半分の月明かりの下でそれぞれの夜は更けていくのだった。