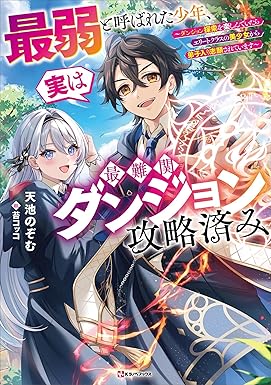第34話 水の精霊ウンディーネ
「やはりお主じゃったか」
「久しぶりね、ノーム。500年ぶりくらいかしら?」
突如としてルクスたちの前に現れたのは、水の精霊――ウンディーネだった。
ウンディーネはノームと同じく宙を漂いながら微笑を浮かべている。
その出で立ちはまさしく水の精霊といったところか。
青髪と調和した装飾豊かな衣服と、頭にちょこんと乗せた魔女帽子が印象的だ。
空中でくるりと一回転したウンディーネを見たルクスは、当然というべき反応を見せた。
「おお、精霊だ! スゲー!」
「ち、ちょっと、手を引っ張らないで! もげちゃう! もげちゃうからぁ!」
握手のつもりなのか、ウンディーネの小さい手を握って声を上げるルクス。
一方で振り回されるような格好になったウンディーネは分かりやすく狼狽した。
「ルクスよ。儂に会った時と同じことしとるぞ。ウンディーネの手をちぎるつもりか」
「あ、ごめん」
ルクスがパッと手を離すと、ウンディーネは自分の手にふーふーと息を吹きかけながら抗議する。
「あなたねぇ、出会って早々何するのよ」
「ごめんな。精霊と会えてつい嬉しくなっちゃって」
「ふふん。ま、私は可愛いからスキンシップを取りたくなるのは分かるけどね」
「いや、別にそういうわけじゃないけど」
「何ですって!」
「あ、いや、可愛いのは確かだとは思うけど、それで握手したわけじゃないって意味な」
「へ? そ、そう……。なら良いわ、許してあげる」
ウンディーネがもじもじしながら視線を逸らすのを見て、ノームが「自信家の割にちょろいのは相変わらずだのぅ」と漏らす。
その言葉が聞こえたのか、ノームはウンディーネに睨まれることになった。
「はは……。何だか急に賑やかになりましたね」
「まったくじゃ」
ロゼッタが引きつった笑いを浮かべ、ノームはやれやれと溜息をつく。
そして、ノームが咳払いしてから話を切り出した。
「ところでウンディーネよ。何でお主こんなところにおるんじゃ? 大氷窟の奥地にいたんじゃなかったのか?」
「ああ、けっこう前に目が覚めてね。暇だから人間たちの様子でも見ようと思って、地上を散歩してたのよ」
「散歩?」
「そ。けっこう楽しいのよ? その子たちがそうだと思うけど、今じゃ学園なんてものもあってね。若い子たちの会話を聞いているだけで飽きないわ」
「精霊のくせに俗世的なやつじゃのぅ……」
ノームがまたも溜息をつく一方で、ウンディーネは話を続ける。
「でね、今日もその辺を浮いてたんだけど、何とノームの気配がするじゃない。それで、面白そうだったから姿を消して付いてきちゃった」
「なるほどのぅ……。じゃあさっきの話も聞いてたのか?」
「ああ、イビルローズが現れて黒の瘴気が発生したとか精霊の痕跡が見つかったとかってやつね。もちろん聞いてたわ」
ノームの言葉を受けて、ウンディーネは少し真剣な表情になって頷いた。
どうやら同じ精霊として思うところはあったらしい。
「イビルローズを持ち込んで黒の瘴気を発生させるなんて、確かに私たち精霊がするとは思えないわよね。色々と引っかかるところがあるのも理解できるわ」
「うむ。それで、他の精霊たちに会って話を聞くのが早いということになったんじゃが、お主が出てきてくれたおかげで一つ手間は省けたわい」
ノームとウンディーネがそんなやり取りを交わしていたところ、ロゼッタが手を上げて疑問を挟む。
「でも、残りの精霊さんたちに話を聞きにいくにしても、けっこう時間がかかっちゃいますよね? ウンディーネさんみたいに地上に出てきてくれてたら良いんですが、そういった可能性もあるんでしょうか?」
「うーん、今のところそういうのはなさそうなのよねぇ。だからさっきノームの気配を感じた時はびっくりしたんだけど。……あ、でも」
「……?」
「初めに会うべき精霊には心当たりがあるわ」
ウンディーネはくるりと回って、得意げな笑みを浮かべた。
コロコロと表情が変わる精霊だなと思いながら、話を聞いていたルクスは問いかけることにする。
「へぇ。それは誰なんだ?」
「ドライアドよ」
「ドライアド……?」
「そ。あの子は木の精霊だからね。さっきの話によれば、黒の瘴気の発生にはイビルローズが関わっていたんでしょ? 植物の魔物についてなら、何か知っているんじゃない?」
「あ、なるほど」
ルクスがポンと手を叩くのを見て、ウンディーネは満足そうな笑みを浮かべていた。