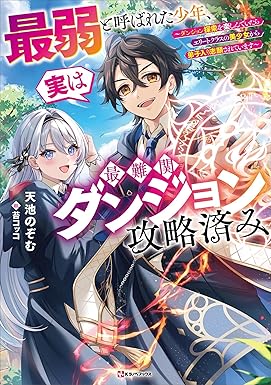第18話 至高の魔法の習得
「――というわけなんだ」
「ふぅむ。なるほどのう。ダンジョンとやらを攻略することで若者を育成する学園か。人間の世界も随分と様変わりしたらしいの」
精霊ノームと出会ってから少しして。
ルクスはここまでやって来た経緯や自分のことについて、ノームに話をしていた。
そのルクスの話が興味深かったらしい。
ノームは時折自分の顎ひげを擦り、興味深く耳を傾けている。
「しかし儂らの住んでる場所がいつの間にか道場扱いされているとは。別に良いけど」
「良いんだ」
「ほっほっほ。儂ら精霊は寛大な心の持ち主じゃからな」
「自分で言うかなぁ、それ」
屈託なく笑うノームを見て、ルクスは「精霊って意外とお茶目な性格なのかなぁ」という印象を抱く。
そして、気になっていたことを聞いてみることにした。
「俺もちょっと聞きたいんだけどさ、ノームのじっちゃんって精霊なんだよな。どうしてこんなところにいんの?」
「ふむ。それは話せば長くなるが……」
「うーん。できれば短くがいいかな」
「寝てたんじゃ」
「短っ」
「お主が短く話せと言ったんじゃろが」
ノームがやれやれと溜息をつく一方でルクスは感激していた。
ルクスにとっては精霊と意思疎通を図れていることが嬉しかったのだ
(ああ、こうやって精霊と話せる日が来るなんてなぁ。見た目は小さいおじいちゃんって感じだけど)
「でもノームのじっちゃん。寝てたって、どのくらい?」
「そうさの。体感じゃが、ざっと500年くらいかの」
「ご、ごひゃく!? それは凄いな」
「ほっほ。精霊は人間と違って長生きじゃからな。暇だったらそれくらい寝るわい」
「そういうもんか」
「そういうもんじゃ」
ルクスの反応が予想通りだったためか、ノームはにやりと口の端を上げる。
やはり中々にお茶目な性格らしい。
「それって他の精霊も同じなの? というか、精霊ってノームのじっちゃんの他にもいるのか?」
「もちろんいるとも。……とはいえ、他の奴らとは久しく会っておらん。大人しく住処で寝てるかは儂にも分からんな」
「住処って、八大精霊ダンジョンのことだよな?」
「ルクスの話によれば今はそう呼ぶんじゃったか。そうだの。そういうことになる」
「おお、それはぜひ会ってみたいな」
「とはいえ、けっこうクセのある奴らじゃからのう。何となくサラマンドラやジンの奴とは相性良い気がするが。たぶんルーナあたりは……。うむ、確実に引かれるじゃろうな」
ノームは何やらブツブツと呟いていたが、ルクスは他の精霊がいるという情報に小躍りしたい気分だった。
というより、既にしていた。
そんなルクスを見て、またやれやれと溜息をつくノーム。
しかし、悪い気はしていないようで、むしろルクスのことを面白い奴認定しているらしく、苦笑を浮かべていた。
「時にルクスよ。お主先程、その魔法陣に入ろうとしておったな」
「ん? ああ。新しい魔法が習得できるかなと思って。ダメだったかな?」
「駄目なもんかい。魔法陣はそのために設置したものなんじゃからな」
「設置したって、これってノームのじっちゃんが設置したものなのか? あ、もしかしてダンジョンをクリアした人へのご褒美的な?」
「…………ふむ。そこまでは知らんか。まあ、随分と時が経っているようじゃしのぅ」
「ん? どゆこと?」
「ま、いいわい。お主の話を聞く限り、今は平和なようじゃしな」
「……?」
意味深なことを言ったノームに、ルクスは怪訝な表情を浮かべる。
が、ノームからはそれ以上語る気はないようで、ルクスの興味も今そこにはなかった。
(200階層で習得できる魔法かぁ。いったいどんなのなんだろうな)
「……ルクスよ。ここまで潜ってくる途中にも何箇所か魔法陣が置いてあったじゃろ。どんなものを習得できた?」
「え? どんなものって、ええと、《土の防壁》に《岩石墜下》だろ。それから《土釜の檻》に――」
ルクスは《ノームの洞窟》に入ってから習得してきた魔法を並べ立てていく。
それを聞いていたノームは次第に焦燥を浮かべ、ルクスが全ての習得魔法を話し終える頃には目を見開いていた。
「な、何とお主。全部習得できたのか……」
「え? それって凄いことなの?」
「凄いも何も。魔法陣はな、その魔法に適性が無い者が入っても反応せんのだ。お主の周りの人間にもそういう奴がおらんかったか?」
「あー、確かに。あれってそういうことだったのか」
ルクスは言って、ロゼッタが魔法陣に入った時に何も反応の起こらなかった魔法陣があったことを思い出す。
学園にいる生徒たちや教師も、反応しない魔法陣があるということを話していたことがあった。
ルクスにとってみれば原因が分からなかったし、魔法陣が反応する数でその人間の優劣が決まるものでもないだろうと深く考えなかったのだが。
ノーム曰くルクスのそれは異常らしい。
「えーと。とりあえず魔法陣、入っていいんだよね?」
「ああ。恐らくお主であればその資格があるじゃろう」
ノームの許可を受けて、ルクスは巨大な魔法陣の中央へと進む。
すると、魔法陣が一際強く発光し、辺りにおびただしいほどの光の粒子が漂い始めた。
「お、これは適性があったってことでいいんだよな?」
「ほっほっほ。本当に面白いの。まさかその魔法を習得できる者が現れるとは」
ノームが実に楽しげに笑う。
そして、周りに漂っていた光の粒子が引き寄せられるように集まり、それはやがてルクスの体の中に溶け込んでいった。
その光の粒子を取り込んだルクスは、習得した魔法が何であるかを理解する。
「こ、これは……」
「ふっふっふ。受け取るがいい、ルクスよ。至高の――《精霊召喚魔法》をな」