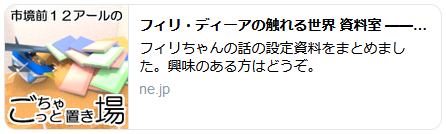25.首都ホープソブリンの死闘(中)
2018.11.23 誤字修正
「残酷な描写」があります。ご注意いただくようお願いします。
「目標の包囲は完了したか」
「は。まずは取り急ぎ配置をしました。これから盤石の態勢となるよう、配備を進めていくところです」
「良し。可能な限り急がせろ」
「は」
マイミー少将が、傍らに立つ副官に質問をし。その副官は、部隊をマイミー少将の手足となるべく指揮をしながら、質問に即答する。
賊が首都ホープソブリン・マイニングに接近したとの報を受けてから、マイミー少将は、自らの旗下にある一個中隊をいつでも出動できるよう待機させ。その賊が「自走する馬車のようなもの」に乗って、目標となるトゥーパー参謀邸に突入したとの報を受け、少将自らが部隊を率いて現場に急行、トゥーパー参謀邸の周辺に布陣をする。
十分とかからずに現地に到着、三十分もしない内に先行包囲網を敷くという迅速な展開を見せながら。それでもなお、既に庭での戦闘は収束し、既に戦場は屋敷の中という状況の速さに、マイミー少将は戦場となった屋敷を隙なく見つめ。副官は包囲をより完全なものとすべく、指示を出し続ける。
――そんな慌ただしい状況の中、つい先ほど到着したであろう一隊の指揮官が、マイミー少将の前に出て、敬礼と共に声をかける。
「ジュディック・ジンライト大尉、武装偵察小隊二十名と共に、ただいま到着しました」
「うむ。――大丈夫か」
「は」
ジュディックの到着の報告に、マイミー少将は言葉短に問いかけをする。
本来であれば三十余名を数えた、ジュディック率いる武装偵察小隊。だが、殉職者二名に、片腕を失った第二班班長のスクアッド曹長も部隊から外し。回復に間に合わなかった負傷兵たちも除外した結果、現在の隊員数は総勢二十名。
この、約六割に数を減らした部隊でこの先の戦闘に耐えられるのかという、マイミー少将の短い問いかけに、ジュディックははっきりと、肯定の意を返し。
「――たった今、賊が二階に上がりました」
屋敷を監視していた兵士からの報告に、ジュディックはマイミー少将へ再び敬礼をし、班を減らし砲兵の数を増やした特殊な編成をした部隊を動かすべく、指示を出し始める。やがて、その指示を出し終えたジュディックは、マイミー少将に向かって報告をする。
「武装偵察小隊はこれより、状況を開始します」
――こうして、首都ホープソブリンの高級住宅街の騒動に、軍という役者が加わり。その騒動はさらに大きくなっていった。
◇
「連中、突入してきたさ。――どうするさ? 一発お見舞いしとくか?」
二階に上がってからも、今までと同じように、絶え間なく銃を撃ちながら、気負った様子も無く、アストは歩き続ける。その彼の耳に入った、後ろを歩くマークスの軽い声に、やっとお出ましかなどと思いながらも、同じように軽い口調でアストは答えを返す。
「すぐ終わるんならな。そんな奴らにかまけてるより、とっとと奴を殺っちまった方が手っ取り早ぇ」
「じゃあ手早く、……っと、流石に動きが早いさ」
アストのあまり時間をかけるなという言葉に、それならまずは牽制をお見舞いしとこうかと、窓から外に砲口を突き出すマークス。それを見たのだろう、瞬時の内に塀の影に隠れる敵兵を見て、マークスは軽く口笛を吹きながら、敵兵が隠れた塀へと砲弾を放つ。
「――っ! ったく、なんさ、あの塀は!」
先の庭での戦闘と同じ、表現のし難い、不快なまでに重々しい金属同士がぶつかり合う音に顔をしかめるマークス。それでも砲撃を中断すること無く、第二射、第三射を立て続けに放つ。
「ったく、そのうぜぇ音、どうにかしろよ」
「それを俺っちに言われてもさ」
その間も手を止めずに交戦を続けていたアストにも、その音には思うところがあったのだろう、射程内の敵をあらかた片付けたあと、マークスに文句を言う。そのマークスは、苦笑いをしながらも、肩を竦めるだけで何も言わず。先へと進み始めたアストの後を追うように、静かに歩き始めた。
◇
鳴りやむことの無い銃声が鳴り響く屋敷の周辺を、軍が包囲する。ジュディックの指揮の元、正門から突入を敢行した武装偵察小隊は、マークスの威嚇射撃めいた砲撃に足を止められ。その間にもアストは一人ずつ、確実に敵兵を倒していき。やがて屋敷の二階もそのほとんどを制圧し終え。――残すはトゥーパー参謀官の待つ、特別警護室だけになっていた。
◇
「二階、居住区まで全滅。特別警護室前での交戦が始まりました」
「……そうか」
特別警護室の中で戦況を見守っていたトゥーパー参謀官は、今しがた部屋の入口で報告を受けた警備長からの報告を受け、静かに答える。
警備員の配置も終え、屋敷からの脱出にも失敗し、これ以上出せる指示も無く。トゥーパー参謀官は、時おり戦況を伝えてくる報告に頷きながら、勝負がどちらに傾くのか、警備長と二人、静かに待ち続ける。……そんな二人に届けられた、敗報にも等しい報告に、警備長はトゥーパー参謀官に対し謝罪をする。
「申し訳ありません」
「何を謝る」
その言葉を聞き、トゥーパー参謀官は返事を返す。その声に、普段通りの、――否、普段よりもさらに彼らしい傲慢さをにじませながら。
「今回のこの結果は、君を含めた私の手駒が、単に相手よりも無能だった、たったそれだけのことだ。まさか君は、自分の無能を自分自身で責任が取れると、そんな思い込みをしてるのか。――それならこの結果にも納得だがな」
その言葉は、この期に及んで、いや、この状況だからだろうか。まるで当たり前のように目の前の警備長を見下しながら。ただ尊大に、警備長に対し命を下す。
「そんな細かいことはどうでも良い。早く君も防戦に加わりたまえ。――ここで意味のないことを話すよりは、その方がよほど有意義だ」
「は」
そんなトゥーパー参謀官の命令に短く返事をして。警備長が振り返り、扉の方に向かおうとした、その矢先。――いつの間にか銃声が消え、静かになっていた特別警護室。その入口の扉が荒々しく蹴とばされ、叩きつけるように開けられた音が鳴り響き……
「――ハン! 何をクソ下らねえことを話してやがる」
……手にした愛銃で、屋敷の中にいた人間のほとんどを倒したであろう男の声が、特別警護室の中へと響き渡った。
◇
扉が蹴破られる音と同時に向き直り、素早く銃を構える警備長とトゥーパー参謀官。だが、彼らが魔法式を刻むよりも、アストの銃撃は早く。構えた銃を取り落とす二人を、冷たい目で見るアスト。
「ああ、確かに無能だわ。この距離なら、切りかかってきた方がまだマシなのにな。ちんたら魔法式なんか刻むってんだからな」
そう言いながら、ゆっくりと二人の元へ歩くアスト。一歩、歩きながら装弾し、次の一歩で発砲する。頭を撃ち抜かれ、力なく崩れ落ちる警備長には目を向けず。続けて装弾しながらも歩を緩めず。やがてうずくまったままのトゥーパー参謀官の目の前に、見下ろすように立つアスト。
「これで、この屋敷で生きてるのはお前だけだぜ」
「……何故こんな真似をした」
頭上から突きつけられる銃口に、降りかかるアストの言葉。その言葉を聞きながら、トゥーパー参謀官は静かに問いただす。
「これが出来るのであれば、もっと簡単に私を殺すこともできたはずだ。何故こんな回りくどいことをした」
「ハン、何を言うかと思えば。――テメェが何をしても結果は変わらねぇ、これで思い知っただろう?」
トゥーパー参謀官の最後の質問。その質問に、アストは面倒くさそうに答え。――その答えに何か納得したのだろうか、トゥーパー参謀官は心底納得のいった表情で、最後の言葉を言い放つ。
「……ああ、そういう事か。君たちは、私よりも自分たちの方が上だ、たったそれだけのことを言いたいがために、これだけのことをした訳か」
「勝手に言ってろ」
トゥーパー参謀官の最後の言葉に、アストは心底つまらなさそうな声を上げ。無造作に引き金を引く。
――こうして、十年来の復讐劇は、どこかあっけなくも淡々と、その終幕を迎えることとなった。
◇
「……いや、あんなことを言ってたけどさ。あの御仁、身の回りの警護は異様なほど硬かったさ」
「普通に手を出してたら逃げ切れないってか。……そんな事、わざわざ教えてやる事でもねぇだろ」
「まあ、そうさな」
アストが引き金を引いた直後、部屋の片隅で独白するように呟くマークスの言葉に、めんどくさそうにアストが答える。
アストが十年前に手にかけた「誰かの駒」、その駒に命令をしていた黒幕を、彼らは裏の世界に潜みながら、追い求め。当時知り合った「親父」からの情報提供もあり、比較的早い段階でトゥーパー参謀官――当時は局長――という黒幕の存在を知った二人。だが、同時に彼らは、その黒幕の、異常なまでの安全に対する執着を知ることになる。
要塞のような邸宅、街の要所に張り巡らせた監視網、さらに、街から出ようとしない、出る場合も軍の護衛を付けるという、もはや執念と言っても良いような安全に対する配慮に、手を出せばこちらもやられる、そんな覚悟が必要な相手だということを二人は思い知り。
なら、先に「果たすべき義理」を果たしてからと復讐を先に延ばしたのは、当時の段階ですでに「親父」の流儀に染まり始めていたのか、それとも彼らの元々の性質か。
「結局、意味があったかどうか、謎っちゃあ謎だがな」
「まあ、すぐそこに軍がお待ちかねだとさ、何のための手間だったとは思うさ」
全てを片付け、さてどうしようかと思った所で、そのトゥーパー参謀官が、聖典を盗み出すための駒を探していることを知り。この依頼を利用すれば、相手も国を動かせないだろうと、「親父」に手を回してもらい、自分たちの素性を知られないようにその依頼を受け、現在に至る。
結局は軍が介入してきた訳で、なんのための小細工だったのかと思わないでもないが。それでも、こちらが接触を図るまで軍は動こうとしなかったのだから、意味はあったのだろう。――本来なら、常時街中に張られていた監視網に触れただけで、軍が出動するはずだったのだ。
そんなことを考えながら、アストは入口の方へと振り返り、壁にもたれかかった相棒へと話しかける。
「まあ、向こうの都合なんざ知らねえが、こっちが手を出すまで手を出して来なかったんだ。一応、意味はあったんだろうさ、……って、オイ、マジか」
最初は、それでも果たした復讐の余韻もあったのだろう、床を隔てた一階にもう一つの「敵」が動き回っていることを承知の上で、相棒としていた世間話を続け、――やがて、その階下の敵の動きに違和感を覚え、そして、階下の敵が何を考えているかを悟ると、慌てて駆け出しながら、相棒へと叫ぶ。
「こっから出ろ! クソ、正気かよ! 奴ら、俺たちを床ごとブチ抜く気だ!」
それは、アストが過去に経験した中でもとびっきりの「非常識」な作戦だった。
◇
「砲隊、構え!」
賊との二度にわたる交戦と、国境線での友軍の戦闘結果を振り返って。ジュディックは一つ結論を出す。
(障害物に身を隠した奴らは無敵だ)
あの賊の持つ速射銃に連装砲という、連射に特化したような武器は確かに脅威だ。だが、単に弾数だけで言えば、十人もいれば彼らを上回る。たったそれだけの人数であれば、準備することは容易い。現にトゥーパー参謀官も、軍に頼らずに百人以上の人と武器を集めてみせた。
その上で、この惨状なのだと、ジュディックはこの屋敷へ突入した時の風景を思い出す。――小口径の連想銃に撃たれたのだろう、的確に頭を撃ち抜かれた多数の死体に、砲撃に巻き込まれたであろう肉の塊。身動きする者はほとんど無く、その殆どは既にこと切れていると一目でわかるような、普通の人間であれば衝撃を受けたであろう、地獄のような光景。――だが、その光景を見たジュディックは、その様子を一瞥したとき、思ったのだ。
(……まあ、生存者がいない方が、都合が良かったのかも知れないな)
普段のジュディックらしくない、冷めた思考。それは、トゥーパー参謀官のこれまでの行いを知った故か。
この屋敷の主であるトゥーパー参謀官は、自身の出世のために、権力と暴力と駆使し、相当に悪質な行為をやってのけたふしがある。きっとここで倒れている者たちは、「警備員」というよりは本当に「私兵」なのだろう、それはきっと、普通の「民」とは違う者たちなのだと、資料を読んだジュディックはそう感じ。
それは、通常であれば生存者の救出を最優先にすべきこの状況で、人命よりも「聖典の奪還もしくは破壊、及び賊の討伐」という任務を優先する自分たちへの言い訳だろうか。だが、ジュディックやその指揮下の武装偵察小隊の隊員は確かに感じたのだ。――ここにいる者たちは、自分たちが守るべき者たちとは違うと。
(とにかく、まずは任務を達成、人命救助はその後だ)
そう、ジュディックは自身の感情を押さえつけ。当初の予定通り、一階の広間へと布陣をする。そこは、目標がいるであろう二階にある特別警備室の真下にある広間。事前に準備しておいた八門の砲を、その特別警備室の外周に沿うように、均等に、ほぼ真上に向けるように配置する。
(奴らが厄介なのは連射できることではない。脅威なのは、こちらが撃つ前に撃つことができる即応性と、異常なまでの命中率だ。――撃たれる前に撃つ。狙いを定められる前に狙い撃つ。奴らはそれに特化している。だから、こういった障害物の多い建物の中は、奴らの独断場だ。ならば……)
同じ条件なら、常に先手を打って攻撃できるのがあの賊の強み。だから、あの賊に勝とうとするのなら、同じ条件で戦ってはいけない。
例えば、包囲して数で押し切る。例えば、銃を生かせないような近距離にまで接近する。――もしくは、大火力を準備して、敵を障害物ごと撃ち抜く。そうすれば、相手の優位は無効化できる。そう確信しながら、ジュディックは、部下たちに対し、叫ぶように命令を下す。
「撃て!」
――その号令で、一階から二階への一方的な砲撃が始まった。
◇
八門の砲口から砲弾が放たれる。轟音のような発射音に、天井が崩れ落ちる音。隊員たちの目の前に落ちる二階の床に、ある者は後退し、ある者は守るように腕で顔をおおう。
号令を発したジュディックも、飛来する石礫に腕で顔を守りながら、見上げるように視線を二階へと向け。
――その頬を、銃弾がかすめ飛ぶ。
頬に一筋の傷を付けながら、ジュディックは、銃弾が飛来したであろう方向へと目を向け。崩れ落ちた特別警護室の入口に立つ一人の男を見上げる。
過去において、目の前で自分の部下を蹂躙した一人の男。その男が、記憶とは逆の、左手に銃を持ったまま。二階から土煙が漂う一階の大広間を、まるで自分たちの姿を目に焼き付けようとするような、そんな鋭い視線で見下ろし。――やがて踵を返し、姿を消す。
――砲撃の衝撃だろうか、その男の右腕は力なくぶら下がり。その指先からは、赤い雫が滴り落ちていた。