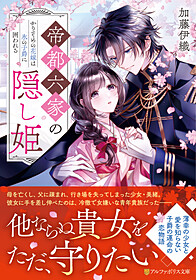第58話 サンバ仮面が日本刀を語る。なお絵面以下略
注)マニアックな話が入ります。サンバ仮面の解説は斜め読みでも全然大丈夫です。
気持ちはわかる。私も人の配信見てて、その人の母親がサンバの仮面付けて出て来たらそりゃ驚くもんね。
「では、刀についての説明をと言われているので、遠慮なく。
みなさんは刀と聞くとお侍さんが腰に大小の刀を差してるのを想像するのが多いんじゃないかしら? あれは江戸時代に『武家諸法度』の中で打刀と脇差の大小2本の刀を身につけることを武士の正装と定めたからなの。ゆ~かの村雨丸は太刀で、打刀とも脇差とも違うのね。その違いは主に長さ。太刀は平安時代から作られ始めて、刀身が長く反りがあるのが特徴よ。時代が平安から鎌倉に移ると、武士の時代になって刀も盛んに作られるようになったの。この頃も主流は太刀ね。反りがあるのは馬上での戦闘を想定して作られているからで、腰に佩いたとき――太刀を身につけるときは刃を下に向けて、下側が湾曲した形で身につけるのだけど、これを『佩く』と言います。対して打刀は刃を上に向けて身につけて『差す』と言うの。これ割と大事な違いだから憶えておいて。太刀に反りがあるのは馬上での抜きやすさの為と言われてるわね。武士の時代が続いて、鎌倉時代では鎌倉の地に多くの刀工を京などから招いて刀を作らせたの。七里ヶ浜から砂鉄が採れたこともあって、あの超有名な正宗が革命的な作刀技術を確立させて『相州伝』と後に呼ばれる作風を完成させ、正宗十哲と呼ばれる彼の弟子が……」
「待ったー!! 誰がそこまで詳しく語れとお願いしましたか!? 私多少知ってるつもりだったけど、聞いてて何が何だかわかりませんでした!!」
私は思いっきりサンバ仮面を画面の外まで押し出した。
いやもう、そりゃ説明してとは言ったけど、刀の簡単な分類くらいかと思ってたよ。まさか延々と歴史を語られるとは……。
「やだー! せめてもうちょっと話させてよー! 打刀の特徴だけ、ちょっとだけ、ちょっとだけだからぁー!!」
『ママさん……』
『話させておあげ……語りたいんだよ』
『ゆ~かが大人になるとこんななんだろうか』
『大人げないママ可愛い』
『いや、割と面白いよ』
『むしろお経のような感じで聞いていた』
『サンバ仮面が日本刀を語る絵面がほんとシュール』
画面の外から聞こえるママの駄々をこねる声に、同情のコメントが相次ぐ。
マジですか……。
「みんな心広くない? 詐欺とか遭ってない? 大丈夫? ……じゃあ、あとちょっとだけだよ。ママー、本当にあとちょっとだけだからね」
「やった! みんな大好き~! ゆ~かの村雨丸は太刀だけど、時代が下ってくると徒歩戦闘をする足軽などの戦力が増えてくるのね。それで軽量化とかが進んで、太刀よりも短い打刀が主流になってきたの。太刀を短くして打刀にしたケースもあるし、最初から打刀として打たれる刀も増えてきたわ。打刀自体は鎌倉時代初期に粟田口国吉が打った『鳴狐』が最古のものよ。普通刀は真上から見ると真ん中が膨らんでいて、それを『鎬』と言うんだけど、鳴狐はその鎬のない平造りという刀で、それまでなかった『打刀』という概念を突然変異のように生みだして……」
「長い!! もうダメ! イエローカード2枚目! ハイ退場!」
私はまたもやサンバ仮面状態のママを押しだそうとした。ところが、ママは私とがっぷり四つに組んだまま、話し続けるじゃありませんか! なんという執念!
「江戸時代になって戦乱の時代が終わると、実践剣術は衰えていって竹刀で練習をする道場が増えてくるの! そうするとますます刀の反りはなくなって、竹刀での戦いの形が刀にも反映されてくるわ。結果、有効な戦法として『突き』が目立ってくるようになります! だから、刀を見るときには反りを見ると大体の年代が」
「そうとも限らないんじゃない!? 腰反りの太刀とか磨りあげられてたらさ! もう本当に終わり!」
「やだやだー! 最後に推し刀についてだけ語らせてー! 刀は湿度に弱いから乾燥している冬の間1ヶ月だけ展示される国宝・圧切長谷部は正宗の弟子でありながら山城伝の刀を作刀した長谷部国重が南北朝時代に打った刀で、皆焼という刃文が全面に現れた焼き入れが特徴よ! 最初は大太刀として打たれたんだけど磨りあげられて打刀まで短くなったの。織田信長から黒田官兵衛に下げ渡されて、以来黒田家に家宝として……」
「くっ!! 全力で押してるつもりなのにびくともしない!! ママ、なんでこんなに踏ん張りが利くの!?」
「スリッパの裏にゴムのブツブツ付けてきた!」
「反則にも程があるじゃん!? 出禁! サンバ仮面はもう一切出さないからー!」
『JK冒険者の配信を見てたつもりが、何故か相撲を見ている件』
『ほんとそれ』
『この親にして村雨丸ありとみた……』
『刀に縁のある血筋か……』
『前代未聞のカオス回だな』
「圧切長谷部は私も見たけど、殺意バリバリに高い刀でした! 以上! ゆ~かの新武器お披露目会でしたー!」
「ちょっとゆ~か! 推し刀だけ語らせてって言ったでしょ!? まだ義元左文字について語ってない!」
「義元左文字もなんか恐ろしく殺意高い刀でした! ママは殺意高い刀が好きみたいです!! それでは、おやすみなさーい!」
ママから手を離して、強引に配信を終わらせる。ハァハァ……ヤマトの暴走よりある意味厄介だった……。こういうことになるとママが強すぎる。
「義元左文字は歴代の持ち主の名から三好左文字、宗三左文字とも呼ばれることがあるの。今川義元の佩刀だったんだけれど、桶狭間の戦いで義元が討たれた後に織田信長の手に渡って、信長の手で磨り上げられて金象嵌でわざわざ『義元を討って手に入れた刀だよ』って銘を入れられて……。って、あああー! 安徳天皇が壇ノ浦の合戦で草薙剣と共に入水したことで、後醍醐天皇が三種の神器を欠いた状態で即位することになって、そのコンプレックスからか後に刀鍛冶を月当番で招いて指導させて自ら刀を打つようになって、打たれた刀は菊御作って呼ばれてる話し忘れたー! あれ日本刀史の上で重要事項なのにー!」
ママってば、配信終わってるのにまだしゃべってる……。
前に蓮くんに「刀の事ならママに聞けば2時間くらい語ってくれるよ」って言ったことがあるけど、多分ガチで語らせたら一晩語るやつだわ、これ……。