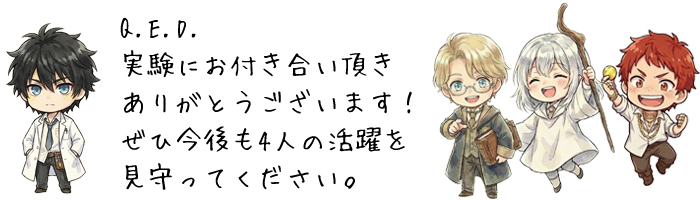第4話 入学試験の大気質レンズ
15歳になった春。私は生家を出て、王都にある「ヒルベルト魔導学院」の門を叩いた。
この国における魔法教育の最高峰であり、同時に、私の理論を実証するための巨大な実験設備(と予算)が眠る場所だ。
試験会場となった広大な演習場には、数百人の受験生が集まっていた。
その大半は貴族の子弟であり、彼らが身に纏う高価なローブや、これ見よがしに携帯した宝石付きの杖が、会場の空気をきらびやかに彩っていた。
対して、私はシャツにベストという軽装。杖も持っていない。
腰に下げた工具袋(チョーク、計算尺、水平器入り)だけが、私の武装だった。
「次! 受験番号402番、マルス・フォン・ベルンシュタイン!」
試験官の声と共に、金髪の少年が自信満々に進み出た。
彼の前、約50メートル先には、試験用の「鎧人形」が設置されている。厚さ3センチの鉄板で補強された、頑丈な標的だ。
「我が家の秘伝を見せてやる! 轟け、雷帝の槌!」
マルス少年が派手な詠唱と共に杖を掲げると、紫色の電撃が迸った。
バリバリという轟音と共に雷撃が鎧人形を直撃し、黒焦げにして吹き飛ばす。
「おおっ!」
「さすがベルンシュタイン家の長男だ!」
「これは合格間違いなしだな」
会場がどよめき、試験官も満足げに頷いて点数を書き込む。
だが、待機列の最後尾で、私はあくびを噛み殺していた。
(……エネルギー効率が悪すぎる)
今の雷撃、電圧は高いが電流が低い。
音と光(放電)にエネルギーの大半が逃げており、標的への熱伝導率は20%にも満たないだろう。
「派手な音を立てる」ことが目的なら合格だが、「敵を排除する」ことが目的ならば落第だ。
「次! 受験番号403番、レイ・カルツァ!」
私の番だ。
私はポケットに手を突っ込んだまま、気だるげに定位置へと歩き出した。
周囲から、「なんだあいつ?」「杖も持ってないぞ」「田舎貴族か?」という嘲笑が聞こえる。
「始め!」
試験官の合図。
だが、私は動かない。詠唱もしない。杖も構えない。
ただ、空を見上げただけだ。
今日は快晴。太陽高度は約60度。
絶好の「光源」日和だ。
「……おい、何をしている? 早く魔法を撃て」
試験官が苛立ち始めた。
私は彼を一瞥し、静かに言った。
「もう撃っていますよ。光の速さで到達するまで、あとコンマ数秒お待ちを」
私は脳内の演算領域をフル稼働させた。
視界に見える無数の「金色の糸」。
上空、高度100メートル付近の空気分子を捕捉する。
(大気密度分布、書き換え。直径200メートルの巨大な凸レンズ形状へ)
使うのは「屈折率(Refractive Index)」だ。
空気は圧縮すれば密度が上がり、光の屈折率が高くなる。
中心部の空気を極限まで圧縮し、周辺部へ行くほど密度を下げる。
そうやって空に巨大な「空気のレンズ」を作り出すのだ。
ローレンツ・ローレンツの式に従い、私は上空の空気を精密に成形した。
演習場に降り注いでいた太陽光――その広大な面積分の光子が、空気のレンズによって屈折し、地上の「一点」へと収束していく。
ターゲットは、鎧人形の胸部。
集光倍率、約1万倍。総熱量、推定31メガワット。
ジュッ。
音は、一瞬だった。
爆発音も、雷鳴もない。
次の瞬間、鎧人形の上半身が「消滅」していた。
いや、正確には瞬時に数千度のプラズマへと相転移し、気化して蒸発したのだ。
あまりの高熱に衝撃波すら発生せず、鉄の鎧はドロドロに溶ける暇もなく気体となって消え失せた。
「は……?」
試験官がペンを取り落とした。
マルス少年も、他の受験生たちも、目の前で起きた現象が理解できず、口をパクパクさせている。
魔法の光も、飛翔体も見えなかった。
ただ、次の瞬間に標的が蒸発していたのだ。
「な、何をした……? 魔法の痕跡(マナの残滓)が全くないぞ!?」
震える声で問う試験官に、私は上空のレンズを解除しながら答えた。
「魔法エネルギーは使っていませんからね。あそこにある太陽光を集めただけです」
私は空を指差した。
上空の空気密度が元に戻り、一瞬だけ陽炎のように空が揺らぐ。蜃気楼と同じ原理だ。
「ただの大気光学ですよ」
静まり返る会場。
私は工具袋の位置を直し、踵を返した。
この出力なら、入学は問題ないだろう。
さあ、早く研究室を見つけなくては。地球への通信機を作るには、この学校の設備をフル活用させてもらう必要があるのだから。
(第4話 完)