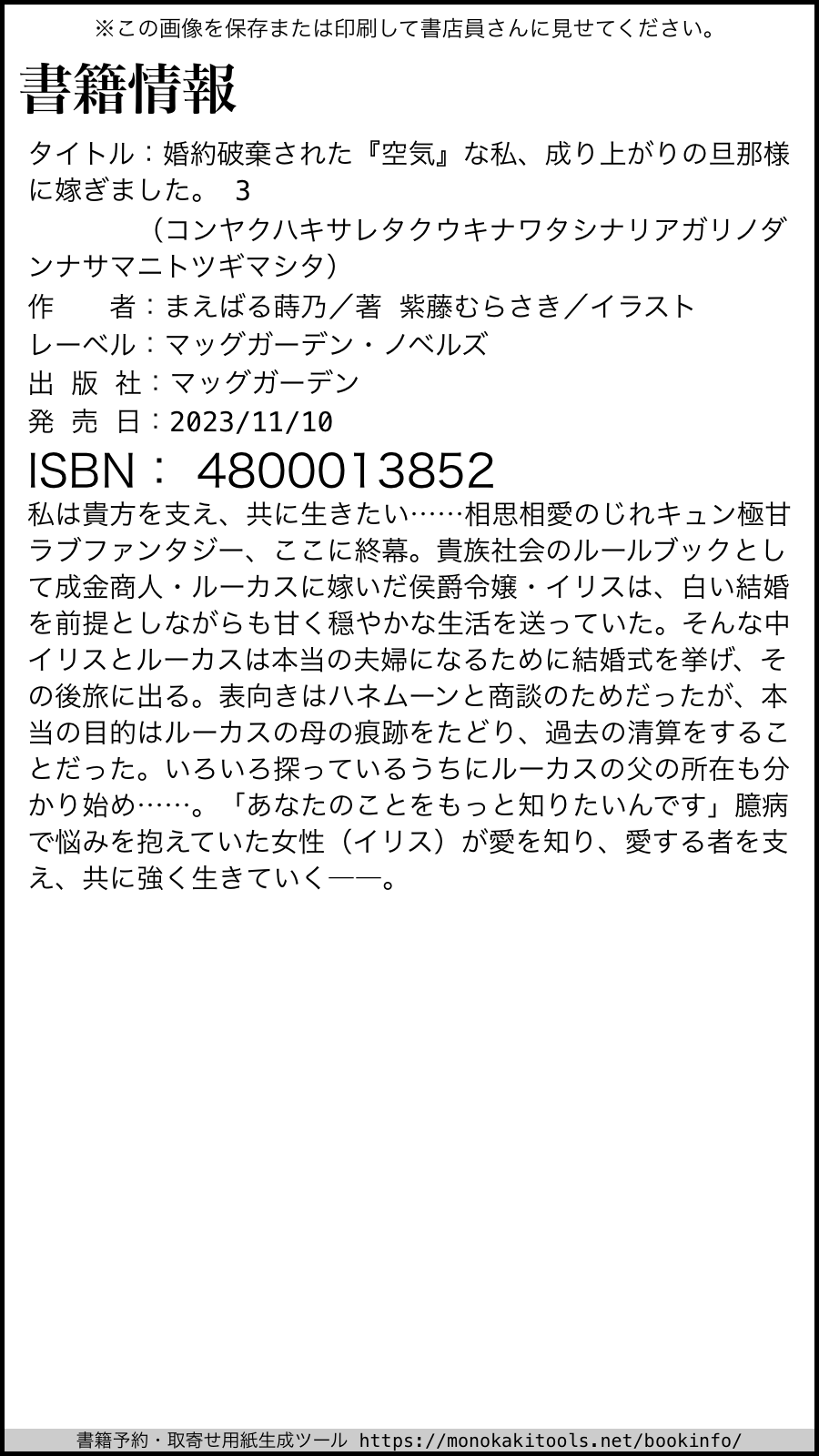底辺悪女の生存戦略
ハリボテ聖女本日発売!空気な私ご予約開始!
よろしくお願いします!
妃候補のご令嬢に求められるのは、品行方正、頭脳明晰、才色兼備。
――なんて嘘だ。
一番求められるのは血脈、容姿、そして何より頭がカラッポであることだ。
現状に疑問を覚えず、周りのプロデュースするままに振る舞い、それで不満も溜めずに妃候補として貞淑で、百発百中で男二人と女数十人、子供をぽんぽん産んで産んだハナから子供への愛着を忘れてすぐに子供を産む、公務で笑顔で手を振る。そんな女が求められている。
完璧なテーブルマナー、背筋を伸ばして歩く所作?
そんなもの、貴族家に生まれた女なら呼吸と同じ、誰だってできること。
庶民の子供が野良仕事をできるのと、スラムの子供が自然とスリを覚えるのと同じ。呼吸と同じだ呼吸と。野良仕事ができて立派ですね、と言うか? 当然だろ、と言うでしょう?
なぜそんなにも悪く言うのか、って?
だってしょうがないじゃない。
私レイン・ノーストは貴族学園で学年に複数人認められる平民特待生、という名の生贄。
私は存在することで、貴族令息令嬢達に「平民とはこういうものだ」と見物させるためのサンプル。
貴族社会に慣れない哀れな平民を、助けてくれる王子様なんてこの世にいない。
たとえ私が美少女だったとしても、ね。
私は生贄。
ご令嬢たちが隠した世界で一番汚いところをよく知る身。
今日も私は令嬢様たちに制服を切り裂かれ、ありがたくも下着着用の慈悲を与えられ、校舎から寮へと帰っている。私を遠巻きに見る連中は全員、貴族、貴族、貴族。全寮制の学園内に安寧の場所は与えられた寮の個室だけ。そこでさえも、何度も鍵が壊されて、夜に襲われかけることもあった。
自慢だった真っ赤な髪もざんばらにされた。
自分で整えると、背中まであった髪は肩でくるりと内巻きになる程度の長さになった。
鏡を見て、私はつぶやいた。
「地獄だわ」
耐えるべきか逃げ出して娼婦にでもなるべきか、私服姿で呆然と考えていた翌日の朝。
ついに先輩の平民特待生が、時計台で自殺未遂を起こした。
毎年一人は平民特待生が自殺するなり辞めるなり、騒動を起こすなりして消えていく。
「死んだら終わりじゃないの。……どうして」
私は唇を噛んだ。
そして季節が変わり、新しく希望に満ちた平民がキラキラとした目で翌日から学び舎に入る。いつ死ぬか、貴族連中の賭け事になるために。
「私は死にたくない。社会的にも、人間としても」
平民がどれだけ外に出て訴えても、選挙権すらない平民の言葉は誰も聞かない。
この学園から逃げ出せばそれでジエンドだ。
私は泣き寝入りは絶対にしたくなかった。絶対に、負けたくなかった。
◇◇◇
「ねえ、私を助けてよ」
そこで貴族男たちをたらし込むことにした――簡単なのだ。男をたらし込むこと、それ自体は。
別に本命にして欲しいわけじゃない。
火遊び的に平民と遊ぶのもいいんじゃない? と、誘う。
淡白さがかえって「遊びくらいなら可愛がってもいいかな」と思われ、そして彼らは軽い気持ちでチヤホヤしてくるようになる。
すると貴族令嬢たちは憤怒する。
たいていの貴族子息様は婚約者という名のつがい持ちだからだ。
男を奪われた女たちのヒステリーは度を増し、私に対する嫌がらせも辛辣になる。
――しかし貴族令息たちの姫になれると、彼らは私の味方になってくれるのだ。
都合の良い、愛想の良いわきまえたちょうどいい平民女だかは。
主張しすぎる女を、うざったい女を、貴族子息は嫌う。
おとなしく言いなりになってニコニコする令嬢を、貴族令息は求めている。
嫉妬したり、私にくさあまりに婚約者を咎めたりする賢しい女を、貴族子息は嫌悪する。
俺を縛るのか、令嬢ごときが――と。
令嬢たちに切り刻まれた髪は丁寧に内巻きにして可憐さを演出する道具にして。
最初はゴミ箱から漁った化粧品を使っていたけれど、何も言わずとも男たちが私にあれこれと貢いでくれるようになった。
私はいつしか直接的な金銭さえ貢がれるようになった。
必死に顔色を窺って。
理想の「ちょうどいい女」を演じて媚びて。
心を擦り減らす代わりに、庇護を得る手段を覚えた。
「ねえ、知ってる? 君みたいな子は淫乱っていうんだよ」
私をブティックに連れて行って買い与えた服を着た私を撫でながら、ねちっこく語る貴族令息。あんたは大神官の息子だったわねと、揺れる宝珠を横目で見ながら思う。
淫乱。
そんな言葉だって、私にはちっとも刺さらない。
私のプライドのありかはそこじゃないから。
そもそも貞操はしっかり守っている。
私が持つ唯一に近い切り札は、切るのはまだ惜しい。
無事に学園を卒業すること、そして生き抜くこと。
それが私の目的だから。
◇◇◇
平民特待生が二人ほど消えた一年目が終わり。
私は第二王子の恋人となることに成功した。
リュート・マクイストン・デリアード第二王子殿下。
黒髪に鋭い青い瞳を持つ彼は、貴族令嬢たちから蛇蝎のように嫌われていた。
幼馴染とすげなく婚約破棄したからだ。
そんな彼は、なぜか私を受け入れてくれた。
貸切になった学園内のサロンにて、私はリュート第二王子殿下にしなだれかかりながら尋ねた。
「ただでさえ評判が地に落ちていらっしゃるのに、私なんかと一緒にいてよろしいのですか?」
「愚図で愚鈍な人間が嫌いなだけだ。男だろうが、女だろうが。蛇蝎のようにしたたかな悪女の方が、幾ぶん退屈しなくてましだ」
「素直におっしゃればいいのに。虫除けに毒を撒いているのだと」
第二王子は意地悪に目を細めて笑った。
「せいぜい良い虫除けになってくれ、悪女」
黒髪の彼と赤毛の私が一緒にいると、随分と派手で毒々しくなった。
貴族令息たちは、第二王子を畏れて私に近づくのをやめた。
貴族令嬢たちは、悍ましいものを見る目で私を見た。
「ふしだらですわ。平民のくせに、礼儀作法も知らないで思い上がって、色目を使って」
第二王子の寵愛を受けるようになって、目立つ暴力が振るえなくなった貴族令嬢たちは、別の方法で私を貶めようと必死になった。
正攻法で生き残れない私が、持てる手管と能力で生き残ることのなにが悪い。
第二王子という後ろ盾を得た私は、人前ではわかりやすい『可愛い女』『かわいそうな女』の振る舞いをするようになった。
淫乱ぶる理由が消えたのならば、可愛らしい女の演技をした方が今後は効果的だ――第二王子の可憐な彼女としての。
私は第二王子に人前で抱きつき、甘え、令嬢たちに嫌がらせを受けると王子の前でぽろぽろと泣くようにした。
第二王子は私の意図に気づいて面白がって令嬢たちを見下し、そして彼に勝手に取り巻く男たちも、一斉に彼に賛同して令嬢たちを冷笑した。
愚かしい女たちを笑い、都合の良い私を逆張りでちやほやするのは、愚かな貴族令息たちにとって良いお遊びになった。
異性の悪口で盛り上がるのは気持ちいいよね。わかるよ。
「君は相変わらず性格が悪い」
「褒め言葉として受け取っておきますわ」
「淫乱だと君を謗る声もあるが、本当のことを聞きたい」
「さあ、それはあなたが一番知っているのではなくて?」
二人っきりになると、第二王子と私はただお互い抱き合って熱を求めた。先ほどまでの毒々しい演技を捨て去るように、私たちは沈黙し、静かな時を分かち合った。
◇◇◇
次に、私は女の味方を得ようと思った。
まず端的に言えば、スクールカースト内で絶妙な位置の女たちを拾い上げてやったのだ。
トップクラスになりきれない、上の下程度の女たち。
その程度の女は大抵、心がねじくれている。
彼女たちは私という特別な存在に好かれると、途端に機嫌をよくする。
「みんなは悪女だというけれど、彼女は本当はいい人よ(だって、私を見つけてくれたのだから!)」
そうね。
確かに言う通り、私はいい人だわ。
だってあなた達の自尊心を満たしてあげているのだもの。
悪評だらけの私が助けると、コンプレックスを拗らせた子ほど心を開いてくれる。
悪い男に優しくされたら簡単にトクベツを感じて、くらっとするのと同じ。
悪女の私が実は苦労人の健気な被害者だと思うと、真面目な彼女たちは憤然と私の味方になってくれるのだ。
味方にしてしまえば、令嬢たちはちょろい。
だってこいつらみんな、世間知らずの真面目さしか取り柄がないお嬢様だから。
ちょっと誘導して放っておけば手を汚さずに私のために動いてくれる。
続いて、次に味方になってくれるのは、もう少し下のランク。「自分は真っ当な人間だ」と思い込んでいる大多数のミドルカーストの羊たちだ。
私がいじめられているのを空気のように無視していた層。
自分は善良かつ中庸である、と信じているタイプ。
これ系は「上の下」を仕留めた後なら簡単だ。
牧羊犬がわりのリーダー格をたらしこめば、みんなストンと私に堕ちる。
ここまでくると、私は
「悪評も流れていたけれど、本当は一生懸命で根がいい人、私たちの憧れの人」
という見事な立ち位置に躍り出ることができた。
私は神経を草臥れさせながら、一人ため息を吐く。
「……羨ましいわ、羊でいられるなんて」
そもそも令嬢に与えられた教育なんて、従順な羊になるための毛繕いだもの。
父に夫に目上のものに、逆らわず貞淑に身を守り贈呈され世継ぎを孕む貢物、リボンのかけられたぴかぴかの子羊。育ちが良ければ良いほど、扱いやすい。
――もちろん、家柄も育ちも良いに越したことはないのはあたりまえ。
だって、学も家柄もないせいで一歩先の未来すら考えられない底辺はいくらでもいるわ。
結局人生なんて、特別な一握り以外の羊にとっては群れに紛れてやり過ごすだけのもの。
その羊の皮すら被れないのなら獣と同じ。羊と、羊の飼い主に殺されるだけ。
だから私、誓って馬鹿にしてるんじゃないのよ、令嬢を。本当よ。
扱いやすいイコール、彼女たちには褒め言葉なんだから。
きっと私の見解を聞いても喜ぶわ、あの子たちは。
私は羊にはなれない。
羊になれば死んでしまう。
あなたたちのような贈答品用の羊じゃないから。
生き延びられない私は、狼になるしかないのだ。
その頃には完全に、男の掌握は私のやるべきことではなくなっていた。
第二王子の女というだけで、縦社会極まった男社会に置いて私は傅かれる側となる。
たとえ気に入らない女だろうが、第二王子サマの認めた存在の価値は、認めないと生きていけないのだ。
◇◇◇
そんな感じで、無事に楽しい学園生活は幕を閉じた。
後ろ盾を得て真っ当に学べる環境を作って、女達を落とし、男達の好感度を上げ、平穏に生きたかっただけだから。
私は学園に求めるものを、在学中に全て手に入れた。
人心掌握の術を学んで、容姿を磨いて。
上手な羊の被り方を覚えて学歴を手に入れて教養を身につけて、ついでに貴族への媚び方も覚えて。
手に入れたコネクションで無事、望み通りの進路も得た。
「……ごきげんよう、まなびやよ」
私は一人、校門から学園に向かって辞儀をする。
卒業式の華やかな場は興味がない。
記念パーティなんて家柄のある人たちが最後の見合いとお披露目を繰り広げる場。婚約発表、婚約解消、婚約申し入れ。そんな場に、私は興味ない。だって私は平民。そういう場所で目をかけられる商品になり得ない女だ。
私はもうたくさん。
「さ、体が冷える前に早く去りましょう……」
証書を片手に学園を去ろうと馬車乗り場に向かう私を、追いかけてくる人がいた。
「待ってくれ、レイン」
「……第二王子殿下」
リュート・マクイストン・デリアード第二王子、その人だ。
意外だった。
侍女たちが整えてやった黒髪は汗で乱れ、息も絶え絶え。情けない有様だ。私は心からの感謝の気持ちを込めて礼をする。
「学生生活で、守っていただきありがとうございました。学園内で起きたことも、第二王子殿下のことも、身分相応に今後は忘れて過ごしますのでご安心ください。殿下の栄光ある未来をお祈り申し上げます」
「違う」
「は?」
「いつもみたいに罵ってくれ! いつもみたいに、全てを憎んだ目で笑ってくれ! ……そんな、飾った君の言葉を聞きたいんじゃない」
「はあ……?」
心からの困惑だった。
私を虫除けに利用した代わりに、庇護者になってくれた存在でしかない王子。
「失礼ながら……頭おかしくなったんですか?」
「本当に失礼だな君は」
「だってそうでしょう。殿下が平民女ごときに頭を下げてどうするんです。示しがつきませんよ」
「まさか、まさか君が本当にあっさりと僕から消えるとは思わなかったんだ」
「身の程くらいわきまえてますよ」
「今までの狼藉はなんだったんだ!?」
「だから私、学園を無事に三年卒業したかっただけですって」
「君と別れたくない」
「頭がおかしくなってますね。救護班呼びましょう」
「やめてくれ。呼ばないでくれ。聞いてほしい」
「救護班が到着するまでの間でしたらどうぞ」
「色々すまなかった」
「はあ」
「虫除け扱いして、あれこれと憎まれ口を叩いたが……悔しかったんだ。君が僕以外の男に笑ったり媚を売ったりしているのが」
「はあ。確かに。私あなた以外と寝たことありませんけど。それなのに淫乱だの悪女だの言われるの、大分イラついてましたけど」
「知ってる、わかってる。あれは本当に言い過ぎた。僕が愚かだった」
「……なにが言いたいんですあなたは」
「君、僕の子を孕んでいるだろう」
「……」
私は返す言葉を失った。ばれていたのか。
生唾を嚥下する私に、第二王子は確信を込めた眼差しで続ける。
「わかっているよ。君に月のものが来なくなったことを。君が緩やかな服を着るようになったことも。君は僕の子供を堕胎することだって選べたはずだ。それなのにお腹を守ってくれている」
「ははあ。私が認知で強請るとでも思ってるんですね?」
私は全てを合点した。
「それが心配なら一生監視して下さって構いません。私は別に、学園を卒業してまで第二王子殿下のお情けを頂こうとも思いません。生きられればそれで」
「結婚してくれ」
「血痕?」
「僕の妻になってくれ」
「は?」
私は硬直する。反射的に周りを眺める。
「救護は」
「叫ぶな!!! 体に障るッ!!!」
「そういう問題ですかッ!」
彼は私を抱きしめて口を塞いだ。私は暴れたけれど、男の腕力には勝てない。
はあはあと息を切らし、私は体の力を抜く。
「どうするつもりなんですか……このまま殺すの?」
「殺すと思ってるのか?」
「ええ」
このシチュエーション、どう考えても私の隙をついて殺すつもりだろう。
けれどここには彼しかいない。救護班もまだこない。無能め。
「信じてくれ」
そう言うと信じられないことに、彼は私の前に跪いて服を脱ぎ始めた。
卒業式の荘厳な演奏が遠くに聞こえる学園の門の外、往来で、美貌の王子の公開脱衣ショーが始まってしまった。
「なにを世迷いごとを」
王子は真剣だった。
「僕が武器などいっさい、何も持っていないことを証明する。そして君への三年間に渡る無礼な振る舞い、妊娠させたにもかかわらずきみに一人で決断させようとしてしまったこと、全て詫びよう。謝罪文だって書く。君が蹴り飛ばしたいなら、ここで今裸の僕を蹴り飛ばしてくれ」
「そんな趣味ないに決まってんでしょ!?」
「僕にはある!」
「ふ、ふざけないで!」
私は大困惑した。信じられない。
貴族というものは、空っぽの女が好きで、平民をゴミ虫以下に見下していて、私のことも都合のよい処理係としか思っていないんじゃないのか。呆然とする私の前で下着まで脱ぎ始めたので、流石に私は王子を止める。
王子は、私を真正面から見て私の両手を握り、切に訴えた。
「突然だが聞いてほしい」
「何もかも突然ですが、なんですか」
「この国は王太子――兄が即位する予定だが、このままでは隣国に併合される」
「は?」
「隣国と我が国の違いは、社会の変革に遅れた平民と貴族の分断にある。このままでは平民はいずれ王侯貴族を襲撃し、別の存在による統治を願うだろう。事実、平民の大商人たちは次々と隣国の王弟と繋がり始めたようだ」
「…………私も隣国王弟のところに行こうかしら」
「やめてくれ」
全裸の王子は私の腕をつかみ、真剣な顔をして訴えた。泣きそうなくらい悲壮だ。
「……この学園で苦労させて悪かった。追い出された平民特待生たちを助けられなかったことは、僕は一生をかけて償っていく。最期には最悪、平民たちの投石で死んでもかまわない。でもまだ僕は死ねない」
「……なぜ」
「王子に生まれた身として、この国を浄化しなければ。立ち直らせなければ、もっと不幸な民は増える。国王と兄を蹴落とし始末し、貴族を適度に処刑し間引き、国を整え他国の脅威に対抗する」
私は目を瞬いた。
目の前の全裸の王子を信じられない気持ちで見下ろす。
はじめてまともなノブレスオブリージュを見たからだ。
「……崇高な意識の高さ、感動しますね。でもそれと私は全く関係ないのでは?」
「君が妻になってくれたら、改革はし易い。僕よりも誰よりも、君は強かで人心掌握が上手い」
「平民の女如きに好きにされる国ってどうかと思いますけど」
「ああ、もっと罵ってくれ」
「この豚、考えなし、露出狂、その上マゾヒスト」
「ああっ」
「……あなたってばほんと大丈夫?」
「君だって、このまま一人で子供を産んで大人しく過ごすつもりじゃないんだろう?」
「あら、修道院で適当に産み落として市井の平民にするつもりでしたけど?」
「衛生環境の整わない修道院での出産は五分五分で母子ともに死ぬ。君は生きろ」
「なぜ?」
「美しいから、君が」
「……ふふ」
「あと、僕の貞操を奪った責任をとってほしい、できれば」
「あっはっはっはっはっは! ああおかしいったらありゃしない」
私は彼の言葉におかしくなってきて、天を仰いでヤケクソで笑った。
「ご冗談を! 私が強奪したわけでもないのに責任を取れって」
「抱いてしまえば君が僕から離れなくなると思ったんだ」
「馬鹿おっしゃらないでください。平民女ごときが勘違いするわけないでしょう、多少手をつけられたくらいで」
「こういうやり方しか知らなかったんだよ、君を手に入れる方法が」
「そういうところです! 社会的地位の高い令息が抱いてれば女はイチコロなんて、そういう考えがこの国の腐敗を担ってると思わないんですか!」
「僕もそう思う」
「ですよね。ご理解いただけて何よりです。それではごきげんよう」
「あっ行かないでくれ。僕はダメだ。君なしでは。だから結婚してくれ」
「だあからふざけないでください、救護班なんでまだ来ないの」
「あっ蹴らないで……やっぱり蹴ってくれ」
「ええい、このこの。妊婦になんてことさせてんですか。今後火種になりそうな母子は手元に置いときたいって言われたほうが、よっぽど私を説得できますよ?」
「そう言った方が君を手元に残せるのなら、そういうことにさせてくれ」
「……疲れた……ええもう、よろしいでしょう。下手な愛を訴えられるより、打算で繋がった関係の方がよほど信頼できます」
「じゃあ契約結婚ということで?」
私は彼の前に手を差し出す。
彼は微笑みながら、目を見つめて手の甲に唇を落とした。
「契約の条件はどうする?」
「そうですね。衣食住の保証と身の安全の確保。あとは子供を愛してくれることかしら」
私の欲しいものの全てを口にすると、「お安いご用さ」と言わんばかりに第二王子は微笑んだ。
その微笑みに不覚にも――私は、生まれて初めてのときめきを見出したのだった。
「……なんか籠絡された気になって腹立つので、ちょっと殴っていいですか」
「喜んで」
「喜ぶならやめます」
◇◇◇
そんな訳で。
頭からっぽの妃を娶るべきリュート・マクイストン・デリアード第二王子は、非常に愚かにも、治安が最悪な底辺悪女を婚約者に選び、周りを丸め込んであっという間に妻にして妃に据えてしまった。
私がうっかり、学園で人心掌握してしまったのがよろしくなかった。満場一致で大反対されることを期待していたのに、私を強く強く、それはもうしつこいほど第二王子妃に推してくる勢力がそれなりにいたのだ。
「気が狂ってるわ」
第二王子の婚約者という面倒かつ出世を見込めない立場を、みんな「どうぞどうぞ」とばかりに私に押し付けて譲ってきたのかもしれない。
ともあれ、契約は契約だ。
私は息子を守るため、レイン・ノレアクリス・デリアード、第二王子の妃殿下となった。
ノレアクリスは私に心酔した公爵令嬢の家柄だ。私は正真正銘最高の血統を引く義妹ができてしまった。
そして夫リュート殿下との間に、1、2、3、4とテンポよく子供を作って妻の役目を果たした。
義両親である国王夫妻は子孫繁栄に驚き喜び、義兄である王太子夫妻は恐れ慄いた。貴族令嬢は基礎体力が衰えた女が多いので、こんなに元気にお産を続けられる女が少ないのだ。
恐れた義兄夫妻は、私と愛しい我が子に暗殺の手を回してきた。
しかし私は愛しい我が子を殺させやしなかった。夫もまた、私と子供の安全を守るという契約を守ってくれた。
果たして私たちは義兄夫婦も籠絡し、義姉さえ息子のお馬さんにしてみせた。
喜び余ってベッドにしなだれこんだ三日三晩の末、さらにもう一子作ってしまった。
そんな感じにあくまで契約と打算に満ち溢れたアットホームな家庭を築きながら、私たちは政治手腕も存分に振るった。夫である第二王子の案に反対する者は第二王子と私、二人で処刑したり追放したり黙らせたりした。
私を悪女悪妻、傾国の底辺悪女と罵る者もいた。
しかしそんな声も、いよいよ隣国の勢い盛んとなり、すわ侵攻というムードになったら静かになった。
隣国に焼かれるより「第二王子夫妻の豚になった方が人生としてはマシだ」と貴族達は判断したのだ。
なんて懸命で愚かで愛おしい羊たち。
国民――貴族も平民も皆私たち夫婦の権勢におもねり、従順で頼もしい味方となった。
隣国侵攻以前に、愚かにも義兄である王太子殿下はキレて私たちへと挙兵したが、夫に返り討ちにされて終わってしまった。
こうして夫、リュート・マクイストン・デリアード第二王子殿下は王太子殿下となり、国王陛下となり、私はその横で最終的に8人の子供をもうけた。
貴族の血が濃すぎて短命が続いていた王族は、私の底辺の血が入ったことにより随分健康に逞しく生まれ変わった。
双子が3組、一人ずつ生まれたのは長男と末娘。
育児はほぼ全て乳母に丸投げにできるとはいえ、10年近く続いた妊婦生活は流石に疲れた。
「そろそろ一緒に寝るのはやめない? リュート」
「そうだな。子を作るのはやめよう。しかしレイン。君と一緒に寝ないと落ち着かない」
「ははあ。離れていたら、何か悪さを起こしそうだから?」
「ああ、もちろんだ」
私たちは笑い皺の浮かぶようになった顔を見合わせ、笑った。
夫は歳を重ねてますます、美しく魅惑的な男になった。
胸がときめいたりなんてしない。これは更年期が近くなったから、動悸がおかしくなっただけだ。
◇◇◇
妃に求められるものは品行方正さ、頭脳明晰さ、才色兼備さ――嘘だ。
一番求められるのは血脈、容姿、そして何より頭がカラッポであることだ。
現状に疑問を覚えず、周りのプロデュースするままに振る舞い、それで不満も溜めずに妃候補として貞淑で、百発百中で男二人と女数十人、子供をぽんぽん産んで産んだハナから子供への愛着を忘れてすぐに子供を産む、公務で笑顔で手を振る。そんな女が求められている。
私は容姿は完璧、貴族社会のルールに関しちゃ頭はカラッポ――よって従順。
血脈はないかと思いきや、『平民上がりの才女』であることが逆に効果的で。
百発百中で子供をぽんぽん産んで柔軟に王侯貴族様の教育に送り出して、公務で適当な笑顔で手を振れる。なんと誹られてもそもそも余計なプライドもクソもない。
私は案外、妃に打ってつけの女だった。
◇◇◇
中年期を迎えた私と夫は、二人で久しぶりに穏やかな夕食後のひと時を過ごしていた。
長いソファに隣に座り、二人で甘い酒を飲み交わす。まるで学生時代に戻ったような気分だ。
「穏やかで平穏な統治には、君のような立役者が必要だね」
「怖いわね。あなたみたいな男が一番恐ろしいのよ」
「君がそれを言うか?」
「だって私はもう用済みでしょう? そろそろ、あなたは私を希代の悪女として糾弾して処刑だって叶うのよ?」
「はは、君を処刑するのは息子が許さないだろう。君によく似て苛烈で、僕によく似て美しいあいつが」
「そうね。あの子は世界で唯一、私が恐ろしいと思う子よ」
私たちは笑った。
お互いにとって苦労続きの人生でも、長い年月と子供たちの笑顔に丸くなり、どうでも良くなった。
結局、生き残って太々しく笑えれば、それでいい。
崇高な目標も信念もなにもない。
底辺悪女の生存戦略は、そんなものだ。
読んでいただきありがとうございます!
もしよければ、ページ下部の★★★★★クリック評価や、ブックマーク追加で応援いただけるととても嬉しいです!