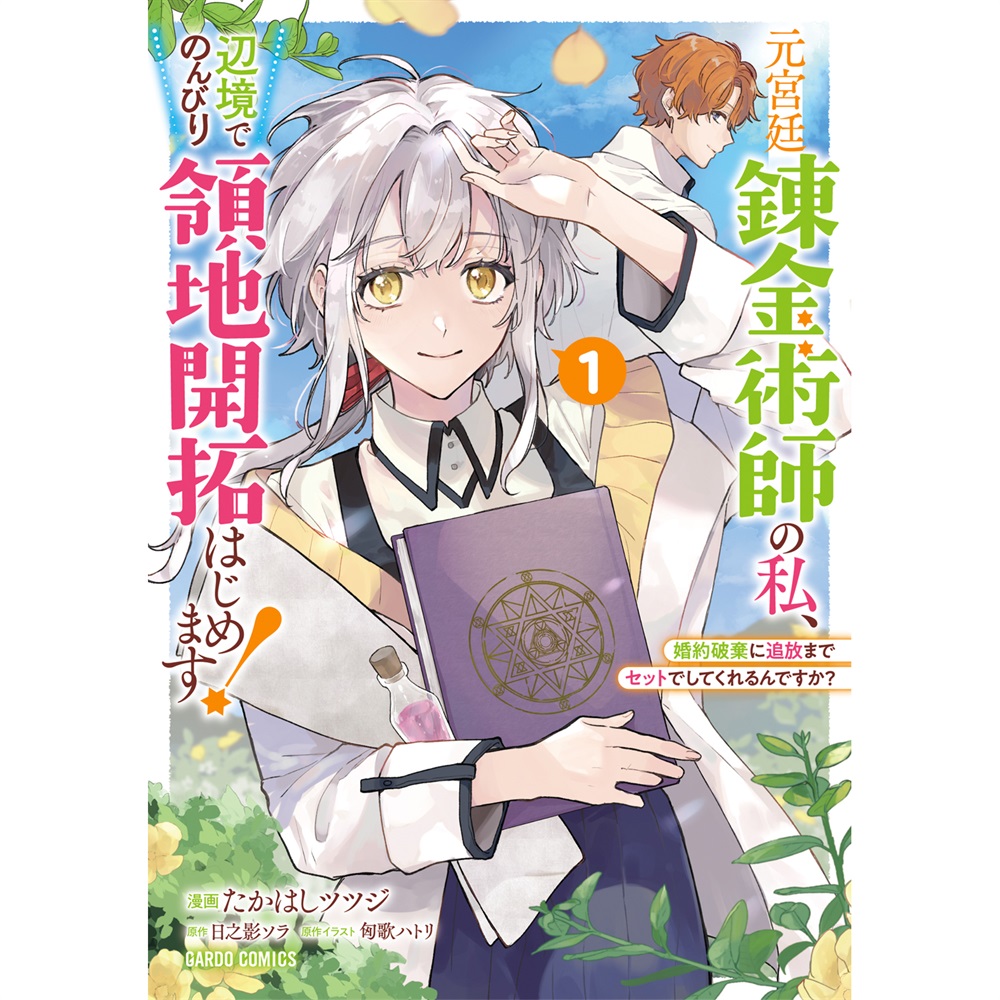«花咲か令嬢»は呪われた王子様に溺愛される ~優秀な姉に虐げられた不出来な妹だけど、素敵な王子様と出会えて幸せです~
ギフト。
それは女神より授けられる恩恵、加護。
十歳の誕生日を迎えた女性は、特別な儀式を受けることで、女神からギフトを授かる。
ただし誰もが得られるわけではない。
儀式を行ってもギフトを得られない者はいる。
女神に愛されなかった者は、その恩恵を受けることはできない。
祈り願うことで、様々な奇跡を起こす者たちを、人々は聖女と呼ぶ。
ギフトを所有しているか否か。
それは女性にとって、特に貴族たちにとって一番のブランドとなる。
貴族の令嬢ならば、ギフトを持っているのは当たり前という認識が広まり、有するギフトの性質や効果の優劣によって、貴族としての格が変わる。
爵位は同じでも、より強大なギフトを有する者が優遇される。
そしてもう一つ、ギフトを活かすための要素があった。
男性の存在である。
女神から授かるギフトは、特定の男性と共に過ごし、絆を深めることでより真価を発揮するようになる。
理屈は未だにわかっていない。
ただハッキリしていることは、誰でもいいわけではないということ。
互いが互いを求め、信頼し、共にいたいと心から思える相手であれば、ギフトは真に女神の祝福を受けるだろう。
故に、貴族同士の婚約には、ギフトの存在が大きく関わってくる。
◇◇◇
「フクシア――君と婚約する気はない」
「……」
縁談の場で、相手の男性から告げられた言葉に、私は小さくため息をこぼす。
わかっていたことだ。
何度目かわからない縁談失敗に、もはや慣れてしまっている自分がいる。
「理由は伝えたほうがいいかな?」
「……お願いします」
本当は聞きたくはない。
聞く必要すらない。
けれど、この縁談には私個人の意思ではなく、プリモワール家の、お父様の意思が関わっている。
なぜ婚約できなかったのかを聞き、お父様に報告する義務があった。
だから私はしぶしぶ、彼の言葉に耳を傾ける。
「私は期待したんだ」
彼は語り始める。
「君に、というより、君が持っているであろうギフトに」
「……」
「君の姉、アネモネ・プリモワールは優れたギフトを授かっている。有名だからね? そんな彼女の妹ならば、同等のギフトを授かっていると思っていた。でも、実際はどうだ? 君のギフトを言ってごらん?」
「私の……ギフトは……」
花を咲かせる。
たったそれだけの能力だった。
私は小さく、呆れられることを理解した上で、彼に答えた。
案の定、彼は大きくため息をこぼす。
「そう、そんなギフトしか持っていないなんて思わなかった」
「……申し訳……」
「思えば不自然だった。アネモネのように優れたギフトを有しているなら、それを公開すればいい。だが君のギフトは、関係者だけが知るように秘匿されていた。期待を持たせる演出かとも思ったけど、真実は単純だ。他人に言えないほどチンケなギフトだったってことだね」
「……」
ギフトの有無、その内容については、公開するかどうかを選ぶことができる。
これは地位に関係なく、ギフトが定めている絶対のルールの一つ。
ギフト保有者は、自らの意思で公言しない限り、伝える意思がなければ隠すことができる。
もし明かされた相手が、他の誰にも伝えないでとお願いされた場合、その願いを守る義務が発生する。
約束ではなく、義務だ。
ギフトとは女神様から与えられた特別な恩恵。
すなわち、私たちの身体には女神様の力が宿っている。
それを暴こうなどと、女神様への冒涜だ。
もしも破れば、その身をどんな不幸が襲うかわらかない。
過去、無理矢理ギフトを暴こうとしたり、約束を破った者たちは、皆酷い最期を迎えている。
故に誰も、この禁を犯すことはない。
このルールを利用することで、私のギフト内容を知っているのは、肉親と一部の人間だけに抑えられていた。
一部の人間……そう、婚約の話を持ち掛けられ、断った相手の男性たちだ。
彼らは知っている。
私が……花を咲かせるしか能のない出来損ないの聖女であることを。
どうして婚約を断ったのか。
友人にでも訪ねられたら、彼らは大きくため息をこぼすだろう。
「はぁ……もっと早く気がつけばよかった。そうすればこんな無駄な時間……」
「御足労いただいたのに、申し訳ございません」
「まったくだよ」
彼は呆れてやれやれと首を振っている。
期待外れだったと。
だけど、最初に婚約の話を持ち掛けたのはそっちだ。
いつも同じ。
私のギフトに期待して、優秀な姉の妹だからと、縁談を男性側から申し込んでくる。
そして対面し、ギフトについて聞かれて答える。
縁談の場は、男女が互いに添い遂げるかもしれない相手を選ぶ場だ。
この時点は互いに、婚約するかもしれないという意思がある。
それ故に、こういった縁談の場では、ギフトについて尋ねることがマナー違反にならない。
別に聞くだけなら罪にはならない。
嫌なら答えなければいい。
彼らの問いに強制力はないのだから。
しかし婚約をするためにも、私たちはギフトを明かすことが必要になる。
貴族にとってギフトは、それだけの価値がある。
私がギフトの内容を伝えると、期待の視線は一気に絶望へと変わる。
いつものように。
そうして少しだけ話して、結論は婚約不成立だ。
彼は席を立ち、出口の扉に向かおうとする。
「本当に無駄な時間だったよ」
「……ギフトのことですが、他言無用でお願いします」
「わかっているよ。誰にも言えない……君も大変だね? チンケなギフトを授かってしまったことには、心から同情するよ」
「……ありがとうございます」
一体、私は何に対して感謝の言葉を告げたのだろう。
去っていく男性を見送りながら、私は現実から目を逸らすように、窓の外を見つめる。
女神様?
どうして、こんな恩恵を私に与えたのですか?
◇◇◇
プリモワール公爵家。
それが私の生まれた貴族の家系。
ユグドラシル王国でも王族に次ぐ有力な貴族の家柄であり、代々優秀なギフト保持者を生み出している。
母は祈るだけで天候を変えることのできるギフトを持っていた。
祖母は植物を自在に操るギフトを持っていたらしい。
その前の世代も、プリモワール家で生まれる女性は、頭一つ抜けたギフトを授かってきた。
故にプリモワール家は、王家の次に女神様に愛された一族、と呼ばれていた。
当代には二人の女性が誕生した。
一人はアネモネ・プリモワール。
私の一つ上の姉であり、彼女は女神に祝福されていた。
有するギフトは火炎と熱を自在に行使する。
彼女の祈りは極寒の大地を正常に戻し、寒さに震える人たちに温かさを与える。
炎は獰猛な肉食動物、魔物から人々を守護する力でもある。
文明の発展、人々が今の時代を築くために、炎との出会いは不可欠なものだった。
そんな始まりの炎を司る彼女は、プリモワール家の名に恥じない令嬢だ。
だけどもう一人、一つ下の妹は不出来だった。
有するギフトは、花を咲かせるというチンケな能力。
ただ花を咲かせるだけで生産性はない。
綺麗な花を愛でるだけなら、わざわざ祈らずとも、丁寧に栽培すれば花は咲く。
ギフトは女神様から与えられた恩恵だ。
故にギフトを持っているというだけで、女神様から祝福を受けた選ばれし乙女、という認識になる。
本来ならば。
「失礼します、お父様」
「フクシアか」
縁談を終えた私は、当主のお部屋でお仕事をしているお父様の元へ足を運んだ。
目的はもちろん、縁談の結果報告だ。
言うまでもなく失敗。
お父様も予想しているから、あまり期待していないのがわかる。
私は報告した。
今回も、婚約には至らなかったと。
するとお父様は小さくため息をこぼし、走らせていたペンを止める。
「フクシア、これで何度目かわかるか?」
「……いえ」
失敗の数なんて数えていない。
嫌になるから。
「十を超えた。縁談を申し込まれ、拒否される。もう聞き飽きた」
「……申し訳ありません」
私だって、同じだ。
好きで縁談をしているわけでも、望んで断っているわけでもない。
向こうから持ちかけ、向こうから拒否をする。
もう、うんざりだった。
「はぁ……お前が先に婚約を決めれば、アネモネもよい刺激を受けると思うのだが……これでは汚点を増やすだけだ」
「……」
お父様の憂いは、私だけに対するものではなかった。
お姉様の性格のこともある。
けれどそんなこと、私には関係ない。
「報告は受け取った。次の縁談相手が見つかるまで大人しくしていなさい」
「はい」
この家で、私に自由はなかった。
私のギフトが他に知られないように、無能だとバレないように。
屋敷の外に出る機会は最小限で、基本的に一人では出歩くことが許されない。
縁談以外で、家の外の人と関わる機会もほとんどなかった。
私はプリモワール家の汚点と呼ばれている。
不出来な娘を生んでしまったせいで、母は心を病んでしまった。
以来、私は母とまともに顔を合わせていない。
屋敷の中ですら、行動範囲は制限されていた。
ここは私にとって牢獄だ。
そんな中、唯一私が癒される場所は……。
「お待たせ、みんな」
屋敷の裏庭にある小さな花壇だった。
私が両手を広げてちょうどの広さ。
決して大きくはない花壇に、色とりどりの花が咲いている。
私が祈りを捧げることで、花たちは咲き誇る。
水がなく、栄養がなくとも、私の祈りだけで花は咲き続け、枯れることはない。
それこそが私に許されたギフト、女神様の祝福。
この場所だけが、私にとっての聖域だった。
でも、そんな聖域ですら……。
「あら? もう縁談は終わったのかしら?」
「――!」
「結果はどうだったの? って、聞くまでもないわよねぇ。フクシア」
「……アネモネお姉様……」
安らかな時間を壊すように、彼女は無造作に踏み入ってくる。
アネモネ・プリモワール。
私の実の姉が、花たちを愛でていた私の元へとやってきた。
その笑みは私をあざ笑う。
「あなたと婚約したいなんて物好き、いるはずがないわよね? なんたって、そんなことしかできない無能なんだから」
「……」
お姉様は花壇に指をさし、私のことを罵倒する。
私のことを悪くいうのはいい。
もう慣れている。
けれど、花たちを馬鹿にされているみたいで、いい気分じゃなかった。
「縁談を断られてすぐ花いじりなんて、つくづく可哀想な子ね」
「……何かご用でしょうか? お姉様」
「別に、ただ暇だったから見にきただけよ」
「縁談はどうされたのですか? お姉様も確か」
「あんなのとっくに断ったわ」
お姉様は呆れてため息をこぼしながら即答した。
優れたギフトを持つお姉様の元には、私なんか比べ物にならない数の縁談が舞い込んでくる。
炎を司るギフトは、誰もが求める特別な力だった。
多くの貴族たちが、名のある家名の者たちが、お姉様に言い寄る。
そして、悉く惨敗している。
「お姉様は……婚約する気はないのですか?」
「そんなの私の勝手でしょう?」
「……」
「私はね? フクシア、あなたとは違って選ぶ立場の人間よ!」
彼女は自分の胸に手を当てて、自信たっぷりな笑みを浮かべる。
「私が誰と婚約するかなんて、私が決めることよ! 私がいいと思った相手以外は全部ダメね。縁談でもいいけど、運命を感じさせる相手じゃなきゃ会う価値すらないわ」
「……そう、ですか」
お姉様はロマンチストだった。
乙女の理想、誰もがうらやむような相手と、運命的な出会いで引きあい、恋に落ちる。
彼女の好みにかすりもしなければ、縁談の場すら用意されない。
期待されて縁談まで持ち込めても、彼女は平然と一目見ただけで、あなたじゃないと断る。
そんな自分勝手な態度でも許されるのは、優れたギフトを持っているから。
お父様の憂いはここにある。
お姉様がこんな調子だから、成人しても中々相手が見つからない。
彼女が縁談を断った相手は、次に私をターゲットにする。
お姉様が無理なら、せめて妹の私を……という思考だけど……。
残念ながら私が不出来だと知って、みんな呆れて帰ってしまう。
今日と同じように。
「お姉様は、どんなお相手なら婚約をしたいと思われるのですか?」
「何? 今日はずいぶんとよくしゃべるわね」
「――! すみません」
お姉様が婚約してくれたら、お父様も少しは安心する。
プリモワール家の未来も明るい。
そうなったら、無理に私を婚約させようとしなくなる、かもしれない。
一瞬過った思考が影響して、私は普段口に出さないことを聞いてしまった。
お姉様は婚約のこと、自分のことを詮索されるのを嫌う。
「まさかと思うけど、あなた……私に意見しようとしたのかしら?」
「そ、そんなことは」
「そうよね? こんなお遊びしかできない愚妹の分際で、私のこと心配しているの? 烏滸がましいわよ!」
「――!」
お姉様を怒らせてしまった。
怒りの矛先は私ではなく、私が大事に育てている花たちへと向けられる。
ギフトによって生み出された炎と熱が走り、花たちを一瞬で燃やしてしまった。
「あ、ああ……」
「ふんっ、私、花って好きになれないのよね? 汚い虫しか寄り付かない。あ、まるであなたみたいね? フクシア」
「……」
なんてひどいことをするのだろう。
花たちに何の罪があるの?
綺麗に咲いて、私たちの心を癒してくれる花たちは、無残にも灰と化してしまった。
私は膝をつき、悲しさに涙が出そうになる。
「いい気味ね。あなたは一生、そうやって地面と仲良くしているといいわ」
冷たい支援と言葉を残し、お姉様は私の元を去っていく。
お姉様が屋敷の中へ入るまで待って、私は灰になってしまった花たちに囁く。
「痛い思いをさせてごめんね?」
両手を胸の前で組み、瞳を閉じて祈りを捧げる。
私のギフトは花を咲かせる。
それしかできない。
でも、それならできる。
たとえ枯れてしまっていても、灰になっていても、それが花であるのなら――
咲き誇る。
灰になった花たちが光り輝き、美しい花へと修復されていく。
灰になっても完全に消滅しない限り、ここに花があると私がわかっている限り、なんど踏みつけられ、燃やされても消えはしない。
お姉様もわかっている。
だから余計に、苛立って花に八つ当たりをするのかもしれない。
花からすればいい迷惑だ。
この花たちは咲いているだけで、何も悪いことはしていないのだから。
「本当にごめんね? 辛いことばかりで」
堪えていた涙が、一滴だけ落ちる。
花弁に落ちた涙の雫は、吸い込まれるように花の中に消えていく。
私は一体、いつまでこんな日々を続ければいいのだろうか。
いつになったら解放されるのだろう。
私は……。
「幸せになれるのかな?」
◇◇◇
プリモワール公爵は頭を抱えていた。
優秀な姉は縁談を断り続け、未だに夢見がちなことを言っているらしい。
不出来な妹に縁談の話を回しても、結果は悉く失敗する。
プリモワール家には女性の跡取りしかいなかった。
それ自体は問題ない。
ただ、優秀なギフトを持ちながら、相手が決まらないということが問題なのだ。
「フクシアはともかく、アネモネもいい加減……はぁ……」
苦労は絶えない。
不出来な妹を生んでしまったことで責任を感じ、彼の妻は精神的に不安定になってしまった。
それを隠すように、妻を屋敷に閉じ込めている。
世間にはただの体調不良であり、元々病弱だったということにして。
なんとかしなければ。
そう思いながら、今日も彼は縁談相手を探していた。
「――! これは……」
テーブルの上に並べられた手紙の中で、一枚だけ目立つものがある。
記されていた縁談相手は……。
「第二王子……ローワン殿下?」
思いもよらぬ相手からの縁談。
アネモネも王子が相手であれば満足するだろう。
ただし第二王子には様々なよくない噂があり、表舞台にはあまり現れず、彼も面識が薄い。
珍しいことに、相手の指定がされていなかった。
基本的にはアネモネかフクシア、どちらかを指名しているのだが……。
「どちらでもいいというのか? 何をお考えだ?」
思考をめぐらすがわからない。
一先ずアネモネに意思を確認し、その結果次第でフクシアに声をかけることにした。
おそらくは、ダメもとでフクシアに縁談を受けさせることになるだろう。
そう考えていた。
◇◇◇
翌日。
プリモワール公爵はアネモネに縁談の件を伝えた。
答えはもちろん……。
「お断りしますわ」
「アネモネ」
「当然じゃありませんか! 王族から縁談なんて驚きましたけど、相手が第二王子ですよ? ローワン殿下といえば、不治の病に侵されていて、ほとんど部屋から出てこないそうじゃないですか」
ローワン・ユグドラシル。
第二王子である彼は、幼い頃から身体が弱く、表舞台には現れない。
現在はニ十歳になり、婚約者を決めるにはちょうどよい年代ではあるが、不治の病にかかり、先が短いと噂されている。
中には、王子は呪いにかかっているのでは?
などという噂まで立っていた。
それでも相手は王族、もしも縁談が上手く運べば王家の一員となれるチャンスだ。
多くの貴族たちが、王族と深い関係になることを目的に縁談を申し込み、未だ婚約には至っていない。
「そんな方と婚約なんて絶対にありえません!」
「そういうな。今回はあちらから縁談の話を持ち掛けてくださった。こんなこと他の家にはなかったことだ」
「だから何ですか? 婚約なんてしませんわ」
「それでも構わない。一度、顔合わせだけでもしてくれないか?」
せっかくの機会、チャンスではある。
プリモワール公爵も必死だった。
一度顔を合わせれば、アネモネも気が変わるかもしれない。
それにかける気でいた。
「はぁ、仕方ありませんね。お父様がそこまでおっしゃるなら、縁談には出席します」
「ありがとう。いい知らせを待っているよ」
「あまり期待しないでください。私は婚約する気はありません」
◇◇◇
縁談当日。
夕刻になり、結果を心待ちにしていたプリモワール公爵の元に、思わぬ知らせが飛び込んでくる。
怒り心頭のアネモネと共に。
「どういうことですか! お父様!」
「な、何があったのだ?」
「何があったじゃありません! 縁談を持ち掛けたのはあちらでしょう! それなのに、顔も合わせてくれないというのはどういうことなんですか!」
「なっ……」
プリモワール公爵も予想外のことだった。
アネモネが怒るのも理解でいる。
縁談を申し込んだ相手側が、殿下自身が会うことを拒んだらしい。
結果、アネモネは王城へ出向いただけで、何もすることなく帰ってきた。
「二度と王家からの縁談なんて受けません!」
「あ、アネモネ!」
怒ったアネモネは部屋から出て行ってしまう。
こればかりは反論もできない。
公爵は頭を抱える。
「何をお考えなのだ……殿下は」
さらに翌日。
思わぬことが起こる。
プリモワール家に縁談の申し込みがあった。
「どういうつもりだ?」
相手は同じく、ローワン第二王子である。
プリモワール公爵も顔をしかめる。
一度反故にしておいて、再び縁談を申し込む意味がわからない。
しかし意図はわからずとも、二度目のチャンスであることに変わりはなかった。
「アネモネは……無理だな」
二度目はない。
ならば必然、不出来な妹を差し出すことになる。
こうしてフクシアと、ローワンの縁談が決まった。
◇◇◇
一台の馬車が王城の敷地内に入る。
馬車が停まったのは、敷地内にある小ぶりの屋敷前だった。
「到着しました。フクシア様」
「ありがとうございます」
私はローワン殿下との縁談のため、王城へとやってきた。
ただし案内されたのは王城ではない。
貴族の屋敷にしても小ぶりな家に、ローワン殿下は暮らしている。
ローワン殿下……。
いろいろな噂が聞こえてくるけど、一体どんなお方なのだろう。
「ううん、どんなお方でも……」
結果は同じだろう。
私と婚約することなんてありえない。
どうやらお姉様とも縁談を場を設けて、会うこともできなかったそうだ。
お姉様でそれなら、私なんてもっと可能性が低い。
私は屋敷の使用人に部屋の前まで案内された。
使用人が中にいる殿下に呼びかける。
「ローワン様、フクシア様がお見えになられました」
「……」
「ローワン様」
「言ったはずだ。俺は縁談など受けるきはない。帰ってもらえ」
聞こえてきた男性の声は、私のことを拒絶する。
おそらくお姉様の時と同じように。
使用人の方も困っていた。
「す、少しお時間をあけてまた伺ってみましょう」
「はい」
「それまでご自由になさられてください」
と、使用人の方に言われた私は、なんとなく屋敷の中を歩いて回る。
身体が弱いというのは事実なのだろうか。
声しかわからない状態じゃ、予想することもできない。
どちらにしろ、縁談は失敗だ。
このまま戻れば、またお父様に呆れられて、お姉様には馬鹿にされるだろう。
「はぁ……」
ため息を一つ。
すると、外からの風を感じた。
窓の外を見ると、そこには花壇があった。
気になった私は外に出る。
花壇には花が植えられていた。
けれど、一輪も咲いていない。
すべて枯れてしまっている。
放置されていたのだろうか?
いいや、よく見ると手入れはされているようだった。
「可哀想に……」
花が、というのもあるけど、この花を育てた人が可哀想だった。
私はギフトの影響で、花からいろんものを感じ取れる。
この花たちは、誰かが咲いてほしいと願って植えられたものだ。
手入れされた土壌、水やりもきちんとされている。
咲いてほしかったはずだ。
「どうか。咲きますように」
私は祈りを捧げる。
大切に育てた誰かの代わりに、私がその思いを実現させよう。
これしかできないから。
祈りを捧げると、綺麗な桃色の花が咲いた。
なんという名前の花だろう。
その時、ばたんと大きな音が鳴った。
屋敷の窓が開いた音だ。
「――! な、何?」
あの部屋は確か……。
ドタバタと走る音が聞こえて、一人の男性が花壇にやってくる。
息を切らし、銀色の髪をなびかせて。
「こ、これは……」
「――ローワン殿下?」
扉の向こう側から聞こえた声だ。
間違いない。
彼が噂の、ローワン・ユグドラシル第二王子。
「花が咲いている? 君がやったのか?」
「あ、はい。す、すみません!」
勝手に花壇をいじってしまった。
ローワン殿下が育てていた花だったのだろうか。
慌てて謝る私に、殿下は驚きながら言う。
「ありがとう!」
「……え?」
思わず声に漏れる。
怒られるとばかり思っていたから。
「自分ではどうしても咲かせることができなかったんだ。その花は、母上が大好きだった花なのに……」
「王妃様が……?」
現国王の妃、彼の母親はすでに亡くなられている。
数年前に病死されたと公表された。
それはちょうど、ローワン殿下が不治の病に犯されているという噂が、囁かれ始めた頃だった。
「本当にありがとう! 君のおかげで、またこの花が見られた」
「え、あ……」
彼は私の手をぎゅっと握り、心からの感謝を伝えてくる。
聞いていた話と違う。
不治の病に侵されているという話だったけど、見るからに元気そうだった。
「――! す、すまない!」
殿下は唐突に手を放す。
そうして焦ったような表情を見せた。
「触れるつもりはなかった。つい嬉しくて、これで君に不幸が訪れたら……俺はなんて恩知らずなんだ」
「不幸? なんのことですか?」
「……この身体は、呪われているんだよ」
「呪い!?」
ふと、あの噂を思い出す。
ローワン殿下は呪いを受けている、と。
「君は、フクシア・プリモワールだね?」
「はい」
「少し話そうか。せっかく来てもらったんだ」
「は、はい」
理解が追いつかないまま、私はローワン殿下に案内されて屋敷の中に戻る。
使用人も驚いていた。
すぐに飲み物を用意して、私は殿下と一室で向かい合って座る。
「縁談は俺の姉が勝手に申し込んだものなんだ」
「……え?」
唐突に話は始まった。
出された紅茶をお互いに一口飲んだ後だった。
殿下は続ける。
「ずっと屋敷に籠っている俺を見かねてか。あの人は普通の人間には見えないものが見えているからな。何か感じたのかもしれない。ただ、俺は縁談を受ける気がなかった」
「だから、お会いになられなかったのですか?」
「ああ。もう一人縁談にきたね? 君のお姉さんだったか」
「はい」
「彼女にも悪いことをした。だけど、俺なんかとは会わないほうがいい。呪いをうつすかもしれないからな」
彼は自分が、呪われていると思っている。
呪いについては諸説あり、未だ明確に解明されていない。
ただの病でも怪我でもない。
医学や魔法、あらゆる学問で説明できない現象を呪いと呼んでいる。
殿下の身体は生まれながらに病弱だったわけではない。
「ある日突然だ。身体が重くなった。今も鉛のように感じる。それだけならよかった。俺一人の問題なら……」
「殿下?」
「俺は、誰かと関わっちゃいけない。一緒にいると不幸にする。母上も、俺と一緒にいたせいで病気になった」
「それは……」
「皆は否定してくれるけどね? 俺は自分のせいだと思っている。あの花、俺が触れると育たずに枯れてしまうんだよ」
殿下は悲しそうな表情で笑う。
本当に切なくて、泣き出しそうな顔だった。
「だから諦めていたんだ。でも、君が咲かせてくれたね」
「それしか、私にはできませんので」
「ギフトか?」
「はい」
「素敵なギフトじゃないか」
「え……」
キョトンとした顔で私は殿下と視線を合わせる。
殿下は優しく笑ってくれていた。
「君がいたから、あの花は咲いた。母上が大好きな、俺にとっても大切な花が……心から感謝している」
「いえ、その……」
「フクシア、だったね? 君がいてくれてよかったよ」
「――!」
生まれて初めての体験に、心が躍動する。
いつも選ばれるのは、求められるのは姉だった。
認められたことなんて一度もない。
素敵なギフトだなんて、言われることはないと思っていた。
「フクシア?」
「す、すみません……嬉しくて」
涙が溢れていた。
殿下の前で情けなく、私は泣いていた。
「婚約の話、受ける気はなかった」
殿下が語り始める。
「お互いのことを何も知らない。一緒にいても不幸にさせてしまう。でも、初めてだ。もう少しでいいから、話していたいと思ったのは」
「殿下……?」
「フクシア、もし君が許してくれるなら、俺と友人になってほしい」
「友人……私が、殿下と?」
殿下は小さく頷く。
「婚約するかどうかは、もう少しお互いのことを知ってから考えたい。もちろん、君にその意思があればなんだけど」
「――はい。私も、殿下のことを知りたいです」
初めてをくれた人に。
私のギフトを、私の存在を、肯定してくれた人だから。
「これからよろしく、フクシア」
「はい。殿下」
こうして、私たちは出会い、友人になった。
◇◇◇
お父様もひどく驚いていた。
婚約自体は保留になったけど、ローワン殿下と関わりを持てたことを。
あの日以来、何度も屋敷に招待された。
「君と一緒にいると、なんだか調子がいいんだよ」
「本当ですか?」
「ああ。なんでだろうな? 君が咲かせてくれた花たちが、俺の中の悪い呪いを追い払ってくれたのかも、なんて」
そう言って恥ずかしそうに殿下は笑う。
「君のほうは平気か? 俺に触れて不幸なことにはなっていないか?」
「はい」
ところが、私はずっと幸せな気持ちだった。
屋敷の外に出られる。
誰かと長く会話するのも、私にとっては特別で、こんなにも和やかに、明るい話ができる相手なんて生まれて初めてだ。
不幸なんて微塵もない。
幸福ばかりもらって、いいのかと思える。
殿下の体調にも変化が現れていた。
気分的にじゃなく、実際に体調が回復し、人前に出る機会が増えていた。
そんな中、殿下も参加されるパーティーに、私はお姉様と共に参加することになった。
会場にはたくさんの貴族たちが集まる。
元気になりつつある殿下は人気者で、多くの人に囲まれている。
近づきたいけど、邪魔をしてはいけないとも思った。
「よくやったわ。フクシア」
「え?」
隣でお姉様が笑う。
「今の殿下なら、私とも釣り合うわ」
「何を……」
「お膳立てありがとう。あとは私に任せなさい」
そう言ってお姉様は殿下の元へと歩み寄っていく。
姉妹だから、散々馬鹿にされていたから、お姉様の考えていることがわかってしまう。
体調が回復し、王族として表に出られるようになった今のローワン殿下を、自分のものにしようと考えている。
颯爽と歩き出し、彼女は殿下の前に立つ。
「君は……」
「初めまして。アネモネ・プリモワールです」
「ああ、君が彼女の。先日はすまないことをしたね」
「いえ、体調も回復されたようで何よりです。いかがでしょう? 今度一緒にお食事でも、二人で」
周囲がざわつく。
お姉様も有名人で、これまでいくつもの縁談を断っている。
そんな彼女からのアプローチに多くの男性が驚く。
しかし相手は王子だ。
誰も、何も言えない。
私も……。
このままお姉様と殿下が親しくなって、婚約したら?
嫌だ。
心からそう思う。
けれど、私のような人間が一緒にいると、殿下が笑われてしまう。
私が殿下を不幸にしてしまう。
それなら……。
ふと、視線が合う。
殿下と。
「そういうことか」
「ローワン殿下?」
「すまないが、そういうお誘いは断ることにしているんだ。俺には心に決めた人がいるからね」
「え?」
彼はお姉様の隣を通り過ぎる。
君ではないと告げるように。
そして――
君だと告げるように。
「フクシア、俺と婚約してくれないか?」
私の前に歩み寄った殿下は、優しく微笑みながらそう言ってくれた。
大勢の前で、婚約を申し込む。
「私で……いいのですか?」
「君がいいんだ。君と一緒にいると、心も体も温かくなる。そんな君だからいい。君が嫌じゃないのなら、どうか俺と――」
嫌じゃないか?
そんなの、答えはとっくに決まっていた。
私は遠慮がちに伸ばした彼の手を握る。
「はい! 私は幸せ者です」
触れると不幸になる?
そんなことあるはずがない。
だってこんなにも、満ち足りた気持ちになるのだから。
まるで、私の心の中で、満開の花が咲き誇るように。
【作者からのお願い】
ご愛読ありがとうございます!
いかがだったでしょうか?
少しでも面白い、続きが気になると思って頂けたら、ぜひとも評価★を頂ければ幸いです。
ブックマークもお願いします!
またまた新作投稿しました!
タイトルは――
『勇者敗北が私の責任って本気ですか? そう思うなら追放してください! ~ムカついて聖剣を魔剣に変えたら敵国の魔王様にバレて溺愛されるようになりました……なぜ??~』
ページ下部にもリンクを用意してありますので、ぜひぜひ読んでみてください!
リンクから飛べない場合は、以下のアドレスをコピーしてください。
https://ncode.syosetu.com/n2603ik/