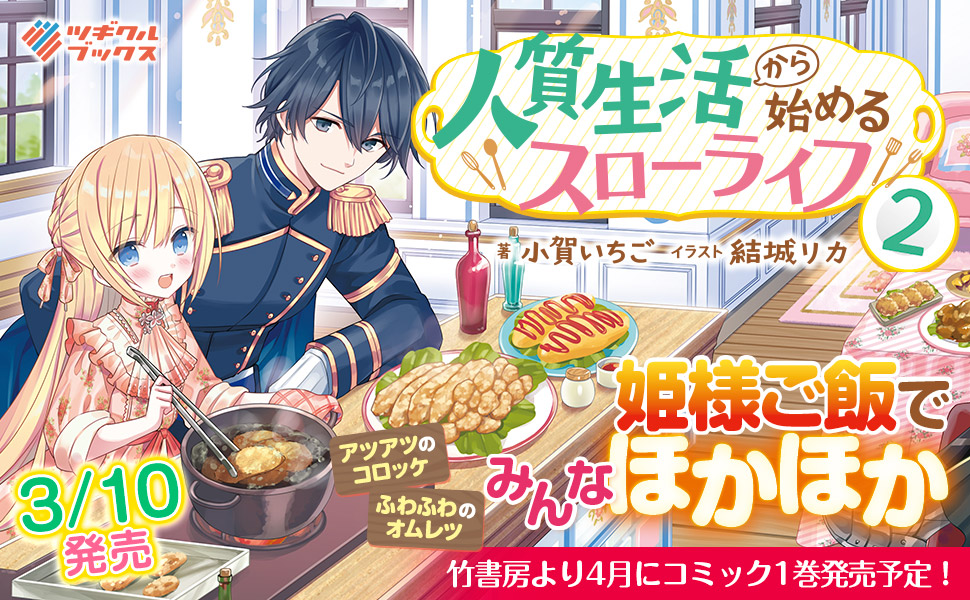変化の兆し
一人の男が王宮の執務室へ向かって足早に進んでいた。廊下を歩く侍従や侍女達は立ち止まり、頭を下げている。その事から身分のある人間だと言う事が理解できる。
執務室の前に立ち止まり入室の許可をもとめると、ほぼ同時に許可が出た。普段から出入りをしている事が見て取れる。
入室し、ためらうことなく机に向かう。
その前に立つと書類にサインをしている男性に話しかける。
「陛下、最近の城下町の事をご存知でしょうか?」
「何があった?宰相。珍しいな。私にそんな事を聞くなんて」
普段から無駄口を叩くこともなく、物事を簡潔にする宰相は質問形式の話をしない。
その宰相がこんな話をするという事は自分自身でもどう話したものか決めかねており、よく分かっていないのだろう。
私はサインをしながら宰相を見る。
こんな様子は珍しい…何があったのか?
私からも問いかけたのに返事をしないなんて
明日は雪か?季節的には暖かくなり始める頃だが…
目の前の男がらしくない反応をするため私も戸惑っていた。
その男がやっと口を開く。
「実は城下で新しい料理が流行っているそうです。」
「そうか、それがなんだ?」
城下の流行は珍しいことではない。大体は貴族から流行りだし、それが城下に普及する形だ。
「ん?料理か?最近、私は新しい料理を食べた覚えはないぞ?」
「そうなのです。どうも城からの普及ではないようです。」
「国外のものか?」
「違うようです。どうも城に出入りしている商人の店からのようで…」
「城に出入りしているのか?それなのに私達が知らないと…おかしいな…」
宰相の戸惑いの理由が何となくわかってきた。
新しい料理は文化と富の象徴だ。王宮から発信されるものでなければならない。 それなのに私たちが知らないと?そんな事はあり得ないし、あってはならない。
王宮の長と言うことは国の長でもあるからだ。
文化の象徴は権力の象徴でもある。それを国の長が知らないのは問題だし、知らないふりをする事はできないし、許されない。気の緩みは規律の緩みに繫がるからだ。
たかが料理と馬鹿にするわけには行かないことだった。
私達が知らない理由があるとすれば、海外からだ。その場合は国外の水夫や観光に来たものが宿で頼んで作ってもらったりする事で広がることもある。しかしそれも違うと言う。
「はい。私も不審に思いまして調べてみました。どうも離れの姫様が関わっているようです」
「姫が?なんでだ?」
「わかりません」
離れの姫が関わっている?9歳の姫が?商人と?
そんなコトがあるのか?
「侍女達は何と?」
「まだ、そこまでは…どうしますか?他国の姫なので陛下の判断を仰ごうかと…」
「そうだな、間違いがあれば面倒だ」
「はい」
離れの姫は留学生として預かっている。まだ学校ヘは通っていないがいずれ通うことになるだろう。
私が忙しく、あまり気にかけていられないのも問題だと思っているが、姫が気にしている様子はなかった。気むずかしい姫ではないので助かっている。
年に数回しか話すことはないが、聡明なのはすぐにわかる。相手への気遣いも言葉使いも子供のものではない。礼儀もだ。自分から留学したいと希望したのも納得できる聡明さだ。
侍女たちからも特に問題になるような報告は上がってきていない。
しかし姫がなぜ商人と関わっているのか…
繋がりなどできようはずもないが…