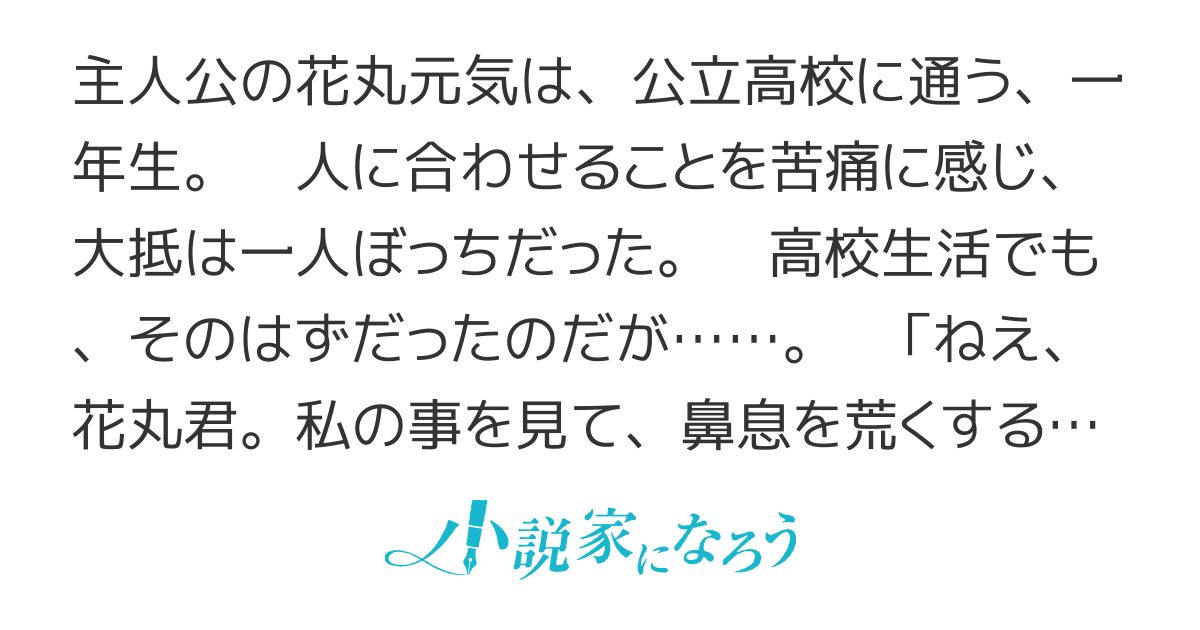お疲れサマー
梅雨が明けてから久しい。
梅雨前線が暇を告げるやいなや、日本列島は連日猛烈な暑さに見舞われていた。
登校中に自転車を漕いで噴き出すように出てくる汗を、地面にポタポタと垂らしながらも、「暑い」と文句一つ言わずに昇降口をくぐり抜ける。正確には文句を言わないのではなく、時候の挨拶をする相手がいないから押し黙っているに過ぎないのだが。それはそれ。
教室に入ればクーラーはあるが、中庭で今日も恐ろしいほどに唸りを上げている、業務用空調機の室外機を見るに、あまり期待しないほうが良さそうだ。大体教室というものは人口密度が高すぎるのだ。
七月も中旬に入り、夏休みも近い。
俺と星ヶ丘、そして祖父江の三人で放送部でグダグダやっているうちに、いつの間にか一学期の終わりが間近に迫っていた。
目下注力すべきであるはずの星ヶ丘との関係構築は一進一退でさしたる進展を見せていない。
二人でどこかに遊びに行ったりということもなく、漫然とした日々を過ごしていた。
いや、俺としてはこのまったりとした日常を過ごすことで、星ヶ丘の傷が癒え、ゆっくりと着実に愛を育もうとしていたに過ぎないのだが、そんな状況に祖父江さんがご不満のようなのだ。
俺の顔を見るたびとかく「告れ告れ」と囃すのだ。
その度
「俺は王道を行くのだ」
と答えた。
「日和ってるだけだろ」
と祖父江さんは無垢なる乙女には相応しくない口調で俺を野次った。
「万難を排し使命を全うするのは無論のことである。しかしそれには如何なる障壁もあってはならないのだ。俺は俺の正道を以って後顧の憂いを断ち、全身全霊の愛を世界の中心で叫ぶ所存である」
と主張した。
しかし祖父江はすぐさま
「語るに落ちるわ、童貞め」
とさらに苛烈な野次で俺を追い詰めた。後生大事に純潔を守っている少年に真実を告げるとは、祖父江杏というおなごは鬼に違いない。童貞の呼吸壱の型「女子と目を合わさない」が炸裂した。
そんなことを思い出し苦汁顔をしながらも、確かに時間を掛け過ぎている感は俺にもあった。いくらクラスでの立場が危うくなった星ヶ丘とはいえ、彼女ほどの美人が、発情期の高校生にずっと狙われないこともないだろう。
彼女が程度の低い軟派者に狙われては大変だ。彼女を幸せにしてやれるとしたら、俺以外にいないはずだと、俺は勝手に思っているが、そんなこともないのかもしれないのかもしれないが、そういうことにしておく。
兎も角そろそろ駒を進める時だ。甘酸っぱい恋は夏にするものだと、少女漫画が教えてくれた。
今日あたりさりげなく告白でもしておくか。気安く頼めば、気安くOKしてもらえるかもしれない。
俺が教室に入ってすぐそこの席に荷物を置けば、すでに来ていた星ヶ丘が
「おはよう」
と挨拶をしてきた。
俺は隣の席にちょこんと行儀よく座っている彼女に挨拶を返す。
しかし自転車を全力で漕いで、かつ階段を駆け上がってきたから、俺は息を切らしていた。
それを見て彼女は
「どうしてハァハァしてるの? いくら私に会えるのが嬉しくても、そこまで興奮することはないと思うけれど」
と不思議そうな顔をした。どうしてそうもナチュラルに不思議そうな顔ができるのか。
「いやぁ、暑い暑い。暑くて敵わん」
俺は弁明する代わりに、シャツを扇ぎながら、ここまで我慢していた言葉を言った。
「あら、あなたが私にお熱なのは入学してからずっと変わってないでしょう」
「……要するに熱が熱を呼んで、俺とお前で危ない恋の化学反応ってことか?」
「どうしましょう。尾張旭くんの脳味噌が超臨界状態に達してしまったようだわ」
「分かる。星ヶ丘と俺の間にある心のバリアはもはや見えなくなり、今ここにある精神世界に於いては、俺を俺たらしめる膜も、お前をお前たらしめる膜も極めて曖昧なものになっているもんな。もはや俺たちは客観的に判別できないレベルで混じり合っているんだ。要するに俺はお前であり、お前は俺なんだ。結婚しよっか」
愛とは粘膜の接触であると言うが、ひょっとしたら異なる二者の精神世界が超臨界流体になることを、膜の崩壊及び融合と捉え、粘膜の接触であると断じたのかもしれない。
命題解決の足掛かりを得たことに対し、俺が喜びを禁じ得ないでいたところ
「ごめんなさい。ちょっと何を言ってるか分からないです」
星ヶ丘は眉を顰めて言った。
「宜なるかな」
「何が言いたいの?」
「星ヶ丘にはまだ、絶対不可侵領域を拓く勇気はないようだ」
星ヶ丘は「どこかで頭でも打ったの? それとも熱中症? 意識レベル正常?」と心配するような視線を向けてきたが、俺は気にせず続けた。
「もちろんお前は肉体的にも精神的にも清らかであろうが、それが故に精神世界の融合、すなわちエロスを超えたアガペーを享受する貪欲さも持ち合わせていないのだろう。
純潔さのために本物の愛を恐れるからと言って誰がそれを非難できようか。エロスを知らずにアガペーを知るのも難しいことだからだ。真実の愛を追い求める心こそエロスの根源である。つまりアガペーに対する渇望こそエロスということだ。
愛なるものが内より湧き上がる心の衝動を伴う限りそれはアガペーたり得ない。誰かを愛したい。誰かに愛されたい。そういう心がある限り、人はエロスの迷宮からは抜け出せない。
そういう意味で、自己と他者の境界が認識されえない形まで変容することは、人間がアガペーの境地に達する唯一にして無二の方法なのである」
「ほんとに頭大丈夫?」
しかし大抵の人間はそれに達することはできない。自身がそうであるように、相手が自分に向ける「愛」もまた単なる欲望の二つ名に過ぎないのだと、無意識のうちに恐れている。
星ヶ丘は、性愛と純愛の区別がつかずに暗闇で震えている子羊なのだ。
「安心してくれ」
俺はそんな彼女の不安を和らげたくて、優しい声音で語りかけた。
「いきなりプロポーズしてくるような男の子が隣りにいて、しかもエロスエロスと叫んでいるのに、どうして安心して学校生活が送れると言うの?」
「分かる。不安なんだよな。確かに結婚前は不安になるよな。マリッジブルーって言うんだろ」
「どうして婚約成立してる前提で話しているのかしらこの男は。あなたは物事に順序というものがあることを知らないの? まず言うべきセリフと踏むべき段階があるでしょう?」
「好きだよ」
星ヶ丘は一瞬言葉に詰まった。
ピンク色に頬を染めながら軽く咳払いして
「……軽すぎるわ。誠意が全く感じられないのだけれど」
と答えた。
「おいおい。俺が生涯を通じて愛した女はお前だけなんだぜ」
今度は彼女は胡乱げな目で見てくる。
「……で、好きだからなんだっていうの?」
「え、付き合う?」
「……私があなたとお付き合いすることのメリットを簡潔に教えてもらえるかしら」
「一言で言えば、俺は星ヶ丘を生娘のまま膜を破ってやることができる」
「いい加減にしないと通報するわよ」
……。ふぅむ、人前で俺の愛の告白を聞くのは恥ずかしいらしい。今日のところは引き下がろう。
「……ま、それはそれとして」
「だめだこいつ」
星ヶ丘さんの呆れたようなため息を左から右に受け流しながら、俺はちらと教室の隅に目をやった。上小田井くんは例のごとくハーレムを形成しており、この教室の人口密度を有意に上げている。
星ヶ丘は当然それに気づいておろうが、目もくれていない。まるで見えてないかのように振る舞っている。
しかしそれは彼女が彼にされた仕打ちを恨んでのことではないだろう。確かに上小田井の正体が知れて俄に沸き立った神宮高校だったが、こうして今も上小田井を持ち上げているのは、一部の生徒だけだ。
そしてその連中も、一部ミーハーな奴もいるだろうが、多くが上小田井が所属するアイドルグループ、ミステリアスの元々のファンが大半を占めているらしい。
多くの生徒は日常生活に戻って、不必要に上小田井に絡む事はなくなった。
野次馬根性猛々しいが、醒めるときは一瞬だ。
だから大抵の人間は、今となっては星ヶ丘と同様な態度で、教室の一角の異様な空間には無関心でいた。
そもそもミステリアスに興味があった人間が一部なのだから、それも当然か。
「一限は──」
目線を星ヶ丘に戻した俺が、授業のことを尋ね終わる前に
「数学よ。変態さん」
星ヶ丘はピシャリと答えた。長年の想い人が、眼前でハーレムを形成していれば、何か思うところがあるのも無理からぬことか。
俺はそんな彼女を励ましてあげようとした。
「……お前には俺が居るぜ」
「私はまだ要らないです」