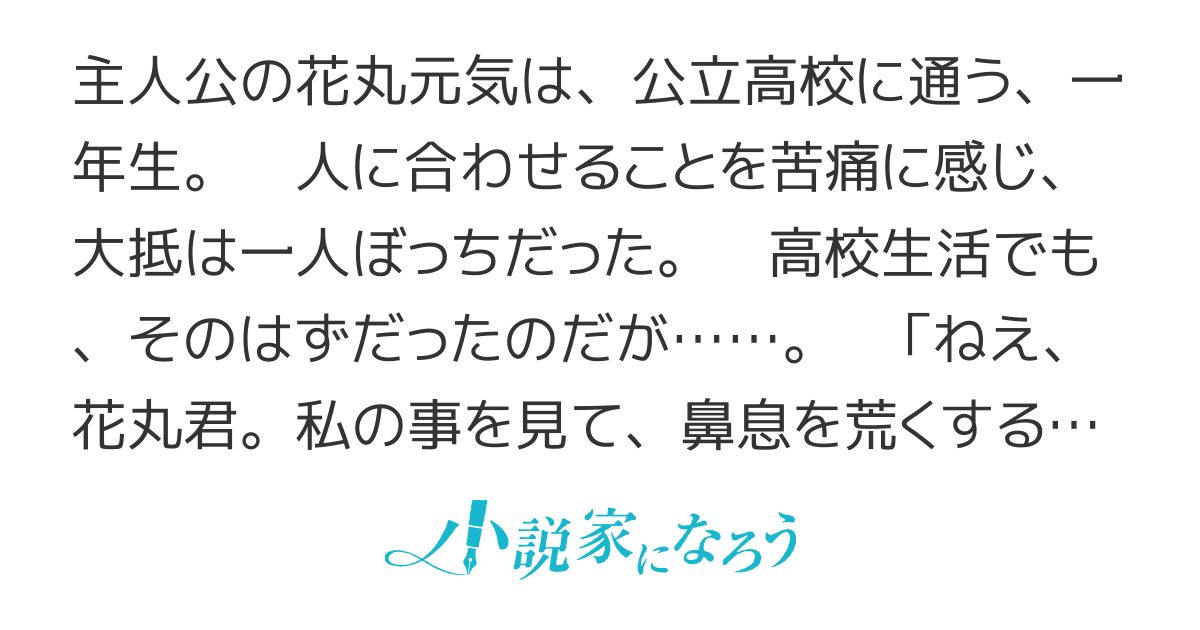執行委員長襲来
幼児というものは概して何でもできると思いこんでいる。
将来、プロ野球選手、アイドル、俳優になりたいと夢を見て、実際それになれるものだと堅く信じている。それどころかウルトラマンになりたい、魔法少女になりたいと、ファンタジーの主人公になる夢を本気で語ったりする。
それは、自分が世界の中心にいて、自分の見ている世界がこの世の全てだと本気で信じているからだ。自分が何でもできるという万能感を持っているからだ。
しかしながらそんな「万能感」というものは、日常生活を送る上で生じる困難にぶつかる内に、次第に薄れていってしまう。自分より出来のいい人間がこの世にごまんといる事を知って、「どうやら自分という人間は大したことはないらしい」ということに、遅くとも高校に入る頃までにはほとんどの子供が気づくだろう。大抵の人間は落としどころを見つけ、妥協に妥協を重ね、いつしか夢すらも見なくなってゆくのだ。
しかしながらいつまでも根拠なき自信にすがり、俺はビッグになると嘯いているようじゃ目も当てられない。夢を諦め現実を直視しなければならない瞬間は誰にでもやってくる。
そう考えると、万能感の喪失というものは、大人の階段を登るのに不可欠なステップとさえいえる。
ちなみに俺がそんな万能感を喪失したのは保育園児の時だ。保育園の日課で縄跳びをやらされたのだが、俺が十日かけて前跳びを十回できるようになった頃には、俺の隣で練習していたやつは、二重跳びどころか、はやぶさまでできるようになっていた。
俺はその時、神というものは不平等で、凡人は天才には勝てず、超えられない壁が存在しているのだということを知った。
尾張旭太陽、四歳の冬である。どうやらこの世界は俺に夢すら見させてくれないらしい。世知辛い世の中である。
いい大人というものは子供の夢を応援するもの、というのが今の世の中の共通認識らしい。
夢などほとんど叶わないというのを知っておきながらだ。そして十数年後になって、夢から醒めない哀れな若者に「いつまで夢を見ているんだ。現実を見ろ」と説教をする。
そうかといって小さな子供が現実的なことを言えば、「夢がない」「子供らしくない」「野心がない」と言いたい放題だ。
大体、俺たち子供に夢を持たせなくしたのは大人たちの責任だろう。テレビをつければ、不景気だ、貧困だ、少子化だ、失業者増大だと暗いニュースばかりで、国民の代表である議員の先生方はそんな状況を打破するような案を練ってくれるのかと思いきや、不正だ、賄賂だ、忖度だといつまで経っても政治をしてくれない。それとも政治というのはあの足の引っ張り合いの事を指していたのか。教科書には書いてなかったが、なるほど、勉強になった。
……。閑話休題。
腹の底では「どうせすぐ諦めるだろう」と思っていても、口先で「応援するよ」というのが「いい」大人。どうやら大人になるということは、まず挫折を味わって、次いで二枚舌を使えるようになることらしい。全く楽しい世の中である。
で、なんで万能感について考えているのかというと、眩いばかりの花道をひた走る御仁が、俺の通う学校の同じ教室にいる訳で、今日も今日とて学園のアイドルを気取っているから……いや、実際アイドルなんだけど。
ああ、つまりこういうことだ。かの上小田井氏は、今も万能感なるものを持ち合わせているのかどうか、気になった次第である。
そんな上小田井くんは例のごとく取り巻きの女子たちに囲まれて、朝から賑やかである。毎度毎度ガヤガヤされるとこちらも迷惑だから、月曜の彼女から日曜の彼女までしっかりシフト表を組んでいただきたい。
「ねえ、尾張旭くん。さっきから眉間にしわが寄っているわよ」
隣の席になった星ヶ丘が若干心配そうな視線をこちらに向けてきていた。
「ああ。何でもない。ちょっと考えごとしてた」
「何?」
星ヶ丘はキョトンと気にかかるような視線を見せる。
「……星ヶ丘はもし自分の子供が俺みたいなリアリストで、子供らしい夢を見なかったらどうする?」
俺がそう言ったら星ヶ丘は明らかに怪訝そうな顔を見せた。
「尾張旭くんは何を言っているの? あなたが私に自分の子供を産ませることを前提として話をしていることに、とてもとても恐怖を感じるのだけれど」
そう言って体を腕で抱きぶるりと身を震わせて見せる。
「……いや、そんなこと言ってないけど。なんで朝っぱらからクラスメートにセクハラせにゃならんのだ?」
「夜ならセクハラしていいと考えているあなたの常識の無さに、得も言われぬ寒気を感じるわ」
「だから端からセクハラする気なんてないから」
「知らないの? 受け手がセクハラと感じたらそれはセクハラなのよ」
「無茶苦茶言いやがる」
そう言って彼女を睨んだら
「やめて、卑猥な目で見ないで。セクハラ!」
「……」
*
閑話休題。
「で、何かしら。私の子供が極端なリアリストだったらって?」
ようやく話は元の軌道に戻ってきて、彼女は俺の問いを聞き返してきた。
「そうだ」
「……そうねえ、私は多分どんな子でも夢を語れるならそれで十分だと思うわ。たとえそれが人から見てちっぽけでも、その子の夢だと言うなら馬鹿にできるものじゃないもの」
「……じゃあ、極端に望外な夢を見たらどうする?」
「宇宙飛行士とか、プロ野球選手とか、……アイドルとかってこと?」
「まあ、そうだな」
星ヶ丘は一瞬上小田井の方に目を向けたように見えたが、俺はツッコミはしなかった。
「応援するんじゃないかしら」
「ほう。なぜだ?」
「なぜって、私の子供だもの。きっと何にでもなれるわよ」
「……あ、そうですか」
子供がいないどころか、結婚すらしていないのに、すでに親バカの片鱗を見せている彼女は一体どんな母親になるのだろうか。
*
昼休みになり、プラプラと図書準備室に向かったのだが、星ヶ丘も後ろにひっついて歩いていた。
「そういえば星ヶ丘は部活やっていないんだよな。なんか理由でもあるのか?」
と彼女に尋ねてみれば
「別に」
と素っ気ない。話すときはべらべらと話す彼女が黙るということは、なにか特別なわけでもあるのだろうかとぐるりと考えを巡らせてみれば、そういえば上小田井も部活に入っていなかったことを思い出した。一緒に帰ったりしようと思えば、星ヶ丘だけ部活に入るのは都合が悪かったのだろう。
悪いことを聞いたと若干申し訳なくなりながら、それからは黙って図書準備室へと歩いていった。
「あら、いらっしゃい」
部屋に入ったところ、すでに先に来ていた祖父江は笑顔で俺たちのことを迎えたが、その笑顔の裏に隠された真意は多分「私はいつまでイチャコラを見せつけられるの? はぁ」みたいな感じだろう。でも「ごめんなさい、祖父江さん」と適当な謝意をテレパシーで彼女の側頭葉に直接届かせる努力をしておいたから大丈夫、多分。
星ヶ丘と祖父江が並んで座り、俺は向かいの椅子に座った。
「なんか今日面白いことあった?」
と祖父江が星ヶ丘に尋ねた。
「そうねえ……」
と星ヶ丘は弁当を広げながら、チラと俺の顔を見てからニヤリとし
「今朝、尾張旭くんに『自分の子が俺に似てリアリストだったらどうする?』って尋ねられたわ」
と嬉々として話した。
「……ねえ、太陽くん。高校生が、というか彼女ですらない女の子に向かって、子供の話をするのは痛すぎると思うんだけど」
祖父江はドン引きしたような顔をした。
「誤解するな。俺はそういう意味で言ったんじゃねえ」
祖父江は俺の言葉には耳を傾けず
「ごめんね。太陽くんちょっと世間離れしているところがあるから」
と星ヶ丘に話しかけている。
「ええ、知っているわ。だから友達が私達くらいしかいないのよ」
「そうだよね」
と二人でヒソヒソと言いたい放題だ。
違うもん。友達は小中の奴ら入れて六人ぐらいはいるもん。
給食の牛乳を代わりに飲んでもらったことがある田中だろ、家の前で通りがかったのを偶然見つけてヤクルトをあげた安本だろ、あとゲームソフトを貸したらそのまま引っ越して行っちゃった山本だろ、あと……あれ、ティッシュ貸してくれたアイツ名前なんだったっけ……。まあいいか。
俺が選りすぐった友人たちである、田中、安本、山本の話をしようかというところで、図書準備室の戸が叩かれた。文芸部に来客とは珍しい。……俺と星ヶ丘も一応来客だけど。
祖父江が「どうぞ」というと、客人はガラリと戸を引いた。
「執行委員長の蒲郡茉織です! 尾張旭君と星ヶ丘さんはいますか?」
戸口に立っていたのは、ぱっと元気いっぱいの笑顔を浮かべる二年の女子生徒だった。
「俺ですけど」「私ですけど」
俺と同じく星ヶ丘も彼女に探されていた理由が分からないようで、手を上げつつ胡乱げな表情を浮かべている。
「二人にはついてきてほしい場所があります」
執行委員長はきっぱりとそう言って、俺たちを立たせた。
「よし、行きましょう!」
そう言ってそのまま俺たちを引っ張っていこうとするが、突然の事態に状況を飲み込めていない俺は
「いや、ちょっと待ってくださいよ。なんの権限があって先輩に昼食の邪魔をされなければならんのですか。せめて理由ぐらい教えて下さいよ」
と先輩に抗議した。
そしたら彼女は満足げに笑い、
「なぜなら私は執行委員長。つまりこの学校で一番偉い人だからです!」
と理由になっていない理由で答える。
俺は今の今まで学校で一番偉いのは学校長だと思っていたのだが、どうやらここでは違うらしい。びっくり。
「……先輩ってもしかしてなんでもできる人ですか?」
と皮肉を込めて聞いたら
「そうです! 私にできないことはありません!」
そう言って彼女はえっへんと胸を張った。
希望を失った高校生たちの目の前に立った、万能感を持ち合わせている執行委員長は、俺達の救世主になりうる気がした……わけがなかった。
俺の本能が告げていたのは、当然波乱の予感である。