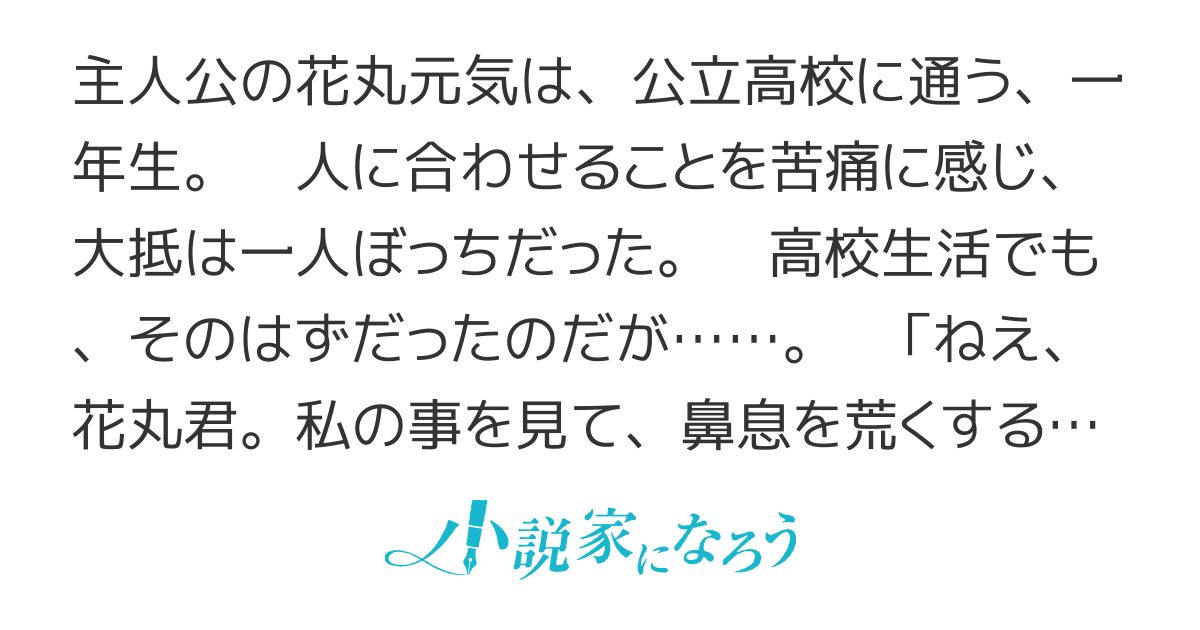触媒を与えられるとツンデレは加速する
帰りのホームルームが終わって、皆が部活なり、帰宅なり各々の目的に向かって移動し始めたとき、鞄を背負った星ヶ丘が、ちょうど教科書などをしまい終わって腰を上げようとしていた俺の前に立った。
彼女はただそこに立つばかりで、何を言うでもなくおどおどと不安そうな顔を見せている。
俺はそんな彼女になるべく優しく声を掛けた。
「じゃあ行くか」
「ええ」
と彼女は少し硬い表情のまま答えた。
*
件のパンケーキ屋というのは高校最寄りの駅ビルの中にある。
駅から学校まで歩いてきた星ヶ丘に合わせて、俺は自転車を押しながら一緒に歩いた。相変わらず表情は硬めで口数は前の彼女より少なくなっている。長年恋慕って尽くしてきた相手に大失恋した後だ、無理もあるまい。
十分程歩き、自転車を適当な場所に停めて、駅ビルの中へと入っていった。
ちょうど終業時間後とあってか、学生服を着た人間が多く駅のコンコースを歩いていた。俺たちは人一人分だけ間隔を空けて、その間を縫うようにして目的の店へと向かった。
店内では身なりの良いマダム二人組が談笑しているぐらいで、すぐに座ることができた。ターゲット層が来る時間帯ではないのだろう。
店員が水とメニューを置いて去ってから
「好きなの頼んでいいぞ」
と俺がささやかな甲斐性を発揮しようとしたら
「気にしないでいいわよ。高校生に奢らせたら寝覚めが悪いもの。自分で払うわ」
とメニューをじっと見ている星ヶ丘に言われた。
「でも俺から誘ったわけだし」
そう言ったら彼女は顔を上げて
「いいってば。あなた、お金持ちというわけじゃないんでしょう? ショウくんと違って」
はぅぁ!?
「お、仰る通りですが、星ヶ丘の笑顔に比べたら俺の野口さんなんて端金なんだぜ」
「あ、そういうのいいんで」
おぅふ。
星ヶ丘はそのまま「すみません」と店員を呼んだ。
注文を終えてから
「ねえ、尾張旭くん。どうしてあなたは私に優しくしてくれるの? 私は嫌なやつだって評判よ」
と彼女はやさぐれた様子で言った。
「……あるいは傷心に漬け込んで、お前の気を引こうとしていると思われても仕方ないのかもしれない」
「……そうなの。でも私は、『彼』に振られたばかりなの。……だから、そういうのは」
「分かってる。ただ……」
「ただ、何?」
俺は言い淀んだ。
上小田井の本性を彼女に告げるべきか迷ったからだ。
でも、あいつがどんな人間か告げたところで、誰が得をするというのだろうか。
そもそも彼女は信じないかもしれない。
信じたとしても、星ヶ丘が上小田井に抱いている気持ちは、単なる恋心だけではなく、十数年かけて培った、より深い感情、いわば信頼のようなものだろう。それが嘘だって分かったら、彼女はどんなに悲しむだろうか。彼女に追い打ちをかけるなんてこと、俺にはできない。
それに彼女は告げ口をする俺を卑しいやつとさえ思うかもしれない。
だから俺はこう言った。
「ただ、他の奴らと違って、俺はお前がいいやつだと知っているし、いいやつが泣いていたら、助けたくなるのが人情ってもんだろ」
その気持ちも嘘ではなかった。
彼女は俺の目をじっと見て、答えた。
「……あなたは優しいのね」
しかしその後も、彼女がかつて見せていた晴れやかな笑顔が戻ってくることもなく、言葉少なめに食事を終え、どこか肩を落としたように見える星ヶ丘が、改札の向こうに消えていくのを見送って、俺も帰路についた。
*
翌朝。
目が覚めて、すぐに昨日彼女と過ごした時間を思い出し、結局何もしてやれなかった自分の無力さを呪いながら、ここ最近で最悪の一日のスタートを切った。
無性に自転車を思いっきり漕ぎたくなって、普段の通学路を倍ほどの速さで爆走しながら、心臓をバクバクさせ教室に入り、ホームルームが始まるまでしばらくぐったりしていた。
*
朝のホームルーム終わりに担任の先生が
「じゃあ、後ろの黒板に席の表書いたので、各自名前を記入していってください」
と告げた。
教師の声に従い俺はいの一番に黒板の前に立ち、自分の名前を廊下側の一番前の席のところに書いた。
なぜこの席を選ぶのかというと、逆説的だが教師から最も見えにくい場所だからである。灯台下暗しというやつだ。これで授業中に当てられる確率が有意に低下する。
これで一学期の残りを平穏に暮らせると安堵したところで、隣の席のところに誰かがサッと名前を書くのが見えた。
その人物とは星ヶ丘照であった。
「え、なんで隣に──」
俺が真意を探ろうとしたら、言い切る前に
「勘違いしないでくれるかしら。私は単に前の席が良かったというだけであって、別にあなたの隣の席がいいだなんてことを考えてここを選んだわけじゃないのよ。最近黒板の文字が見えにくくなってきたような気がしないでもなくなってきたから。というかあなたが隣だってことに今気づいたわ。もっとよく見てから決めればよかった。でも一度決めたことは途中でやめないというのが私のモットーなの。だから我慢するわ」
と顔をそらし、しかしちらちら視線をこちらに向けながら、一気にまくし立てるように言った。
「……何か俺の隣は嫌そうだから、俺移るな」
そう言って、俺が一度書いた名前を消そうとしたら
「何をしてるの? 男児たるもの一度決めたことをひょいひょいと変えるべきじゃないわ」
と言って彼女にガッチリ腕を掴まれた。
俺は昨日までの星ヶ丘と態度が急変していて戸惑いを覚えた。しかしすぐにある結論に至った。
これは……
ツンデレされているのでは?!
彼女が心を開いてくれたことが嬉しくなった俺は
「そうかそうか。そんなに俺の隣がいいんだな。可愛い奴め」
と口を滑らせた。……ツンツンされてるのに心を開いた、というのも変な気もするがまあいいか。
俺の言葉に対し星ヶ丘はサッと気色ばんで
「なっ、だから目が悪くなったせいで──」
と言い訳を始めようとする。
だが俺は彼女が喋りかけたのを遮るように、むんずと顔を近づけて、彼女の目を覗き込んだ。
そうするなり星ヶ丘は身をのけぞらせ
「っ何なの!? 急に人の目をじっと見ないでもらえるかしら?」
と非難するような目を向けてくる。
「いやぁ、星ヶ丘ってコンタクトしてるんかなあって思ったんだが、裸眼みたいだな」
「当たり前でしょう?! 急に見つめないでくれる? そういうことは恋人としてくれるかしら」
「それは『私を恋人にして欲しい』という遠回しなアピールか?」
「違うわよ、馬鹿!」
「星ヶ丘って怒ってても可愛いな」
「可愛いっていうの辞めてくれる? あなたに言われると怖気を震うのだけれど」
「照れんなよ」
「別に照れてなんかいないけれど」
「じゃあなんでほっぺ赤くなってるんだ?」
俺がそう言ったら、彼女は赤い顔のまま眉をひそめて
「尾張旭くんは何を言っているの? そんなの血管が拡張して、血液が皮膚表面に集まってきているからに決まっているじゃない。知ってる? 血は赤いのよ。それともあなたはなぜ血が赤いのかなんて聞くのかしら? それは要するに七〇〇ナノメートル前後の電磁波を赤色光と昔の人が呼んだせいであって、それ以外の可視光線を吸収する色素が赤血球に含まれているからであり、とどのつまり赤色を赤色と人が定義したせいよ。と言う訳で妙な勘違いをするのはやめてくれる? それともヘモグロビンの共役二重結合についても説明したほうがいいの?」
と早口でまくし立てた。なるほど。要するに顔が赤くなったのは、赤色が赤いせいだということが言いたいらしい。……。
「え、何? N○K高校講座なの? それも生物と物理と化学まとめてやろうとしてるし」
「……あるいは、磁気嵐の影響か何かで、今この瞬間、日本国の愛知県に降り注ぐ光に赤色光が多く含まれている可能性もあるわ」
なんか無理矢理地学もぶっ込んできて、理科制覇しちゃってるし。
それにしてもこのレスポンスの速さで、ここまでべらべらと言い訳を連ねられるのも、一つの才能ではないだろうか。それの妥当性には疑問符を付さざるを得ないわけだが。
しかしながら、口が立つことには変わりない。どうやら引き出しも多いようだし彼女と会話をするのは想像していたよりも面白そうだ。
そして今のやり取りを通して、俺は一つ気づいたことがある。
それは、星ヶ丘のツンデレがアカデミック過ぎて、上小田井に理解されていなかった可能性があるということだ。彼女の相手は並大抵の男には務まらないだろう。これは上小田井が芸能人として三流だからとかそういうことではなくて、星ヶ丘ロゴスについていけるだけの知識と理解力が必要であるということだ。芸能人とは言え普通の高校生にその荷はちと重たい。
だが俺なら、お前のことを分かってやれるぜ。なぜなら俺は普通じゃないからな。ガハハ。
俺は彼女の内に秘めた思いを代弁した。
「……まあ、言い換えるとこういうことだろ。お前のヘモグロビンが吸収し得なかった赤色光を俺の網膜視細胞が吸収することで初めてこの現象は完成するのであって、つまり俺たちは二人で一つということだな。お前を通り抜けてきた光が、俺の中に入ってくると思うと、背筋がゾクゾクする。ありがとうございます」
付け加えて言うと、俺が星ヶ丘照の姿を知覚するということは、この観測地点における「星ヶ丘照」という事象の唯一の観測者が俺ということになり、俺しか知らない彼女というのが、俺の知覚世界に出現しているということになる。いつの間にかそんな秘密を共有する仲になってしまったか。照れる。
彼女は俺の言葉を前に固まっていた。今まで彼女が手にし得なかった良き理解者の存在を目の当たりにして、感動のあまり言葉を失ってしまったに違いない。
そう思って感慨深く思っていたら、彼女はドン引きしたように
「……一体どういう解釈をしたらそんなことになるの? ポジティブ過ぎて、というか発言が普通に気持ち悪いのだけれど。視認できなくなる距離まで離れてくれる?」
と心底気味の悪そうな顔をした。
おっと。あまりに俺が女心を理解しすぎるせいで、動揺させてしまったらしいな。よし、話を変えよう。
「まあ、それはそれとして星ヶ丘の目ってキラキラしてて綺麗だよな」
すぐに星ヶ丘は口元をモニョモニョと歪ませながら
「尾張旭くんは馬鹿なの? 私がそんな見え透いたお世辞で喜ぶようなチョロい女に見えた? ガーネットのように輝く瞳を持った天使のような女の子だなんて言われても全然嬉しくないのだけれど」
と言ってベシベシ肩を叩いてきた。多分に俺の発言が改竄されていたけれど、まぁ気にしないでおこう。だって可愛いんだもん。
全く痛くはなかったが叩かれる度
「あいったぁ、あいったぁ、あいったぁ、閉じた、あいったぁ」
ととりあえず合いの手を入れておいた。
そんなとき
「あのぅ」
その声に俺たちは二人ともハッとした。
「二人だけの世界に入ってる所大変悪いんだけど、もう授業始めてもいいかな? みんなも座ってるし……」
担任の先生が苦笑いしながら俺たちのことを見ている。
気づいたら教室中の視線が俺たちに集まっていた。先程よりピンク色に染まっていた星ヶ丘の頬が、ハイビスカスの花のように真っ赤になったことはここだけの秘密だ。
それを指摘してどんなツンデレで応酬してくるのかについては非常に興味を唆られたが、あまり困らせて嫌われてしまっても面白くない。だからぐっと堪えることにした。
──────ある夜のメールのやり取り
文芸(美)少女『で、初デートはどうだったの?』
主人公「パンケーキは美味かった」
文芸(美)少女『……駄目だこいつ。君、落とす気あんの?』
主人公「駄目だとは何だ。大体デート一回したぐらいで落ちるようなチョロインが、俺のヒロインなわけ無いだろ」
──────ある少女の所感
ツンデレ「ツンデレが恋に落ちたので、ツンデレしてみた」
──────あるクラスメートの所感
名無しさん「とりあえず爆発すればいいと思いました」
──────あるアイドルの所感
実はイケメンボーカリスト「男の趣味悪すぎて草」