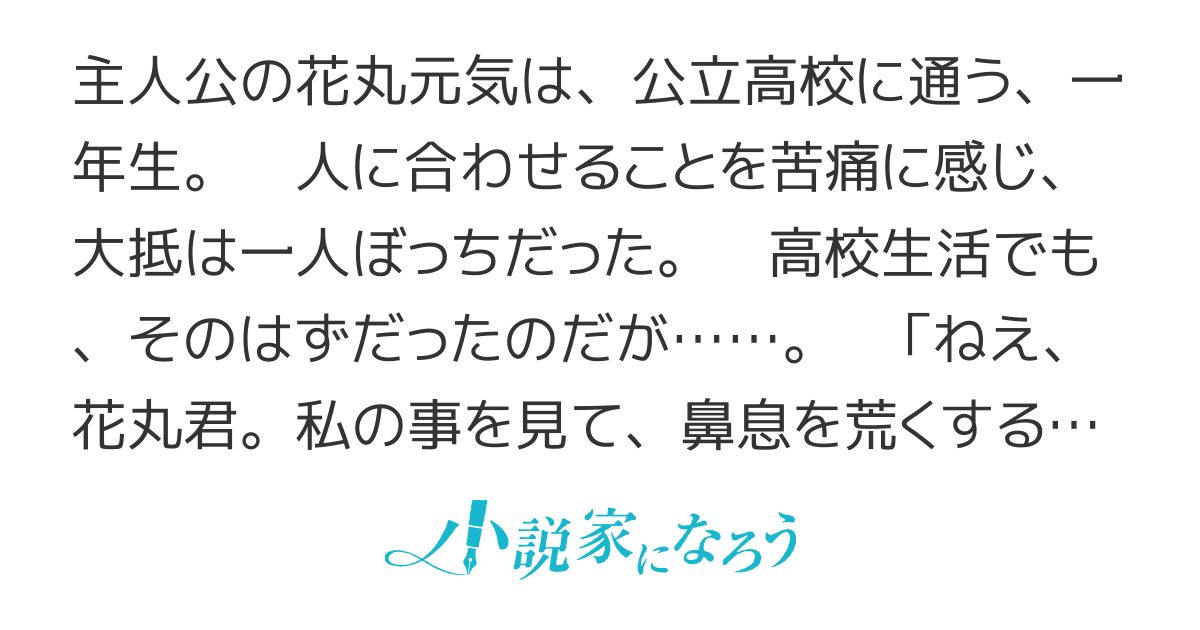すっぱい葡萄
「うっす」
昼休みになったので、例のごとく文芸部の部室に訪れたのだが、俺が入るなり中にいた祖父江は
「はぁ」
と大きな溜め息をついた。
「え、何? 俺、何かした?」
「何かって、太陽君何もしてないよね? 馬鹿なの?」
「何ゆえ、唐突の罵倒?!」
「私がせっかく星ヶ丘さんと一緒にお昼ごはんを食べさせてあげる機会を作ってあげたというのに、なんで一人で来てるの? 馬鹿なの?」
「……昨日と言ってること違う」昨日はお前は勝手にしろって言ってたじゃん! お前もツンデレかよ。「大体、俺は星ヶ丘のこと好きなわけじゃないって、何度も言ってるだろ」
俺がそう言い返したら、また祖父江は大きなため息をついた。
「あのさ、太陽くん。君はね、星ヶ丘さんのことが好きなの」
「好きなの、って俺の気持ち勝手に宣言されても困るんだが」
「……太陽くんはフロイト先生の適応機制をご存じない?」
「フロイトっていうのは聞いたことあるが、適応機制ってなんだ?」
「……じゃあ、イソップ童話の『すっぱいぶどう』の話は知ってる?」
「それは知ってる。狐が高いところになってる葡萄を食べられなくて、『どうせあんな葡萄はすっぱい葡萄さ』って負け惜しみを吐いた話だろ」
「そう。適応機制っていうのはつまりそういうこと。自分に生じた欲求に対する様々な対処法のことを適応機制っていうんだよ。狐の場合は『合理化』だけど、君の場合は『否認』かな。『俺は振られてなんかいない。なぜなら、そもそもあいつに惚れていたわけじゃないから。振られようがないだろ』ってね」
「……どうだか」
俺は祖父江の言葉に対し肯定も否定もせずに、ただ肩をすくめた。言われてから思い出したが、適応機制という言葉は前に聞いたことがあった。他にもいろいろな精神的機微が分析されていたはずだ。確か『ツンデレ』に当てはまるものもあったと思うが……。
俺が記憶を探ろうとしたところで、祖父江は続け
「なんで君が、そんな事態に陥っているか分かる?」
「さあな。どうやら俺のことは俺なんかより、祖父江先生の方がご存知らしいから、御高説賜りたいな」
俺は皮肉っぽく返したのだが、祖父江は特に気を悪くするでもなく、指をくるくる動かしながら
「星ヶ丘さんに好きな人がいたから。それも幼馴染で、べた惚れの」
「ああ分かったぞ。そうか、俺は星ヶ丘の幸せを願ってあえて身を引いたってわけか。なるほどわかった。よし、この話は終わりな──」
俺は話を終えようとしたのだが、祖父江は遮るように
「今、星ヶ丘さんは失恋した。君がこれ以上躊躇う必要はないと思うけれど」
と窺うような視線を向けてきた。
「……なんだ、傷心につけこめとでも」
「やだなあ。女の子の涙を拭き取るのは紳士の務めでしょう?」
祖父江にじっと見られ、俺は言葉に詰まった。
確かに泣いている星ヶ丘を見て、助けてやりたいと思ってこの部屋につれてきたのは、俺の意思だった。それが好意によるものだったなんてことがあるのだろうか? この三ヶ月、彼女と共有した時間の中で、俺はただのクラスメート以上の親近感を持って彼女と接していたわけではない。友達と言うのにもためらいを覚えるくらいの希薄な関係でしかなかったのだ。
ただ彼女が芸術品のように綺麗だったから思わず声をかけて、ただ長年の想い人に捨てられた彼女の心が痛いほど分かったから手を差し伸べて……。ただそれだけのはずなのだ。それが恋心だと果たして言えるか?
俺は自問した。
だが答えが出るわけがなかった。なぜなら、俺は今まで恋心を抱いたことなんてなかったんだから。
一つの事象しか知りようがないなら、それを突き詰めることによってしか答えは得られまい。
「……しかしながら、具体的にどうすればいいのだ?」
ひとまず、俺が星ヶ丘照に惚れていると仮定しよう。そこから先は俺が頭の中でうんうんと考えてもどうにもならない。この問題は対人関係によって生じた以上、答えは俺の頭の中にあるのではなく、彼女との関係の中に存在しているはずだ。こうなった以上は、彼女と接触しそのやり取りの中で自分の気持ちを確かめるしかない。
祖父江なら、次のステップに進めるための手段を教えてくれるだろうと、すがる思いで見つめたのだが
「さあ、喫茶店にでも誘えば?」
そっけなくそう吐き捨てた。
「ええ、急に辛辣じゃん」
「そこ、私に頼ってちゃこの後やってけないよ。後は自分の頭で考えなさい」
祖父江がちょうど言い切ったところで、文芸部の部室の戸が開いた。
やってきたのは星ヶ丘である。
「こんにちは。約束したから、来たわ」
「うん! ありがとう!」
祖父江は打って変わって明るい顔で星ヶ丘を出迎えた。
「いえ」
星ヶ丘は恭しく席についた。だが落ち着かないのか、そわそわしている。
不意に誰かの足が、俺の足に触れた。
その方を向けば、祖父江が「ほら」と口パクで急かしてきた。
俺も口パクで「今?」と聞けば、すぐに「今」と口パクで返ってきた。
急になにかしろと言われても、無理なものは無理だ。
とりあえず祖父江の無茶振りは無視することにしよう。
ふと俺は星ヶ丘が持っていたのものが目に入り、尋ねた。
「……昼、それだけなのか?」
彼女の手にあったのは、惣菜パンの袋一つだけだった。手作り弁当ではなく、おそらくは学校の購買で買ったパンだろう。それだけで足りるのだろうか?
星ヶ丘は元気がなさそうに
「……あまり食欲が無いのよ」
と答えた。
昨日も弁当を食べ残していたし、やつれた様子から察するに家でもあまり食べていないんじゃないだろうか。上小田井に振られたのがやはり相当ショックだったらしい。教室では気丈に振る舞ってはいるが、精神的には相当堪えているのだろう。
弱っているのを人に見せないという振る舞いは、彼女が惚れた男に対して見せていた天の邪鬼な態度にも通じているのだと俺は思った。星ヶ丘照はそういう性格に生まれついたのだ。
表面上は強がっていても、その中身がガラス細工のように繊細なのだ。
俺は思い出した。
ツンデレも適応機制の一つである。医学的には反動形成というのだ。
好きでも真逆な態度をとってしまう。
辛くて泣きたくても平気なふりをしてしまう。
傲った態度を取るのは、心が弱くて敏感でそうでもしないとやっていけないほど繊細だからだ。
そんな彼女がどうして嫌な女だと言えるだろうか。
俺はその弱ささえ美しいと思ってしまう。
一つの結論に至ったとき、俺は特に悩むでもなく、何をすべきか分かった気がした。
早々と食事を終えてしまった星ヶ丘に対し
「なあ、星ヶ丘、今日の放課後なんだがちょっと付き合ってくれないか」
と告げた。
「……どうして?」
星ヶ丘は訝しげな視線を向けてきた。
「パンケーキ屋にでも行こうかなと」
「……だからなんで?」
彼女の表情は更に曇った。
「駅ビルにパンケーキ屋あるの知ってるだろ。前から行ってみたかったんだが、なかなか野郎一人じゃ入りづらくてな。女子が一緒だと心強いんだが。……一緒に来てくれたらなにか奢るぜ」
「……私、食欲ないって言ったでしょう」
星ヶ丘は興味ない素振りを見せたが、
「まあまあ、ほら、美味そうだろ」
と俺はスマホで店のホームページを見せた。カラフルに盛り付けられたパンケーキの写真が載っている。
「だから、私は……」彼女はなおも断ろうとしたが、そこでお腹がグーとなった。「……」
赤くなる星ヶ丘に構わず俺は続けて
「ほら、この苺のやつとか絶対美味いと思うぞ。食欲ないなら、飲み物だけでもいいんだ。頼むよ。哀れな男を助けてやると思って」
俺が押し切るように言ったら、星ヶ丘は頬を染めたまま軽く咳払いをして
「……しょうがないわね。あなたがそこまで私と一緒に行きたいというのなら、別に行ってあげてもいいけれど」
と言った。
「じゃ、約束な」
どうだ、見たか。
そんな気持ちで祖父江の方を見たら、ニヤついた顔で
この女たらし
と口を動かしたのが見えた。
……いや、違うだろ。