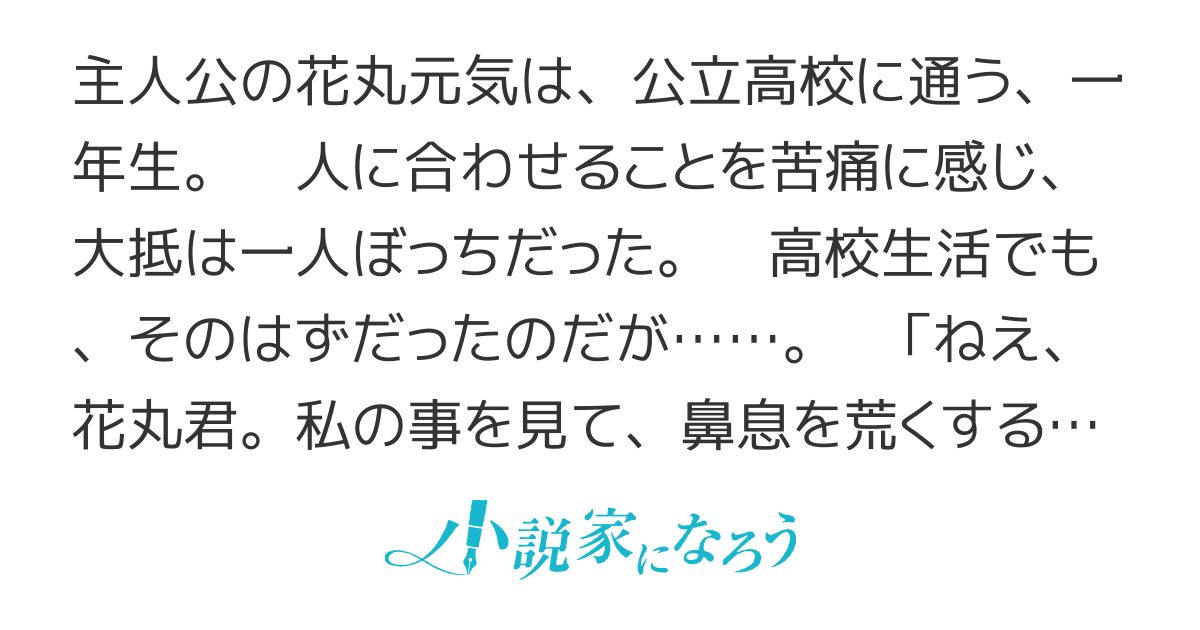女泣かせて悦に浸るやつにまともな人間がいるはずがない
翌日学校に行ったら、校門前に人だかりができていた。
制服を着た警察官まで出動している始末で、何か異常事態が起きていることだけはすぐに察せられた。
どうやら集まっているのは、メディアの人間らしい。カメラを構えた人間が複数人、目をぎらつかせながら登校してくる生徒たちに目を向けている。
訳が分からなかったが、警察官に守られながら学校の中へと入っていった。
教室に入るまでの間で、見知った顔がいたので尋ねてみた。
「一体、何の騒ぎだ?」
その男子は答えて
「知らないのか? ミステリアスのボーカルがうちの学校の生徒だったってのが昨日ネットの記事に上がったんだよ。多分それで雑誌の記者が校門前に詰め掛けていたんだと思う」
「ほぇー」
ミステリアスと言ったら、ちょうど昨日祖父江と話した、素顔が知られていないイケメンバンドの五人組のことではないか。なんともタイムリーな事件が起こったものだ。そのボーカルがうちの学校の生徒だったとは。
「学年ラインで誰なのかって話が上がってたろ。……そんで俺らのクラスの上小田井なんじゃないかって」
え、何? 学年ラインって。俺それ知らないんだけど。
「……って、え? 上小田井だって? あの根暗長髪ラノベ主人公みたいな男のことか?」
「は? 何の話だ」
「あ、いや。こっちの話」
星ヶ丘が惚れている男が話題沸騰中の音楽グループのボーカルだと? そんなことが……。
あ。そういえば、星ヶ丘はあいつのこと……。
「なあ。そのボーカルの名前ってなんだったっけ?」
「ショウ」
……なるほど。彼女だけが知っている上小田井の秘密というのは、どうやらこのことだったらしい。
教室に入ってみれば、噂の上小田井君の周りには人だかりができていた。
「ねえ上小田井君! サイン頂戴!!」
「ちょっと!! 私が今話していたでしょ。じゃましないでよ」
「私ショウ君のファンなんです! 握手してください!」
「他の芸能人とかもよく会うの?」
「ねえ、ちょっと歌ってみてよ! 新曲、生で聞いてみたい!」
こんな感じで興奮した女子たちが群がっている。うちのクラスの女子ばかりではなく、他のクラス、さらには上級生までもが一緒になって上小田井を囲んでいた。
しかし、その中に星ヶ丘の姿は見えなかった。どこにいるのかと思えば、いつも通り自分の席に座って、我関せずといった面持ちで粛々と授業の準備をしている。
俺は彼女の近くの席なので、荷物を置いてから
「上小田井ずいぶん人気だなあ」
と話しかけてみた。
「そうみたいね」
彼女はすげなくそう答える。
「……星ヶ丘は混ざらなくていいのか?」
「どうして?」
「だって、いつもあいつと話してるじゃん」
「……別に。他の人が話しかけているのを押しのけてまで、する話はないし」
素っ気なく言ってはいるものの、上小田井が自分だけのものではなくなっているのを見て、気が立っているようにも感じられた。
*
教師含め皆どこか浮ついた雰囲気のまま、その日の授業はすすんでいき、放課後を迎えた。
ショウ改め上小田井翔のことが学校中に知られ、校内のいたるところでその話で持ち切りとなっている。廊下は上小田井のことを一目見ようと人があふれ、抜け出すのに一苦労だった。
例の文芸少女はこのことをどう思っているのかと、ご機嫌伺いがてら文芸部の部室へと向かった。どうせ今日は委員会があって図書室にはいかなければならないから、そのついでだ。
部室についてから、コンコンとノックをして中に入った。
「あらあら。これは尾張旭太陽君ではないですか」
「杏お嬢様。ご機嫌麗しゅうございますか?」
「変わりありませんわ」
といつも通り二人でアホな挨拶を交わす。
「……ほんとに変わりないな。今日は一日学校中が沸き立っていたというのに」
「ショウのことで?」
「しょうしょう。ショウのこと」
「まあ、もともとそんな興味なかったしね。というかほんと滑稽だよね。今まで誰も上小田井君の話なんてしなかったのに、一躍学校のアイドルだよ? 皆調子いいよねえ」
「まあ、実際アイドルだしな」
それから祖父江は面白がるような口調で
「でもまさか尾張旭君の恋敵がアイドルとはねえ。これは敵わないわけですわ」
「恋敵って、俺は別に星ヶ丘に惚れているわけじゃないんだけど」
そう。あれは俺の勘違いだったのだ。一級の工芸品に息をのむような感動を覚えるのと同様、彼女の美しさに感動したのを恋心と誤ってしまったのだ。
そうであるというのに
「強情だなあ」
と祖父江はあきれたような顔をしている。
だから違うんだって。
まったくこの子は聞く耳を持たないんだから。
「でも星ヶ丘さんも焦ってるんじゃない? 上小田井君の正体が芸能人だってみんなに知られちゃったら、女子たちがほっとかないでしょ。誰かに食われる前にアタックするかもよ」
「アタックなら散々してると思うんだけどなあ」
それを上小田井が交わし続けているのだろう。全く罪作りな男である。
「アタックってツンツン攻撃のことでしょ? そうじゃなくてようやくデレデレ攻撃を始めるんじゃないの? 知らないけど」
「馬鹿野郎。ツンデレがデレデレし始めたら、なんの旨味もないじゃないか。たまにしかデレないから可愛いんだろ? ツンデレの黄金比は9対1だろ? 甘すぎると胸焼けしちゃうだろ? デレデレがいいだなんて素人考えだからね? そんなこと言うやつは童貞に違いない」
「お前も童貞だろ」
「……よし委員会行こ」
*
その日から、ここ神宮高校においては、女子生徒を引き連れた上小田井の大名行列は日常の風景と化した。
妙だったのはその行列には決して星ヶ丘照は加わらなかったということだ。登下校時には近所の幼馴染らしく二人で一緒に行動しているのだが、学校に近づき周りの生徒が上小田井に寄って来ると自然と離れて距離を取るようだった。
また一つ変わった事は、上小田井がそれまで顔を隠すように伸ばしていた長髪をバッサリと切った事だった。
俺は日常生活でも隠すぐらいなのだから、相当な醜男に違いないと踏んでいたのだが、憎たらしいことに、星ヶ丘が評したようにその顔は甘いマスクと言って差し支えないものだった。
イケメンボーカルとうわさされた男の素顔が露わになり、女子たちはいっそう騒ぎ立てた。しみったれたやつだと思っていた上小田井が、女子に囲まれヘラヘラしているのを見て、モヤモヤした得体のしれないものが、腹のそこで渦巻くような感覚を覚えた。俺もつくづくみみっちい男である。
ただ一つ変わらなかったのは、そんな感じになっても星ヶ丘は上小田井に対しツンツンした態度を辞めなかったということだ。彼女こそツンデレの鑑ではないだろうか。俺が市長だったら市議会を脅し立ててでも指定文化遺産に登録していたところだ。
ある日の夕方、俺は筆箱を机の中に入れっぱなしにしていた事に気づき、教室へと引き返していた。
部活で使われる本館と特別棟以外の、普通教室が集まっている校舎はひっそりとしている。俺の歩く足音がひたひたと壁に反射して響いてくる。
俺たちのクラスに近づき、さっさと筆箱を回収して帰ろうと中に入ろうとしたら、人の話す声がした。別に悪いことをしているわけじゃないのだが、人がいる事に驚いた俺はとっさに身を隠した。そして中の様子を窺ってみる。いったい誰が話しているのだろうか。
「えっと……、なんというか、もう俺と一緒に帰ってくれなくていいよ」
「……なんでよ?」
男と女の声だ。女の方はどうやら星ヶ丘らしい。朧げな記憶と話から察するに、男は上小田井だろう。
上小田井は続けた。
「実は、俺のこと好きだって言ってくれる子がいて、その子と付き合おうと思うんだ」
「……ふーん。……その子って誰?」
「二年の先輩だから知らないと思う」
「……そう。まあ、せいぜいボロが出ないように頑張ることね」
星ヶ丘はそう言って、そのまま踵を返して歩き出したようだった。
それを上小田井が呼び止める。
「あ、待って」
「何かしら?」
「……お前、俺のことどう思ってた?」
「……なんでそんなこと聞くの?」
「……なんでって、そりゃ気になるから。ずっと俺に当たりキツかったし、家が近所だからってだけでほんとは嫌いだったのに一緒にいてくれたのかなって……。やっぱ、皆にそれでからかわれるの、嫌だったよな」
俺はそれを聞いて、なんと鈍感な男なのだろうか。ずっと一緒にいて彼女がどういう気持ちか全く気付かなかったというのか、と怒りに似た感情すら覚えた。そこでおそらく星ヶ丘照という少女も素直になることはできずに、「そうだ」と答えるんだろうなと、切ない気持ちになったところで
「好きだった」
彼女の口から飛び出してきたのは、想像だにしない言葉だった。
上小田井も予想外だったようで
「……え?」
と間抜けな声を出している。
それでも彼女ははっきりとした口調で繰り返した。
「ずっと好きだった」
さて上小田井はどうこたえるのかと、さすがの俺も耳を立てざるを得ない状況になったのだが
「……そんなこと。そんな、……今更好きとか言われても困る」
上小田井はうじうじとそう言った。全く情けない。
「あなたが聞いてきたのでしょう」
星ヶ丘は詰るように返した。
「……そうだな。でもごめん。今更遅いよ。……本当にそうだったなら、もう少し優しくしてほしかった。そしたら俺だって──」
「もういいじゃない。あなたには念願の彼女ができた。それで十分でしょう。じゃあさよなら」
彼女に見つかるまいと俺はとっさに隠れようとしたのだが、身を隠す前に彼女は出てきた。
ちらりと見えた彼女の瞳は、雫に浸ってキラキラと光を反射させていた。彼女が俺に気づいているのかどうかわからなかったが、防火扉の後ろに引っ込んだ俺には見向きもせずにそのまま駆け足で去って行ってしまった。
俺に何ができるとも思えなかったし、何もすべきではないというのが多分真実だったので当初の目的通り、筆箱を回収するために鈍感男のいる教室に入ろうとしたのだが、ツカツカと上小田井が出てきた。
これはドラマみたく「ちょ、待てよ」と、自分の本当の気持ちに気付いて彼女を引き留めに行くのかと思ったら
ざまぁみろ
俺の思い違いでなければ、上小田井がそのように口を動かしたのがすれ違いざまに見えた。
いい加減張り倒してやろうかと思った。