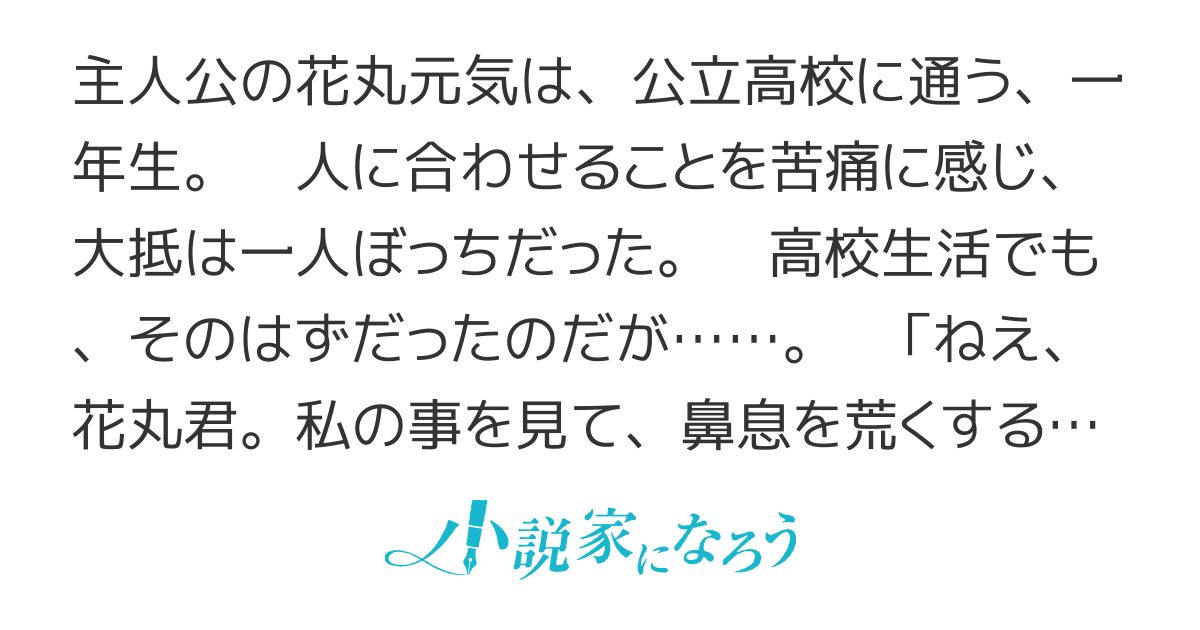ツンデレ幼馴染と鈍感ラノベ主人公……と俺(今のところ傍観者)。
誰かが「愛とは粘膜の接触である」と言った。人は粘膜の接触によって生まれ、母の粘膜の袋の中で育ち、地に落ちてくる。
では粘膜が接触していなかったらそれは愛ではないのかというと、そうとも思えない。
例えば愛国心は確かに存在するが、人は粘膜を通して国と愛を育んでいるわけではないだろう。
人はペットを愛するというが、それらペットと粘膜で接触すれば、重篤な感染症に罹患することは避けられない。
逆に粘膜が接触していればそれは愛なのかというと、それにも首を傾げざるを得ない。ただの粘膜の接触は愛などではない。
カエルの粘液が目に付着なんかしたりしたら、大抵の人間は発狂したようにのたうち回るだろう。それは果たして愛と言えるか。愛ゆえに狂喜乱舞しているとでも? もちろん違う。これは愛ではない。
人間は生物である以上呼吸をする必要があるが、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する過程は粘膜を介して行われる。それは大物芸能人でも、一般市民の俺でも変わらないわけで、つまり時間的空間的差はあるにせよ、トップアイドルの呼気を吸っている俺は、彼女らと粘膜を介して接触していることになる。これは愛かもしれない。違う。
とにかく、愛とは何かという問いに一元的な視点で答えを出すことができないというのが最も妥当な答えなのかもしれない。
では愛という概念を性愛的な領域に限局して捉えるとしたらどうだろうか。つまり男女間の愛についてだ。一つここで俺が告白することがあるとすれば、俺は高校に入るまで誰かを性的な意味合いで愛したことはなかった。平たく言うならば女に惚れたことがなかったのだ。美人かどうかというのは、単なる造形の美しさを論じるにとどまり、美しい絵や美しい風景を愛でるのと同じで、それに対し特別な好意を抱くことはなかった。俺の中での女に対する認識といえば、群れるのが好きで、可愛いものが好きで、そして外見的な形質として局部の形状が男のそれと異なっているというくらいのものでしかなかった。
そんな俺に男女関係のパラダイムシフトをもたらしたのは一人の少女との出会いだった。
その少女の名前は星ヶ丘照といった。
容姿端麗なクラスメートで、かつ俺の委員会仲間でもあった。
高校に入学し初めて彼女を目にしたとき、心臓のあたりがきゅっと締まる感覚を覚えたのは今でも記憶に残っている。
生まれて初めて感じたその感覚は、俺が今まで知らなかった恋という代物なのではと気分が高揚し、その真偽を確かめようと、その日のうちに彼女を駅前のカフェに誘うことを決意した。
しかしながら話しかけてすぐに
「ごめんなさい。私好きな人がいるの」
俺の初恋らしきものは、始まって半日と経たずに砕け散った。
彼女と同じ委員会に入ったのは全くの偶然だったが、しばらく委員会を通して一緒に過ごすうちに、初めてあった日の胸の高鳴りもいつしか消え去り、どうやらあれは恋ではなかったらしいと思う頃には、梅雨も終わりを迎えようとしていた。
彼女は出会ってそうそう声をかけてきた軟派者に対しても優しかった。別に無視されることはなく、必要なことがあればその分だけ言葉をかわし、ただのクラスメートでただの委員会仲間というに足るくらいには、良好な関係を築けていた。
彼女とした他愛もないやり取りの中で彼女の惚れている相手というのが、幼馴染の男子であるということを知った。なんと同じクラスの男子であるという。つまり俺のクラスメートでもあるわけだ。名前を聞いたら特に隠すわけでもなく
「上小田井くんよ」
と彼女は答えた。
何でも物心がついたときから一緒にいる仲だという。
俺はその話を聞いたときは、上小田井なる男の顔が頭に浮かばなかったのだが、次の日教室で確かめてみればなるほど合点がいった。目が隠れるような長髪の男なのだが、星ヶ丘とよく一緒に帰っているのを見かけていた。
彼女の彼に対する態度は、他の人間に対するものと随分と違ったものだった。デレデレした態度とかそういうわけではない。まさしく気の置けない人間に対する態度で、見様によればきついあたりに見える言動もしばしば見られたが、姉弟のように一緒に育った仲であればこそと頷けるものでもあった。
先日も
「ほら、ショウくん。いつまでノロノロしているの? 私を待たせて申し訳ないと思わないの? ナマケモノの真似でもしているの?」
とぐずぐずして帰りの支度を終えられない上小田井をなじるように星ヶ丘は声をかけていた。
それに対し上小田井は
「先に帰っててもいいよ」
と返答しているのだが
星ヶ丘はさらに
「何を言っているの? 散々待たせておいて、その時間を無駄にしろと言っているの? 馬鹿なの?」
と野次を飛ばしていた。
これこそ長年連れ添った二人が織りなす、絶妙なやり取りというにふさわしいものではないだろうか。とっととくっついて爆発してしまえば良い。
しかし美少女と言って差し支えない彼女があえて彼を選んだ理由だけは俺にはわからなかった。上小田井翔という男は影が薄く、特に目立つところのないやつで、他の女子たちが彼のことを話題に上げている所はおろか、むしろ陰気なやつとして煙たがられているぐらいだった。
そんな男だったから、単純な興味で「どこがいいのか?」と彼女に尋ねた。
そしたら彼女は
「髪を切ったら本当は格好いいの。みんな気づいていないけれど。……他にもいいところは色々あるけれど、言うなって言われているから言わないわ」
と答えた。まるでウェブ小説の主人公みたいなやつだと俺は思った。
*
ある日の昼休み。
俺は図書室の隣の、文芸部の部室に向かっていた。
俺と星ヶ丘の委員会の主たる活動場所は図書室であるのだが、図書室は飲食が禁止だった。そのため、のどが渇いたときは外で飲む必要があるのだが、図書室と扉でつながっている文芸部の部室は飲食が可能なのである。だから俺は文芸部員と仲良くなって、よく利用させてもらっている。
今日もなんとなく教室で昼飯を食べる気にならなかったので、弁当を持って、そこを訪れたのだ。一年の祖父江という文芸部員が高確率でそこにいるので、時たま一緒に昼食をとったりしていた。
ドアを二、三回ノックしてから
「邪魔するでえ」
と声をかけて入った。
「邪魔するなら帰ってー」
「はいよー。……って、なんでやねん!」
そのやり取りの相手、祖父江杏は、俺の最後のノリツッコミにケラケラ笑っている。
そして
「ほんと尾張旭くんってベタなギャグが好きだよね。売れない芸人でも目指してるの?」
と祖父江は言った。
「いや、俺が好きというか、君が振ってきたんじゃん。あと売れない芸人は誰も目指さないと思うぞ」
俺は座るために椅子を引きながら、そう答えた。
「いやいや、振ってきたのは尾張旭くんが先だったよ」
「ええそうかな」
「そうだよ」
祖父江は席についた俺を見て
「それで何かな? また文芸美少女との逢瀬を遂げに来たのかい?」
とにやにやしながら尋ねてきた。
「……」
「あ、今『何こいつ自分のこと文芸美少女とか言ってんの? 鏡見て言えよ』とか思ったでしょ」
俺は答えて
「いや、思ってないけど……」
「顔に出てるよ。そこで気の利いたセリフの一つも言えないから、星ヶ丘さんに振られるんだよ」
「いや振られてないし。カフェに誘ったら断られただけだし」
「それを私どもの世界では『振られた』というのだよ、少年。大体『お茶でもしない、お嬢さん?』っていつの時代の口説き文句ですか? 尾張旭太陽くんは大正時代の人ですか?」
「そんな口説き方は断じてしていない」
「でも似たようなもんでしょ」
「……よし、飯でもくうべ」
*
昼食も摂り終える頃、祖父江がポチポチとスマホをタップしているのが気になり
「何見てるんだ?」
と彼女のスマホを覗き込んだら
「……ねえ尾張旭くん。躊躇なく女の子のスマホ覗き込むのどうかと思うんだけど」
「おいおい俺お前の仲じゃないか」
「……まだ出会って2ヶ月くらいしか経っていないんだけど」
「まあ気にすんな」
「それあなたのセリフじゃないと思う」
「……で何見てるんだ?」
祖父江は「駄目だこいつ」とブツブツ言いながらも、画面を見せてくれた。
「誰だこいつ」
俺は見るなり言った。
祖父江は眉尻を下げて答える。
「言うと思った。今、流行りのバンドグループ『ミステリアス』のイケメンボーカル、ショウ。素顔は誰も知らないんだけど、女子中高生の間で今一番人気の歌手……らしいよ。噂じゃメンバー全員イケメンの高校生みたい」
と完全に他人事のように話す祖父江が新しく見せてきた写真には五人組の顔の上半分が切れた男達が写っていた。胸元にはバンド名と曲名らしきものが書かれてある。……Albatrossって確かアホウドリのことだよな。……一体どんな曲だよ。
そして、ツッコミどころは他にもいろいろとあるのだが、まず第一に
「……なんで素顔が知られてないのにイケメンって分かるんだよ?」
何か。目が見えなければイケメンなのか。俺も明日からサングラスすればイケメンになれるのか? これはあれか、ゲレンデで出会う女がやたら美人に見える例の謎現象と同じやつか? それとも後ろ姿がきれいだと、それだけで美人に見えてきてしまう現象と同じやつか?
それで実際確かめてみると……。なははは。
俺は何も言っていない。
人間の脳というものは都合よく出来ているものだなあと実感する今日この頃。
と俺がゲレンデマジックの真髄に触れようとしているところで祖父江は続けた。
「まあ、そこは気にしたら負け」
「……で、杏さんもハマってるわけ?」
「いや、私はそこまでかなあ。皆が聞いてるからちょっと話題合わせるためにさ……」
そう言って彼女は肩をすくめた。
大方グループの女子がその話ばかりするのだろう。興味がなくても情報のアップデートに励むとはご苦労なことで。
その点男子はいいぞぉ。共通の趣味さえあれば言葉がなくても仲良くなれるからな。
……まあ俺友達いないけど。
いや、いないことはなかった。小学生のとき「俺たち友達だよな!」って確認したら、目をそらされたあと「え、……うん、まぁ」みたいな反応くれた子が四人はいたから。
……やったぜ。祖父江入れると五人だ。あと一人増やせば皆で王下七武海ができる。めっちゃ弱そう。特に俺。