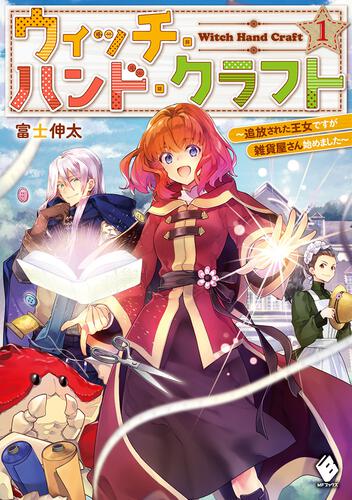凶運のキャロル/覆水は盆に返り、割れたカップも元通り/悪魔のガトーマジック 8
ジルは、割れたカップや皿をすべて引き取って自分の屋敷へと帰った。
「どうしたんだい、そんな暑苦しい格好して?」
屋敷に戻ったジルは長袖のチュニックとワイドパンツに着替え、エプロンを着けた。さらには手袋を嵌めている。上着もエプロンも厚手のものではないが、真夏の時期の格好としては流石にモーリンの言う通り、暑苦しい姿だ。
「かぶれ防止のためですね。アレを使おうと思います」
「ああ、前にご主人様が森で集めてた変な樹液だね? カブトムシでも飼い始めたのかと思ったよ」
「ウチにはすでにカニが居ますから間に合ってますね」
「危ない作業なら手伝うよ?」
モーリンが心配そうに尋ねるが、ジルはへっちゃらとばかりに手をひらひらさせた。
「ご心配するほどじゃないですよ、細かい作業は得意ですから。それでは作業部屋で作業していますね」
「また変なこと思いついたんだね……。ま、良いさ。気をつけるんだよ」
「へ、変じゃないですよ! 素晴らしいものです! あ、でも試着するような衣服じゃないんですよね、残念ながら」
「はいはい、楽しみにしてますよ」
モーリンの気のない返事を背中で聞きつつ、ジルは作業部屋へと入る。
「さーて、ついにこれを使う日が来ましたね……」
ジルが、作業部屋のテーブルの下に置いてある木箱を開けた。
そこには土色の液体の入った小瓶が収納されていた。
「木椀に塗って漆器を作ろうかと思いましたが、量がそんなに取れなくて迷ってたんですよね……金継ぎならそこまで量は使わないでしょうし、丁度良いでしょう」
小瓶の中身は漆だった。
その中でも、生漆、と呼ばれるものだ。
そもそも漆とは、漆の木から採取する樹液から作られる。木の幹に傷を付けて樹液を採取したばかりのものを「あらみ」と呼び、あらみを濾過したものを「生漆」と呼ぶ。
通常、漆器に使われる漆とは生漆ではない。ここから更に精製を加えた透き漆や、透き漆に顔料を加えて黒色や朱色にした色漆などに加工され、それを木製の食器などに塗られて漆器ができあがる。
では、精製もされず色も樹液の色のままの生漆を何に使うか。
その答えの一つは、硬化剤であり接着剤であった。
「まずは、キャロルさんから預かったカップを蘇らせてみましょうか。金継ぎを使って……!」
ジルは懐から、アカシアの書を取り出した。
今、アカシアの書の表紙には不思議な陶器の写真が載っている。
それは真っ黒い茶碗に稲光のような、金色の筋が走っている不思議なものだった。
タイトルにはこう書かれている。
『初めての金継ぎ』と。
「しかし異国の茶碗は不思議ですね……。でこぼこで均一じゃないのに、不思議な気品があるというか……」
金継ぎとは、陶磁器の割れた箇所を漆で接着したり、あるいは欠けた部分そのものを漆で補い、その上を金粉で装飾して修復する修復技法のことである。
この修復技法の特徴の一つは、食器や茶器としての機能を損なうことがないことだ。漆は硬化してしまえば皮膚にダメージを与えることはない。また金も他の物質と反応しにくいため、食器として問題はない。
そしてもう一つの特徴は、見た目の変化そのものを美観へと活かすことだ。金継ぎは日本の室町時代、茶の湯の世界で生まれたとされている。割れてしまった器の金継ぎした箇所は『景色』と呼ばれ、茶人たちは補修した箇所を欠点ではなく美点として捉えた。
ジルは『アカシアの書』を手にしたばかりのときに徹夜で読みふけったが、この『初めての金継ぎ』の内容は今ひとつ理解できていなかった。「茶碗もあまり美しくは見えないし、これをツギハギで補修するくらいなら作り直した方が良いのでは?」と感じた。むしろ漆を使うのであれば、漆黒や朱色の漆器を作りたいと最初ジルは思っていた。
だが、様々な染め物に手を出し、自分の手で服を作り、その背景にある美意識に触れてきたことで、「金継ぎの景色を楽しむ」という感覚を理解した。均整の取れたものや純粋な色を尊ぶアルゲネス島における美意識では生まれにくい造形を「あっ、これはこれですごく面白い」と思えるようになった。
「私の予想が正しければ、この白いカップに金は凄く見栄えすると思うんですよね」
キャロルから預かったカップやソーサーを取り出した。
薄緑色や青色の舶来品のカップもあれば、白磁に絵付けをしたものもある。
だが一番多いのは、何の絵も描かれていない白磁のティーカップだった。
白磁は、このアルゲネス島において高級品だ。
特に絵や文様などのない、ごくごくシンプルなものは根強い人気がある。
人気があるため数も多く作られており、貴族や高級商人などではない庶民であっても金を貯めれば決して手に入らないものではない。そんな大衆的なところがありながらも、白磁には色あせない佇まいがある。まさに白磁らしい白磁であり、茶器らしい茶器だ。混じりけのない色と形状は美術品としても実用品としても評価が高い。茶導師の中でも愛用する人間は多い。
だが割れてしまえば実用品としてはおしまいだ。それが一般的な通念というものだ。
ジルは今、その通念に叛逆してみようと決意した。
「まずは断面を磨いて、生漆を塗って、と」
粗い目のヤスリで、割れたカップの断面を磨いて面取りしていく。
それが終わったら、ジルは細い筆を使い断面に生漆を塗り始めた。本格的に割れた箇所を接着する前に、割れてもろくなった断面を補強するためである。
ジルは生漆を丁寧に均一に塗り終え、ひとまず筆を置いた。
「叛逆は一日にして成らずですね。今日はここまで」
割れたカップを、ジルは箱に収める。
今日の作業はこれだけだ。
漆を使った作業は『寝かせる』時間がどうしても多い。
◆
そして次の日、再びジルが作業を始めた。
次の工程は、生漆が馴染んだカップの断面に麦漆を塗るというものだ。
麦漆とは、水で練った小麦粉と生漆を混ぜて作った接着剤である。これを断面に塗り、割れたカップをくっつける。
「耳たぶくらいの硬さに練る……と言っても耳たぶの硬さってよくわかんないんですよね……。でも小麦粉関係のレシピ本って大体『耳たぶくらいの硬さに練る』って書いてあるから、この本が書かれた国の人にとっては凄くわかりやすい表現なのでしょうね。……まあ、このくらいで良いでしょう」
ジルはそんな独り言をつぶやきながら、練った麦漆を割れた面に塗る。
そして、面と面をくっつけた。
「ぺたりぺたり……と。このくらいで良いでしょう。あとは固定して、と」
ただし粘着力が発揮するまで時間がかかるため、動かないように糊を塗った紙で貼り合わせてしっかりと固定する必要がある。ジルは糊を塗った紙をカップの割れ目に貼り付けた。
「よし!」
まるで怪我人の傷口に包帯を巻いているときのような、不思議な慈しみと喜びがジルの心に湧き上がった。見た目はまだまだ不格好で痛々しい。それでも予感と手応えを感じた。このカップを、もう一度使えるようになると。
「はーい、漆が固まるまでベッドで安静にしててくださいねー……【濃霧】、【発熱】」
ジルが魔法を唱えた。
漆を硬化させる乾燥工程のために、湿気と温度を維持する必要があった。
割れた陶磁器などを麦漆で補修した後は一週間から二週間ほど「漆風呂」という高い湿度を保った場所で寝かせる。漆は空気中の水分を取り込んで硬化するためだ。
そのため「乾燥」と呼ばれる工程でありながらも、実際は「湿度が70%から85%、摂氏24度から28度の場所へ置く」という不思議な段取りをしなければいけないのだった。
「魔法で直接、水分を取り込ませても良いんですが……漆の性質がまだよくわかりませんね……。まあ、慣れたら色々試すとしてまずは教本通りにやってみましょう」
そして一週間ほど寝かせた後は、完全に固まった麦漆がはみ出た箇所を削って磨く作業が待っていた。これも地道な作業だ。まずは彫刻刀で粗く削り、その後は丁寧に磨くしかない。そこに砥の粉という岩石から作った粉末と生漆を混ぜた「錆漆」を塗って、また磨く。
そして次に金粉を張るための下地となる漆を塗り、また磨く。この作業を三回ほど繰り返してようやく表面に金を貼り付ける「蒔き」の工程へと辿り着く。金継ぎは「ひたすら漆を塗り、削り、磨く」という単調だが精密さの求められる作業の連続だった。ピクルスを漬けるような待ちの時間と地道な作業の連鎖に得意なジルも流石に少し疲れた。最終的に金継ぎが完成するまで一ヶ月近くかかってしまった。
とはいえジルは金継ぎしかしていなかったわけではない。並行して雑貨店の支店のリフォームの打ち合わせも進めていた。マシューの知人を通して大工を雇い、古くなった床板を張り直したり、カラッパがうっかり壊した玄関を直したり、壁紙を張ったりと、こちらは順調に進んでいた。
そして、共に完成の日を迎えようとしていた。
ご覧頂きありがとうございます!
もし「面白かった」、「続きが読みたい」と思って頂けたならば
下記にある広告下の【☆☆☆☆☆】で評価して頂けますでしょうか。
(私の作品に限らず、星評価は作者の励みになります)
どうぞよろしくお願いします。